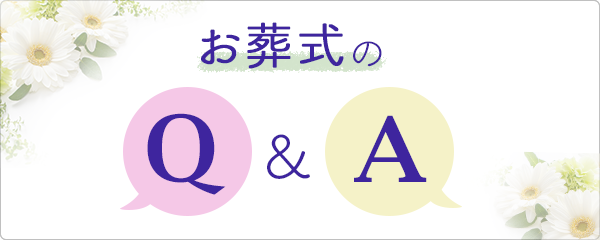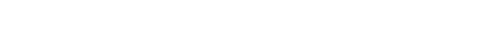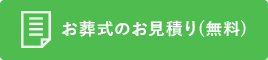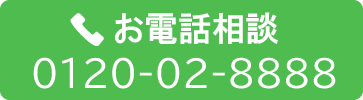通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/09/18
更新日:2025/09/18

 目次
目次初七日(しょなのか/しょなぬか)は、命日から7日目に営む最初の追善供養で、四十九日へ続く中陰(ちゅういん)期間の出発点といわれます。近年では、葬儀当日に初七日法要を合わせて行うケースも増え、地域や寺院の方針によって進め方が異なることもあります。
そのため「初七日の数え日は?」「繰り上げ・繰り込みの違いは?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。
そこで本記事では、初七日の意味や数え方、法要の流れ(別日/葬儀当日)、位牌の扱い、マナー、忌中に控えたいことなどを詳しく解説します。落ち着いて準備を整え、故人への感謝を穏やかに表せるよう、ぜひお役立てください。
● 初七日の意味や役割を知りたい人
● 初七日の数え方を知りたい人
● 初七日の法要の流れを知りたい人
● 初七日法要と位牌の関係を知りたい人
● 初七日法要のマナーを知りたい人
初七日(しょなのか/しょなぬか)は、故人が亡くなってから最初に迎える追善供養であり、四十九日へと続く一連の法要の出発点です。もっとも早い節目であるため、ご遺族にとっては気持ちの区切りをつくり、落ち着いて弔いを整えていく大切な機会となります。
従来は命日を1日目として7日目に営む法要でしたが、近年では葬儀当日に初七日法要を合わせるケースも一般的です。
追善供養とは、遺された方が読経・焼香・供花や供物、善行(寄付・清掃など)を通じて、その功徳を故人へ回向することです。中陰(ちゅういん)期間中に営まれる各法要は、この追善供養を節目ごとにかたちにする場であり、初七日はその最初の機会にあたります。
仏教では、逝去から四十九日までの49日間を「中陰(ちゅういん)」と捉え、7日ごとに法要を重ねます。七つの節目のうち最初が初七日、最後が四十九日(満中陰)で、四十九日は忌明けの大きな区切りとされます。
初七日は、こうした中陰の始まりの節として、故人を偲び感謝を伝えるうえで大切な意味を持ちます。
初七日の読み方は「しょなのか」または「しょなぬか」です。
日本の仏教説話では、此岸(この世)と彼岸(あの世)は「三途の川」で隔てられているとされています。諸説ありますが、初七日ごろにその川辺へ至る、またはこの頃に渡河するといわれることもあります。いずれにしても、初七日は「冥路の旅のはじまり」として重んじられる節目なのです。
初七日から七七日(四十九日)までの主な節目は次のとおりです。
| 法要名 | 読み方 | 命日からの時期 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 初七日 | しょなのか しょなぬか |
7日目 | 中陰供養の最初の法要。最初の追善供養の節目。 |
| 二七日 | ふたなのか | 14日目 | 引き続き読経・焼香で功徳を回向する節。 |
| 三七日 | みなのか | 21日目 | 三度目の節。供養を重ね、遺族の心の整理が進む頃。 |
| 四七日 | よなのか | 28日目 | 中陰の中間点。地域により読経後に会食を伴う場合もある。 |
| 五七日 | いつなのか | 35日目 | 四十九日に向け、本位牌の準備や日程調整など実務を整える時期。 |
| 六七日 | むなのか | 42日目 | 満中陰直前。納骨や返礼品、挨拶文など最終確認を行う時期。 |
| 七七日(四十九日) | しちなのか | 49日目 | 中陰が明ける大きな区切り(忌明け)。本位牌への切り替え・納骨を行うことが多い。 |
ただし、上記は一般的な例です。宗派や地域、菩提寺の教えにより、法要の内容は異なる場合もあります。迷われた際は寺院・葬儀社へご相談ください。
初七日の数え方の基本は「命日を1日目として7日目に営む」という方法です。ただし、地域や寺院・宗派の方針で数え方が異なる場合もあり、主に「数え日」と「満日」の2つの数え方があります。
「数え日」とは、命日を1日目として数える方法です。一般的に広く用いられており、たとえば「4月1日逝去の場合、初七日は4月7日」になります。
それに対して「満日(まんにち)」は、命日の翌日を1日目として数える方法です。関西や北陸の一部の地域で採用されることがあり、日付が1日後ろ倒しになります。たとえば「4月1日逝去の場合、初七日は4月8日」になります。
数え日と満日のどちらで数えるべきか、悩んだ際は菩提寺や葬儀社に確認してみましょう。
初七日は仏教の法要ですが、ほかの宗教にも「故人を偲び、感謝を表す」という初七日に近い役割を担う儀式があります。
たとえばキリスト教では「初七日」という枠組みは用いないものの、カトリックでは追悼ミサ、プロテスタントでは記念式(記念礼拝)などを行い、葬儀後の一定の時期に祈りを捧げます。日数の取り決めは一律ではなく、教会の運用やご家族の事情に合わせて日程を定めるのが一般的です。
一方で、神道には仏式の初七日に相当する決まった法要はなく、十日ごとの霊祭(十日祭・二十日祭・三十日祭・四十日祭・五十日祭)を重ねるかたちで区切りを迎えます。
いずれの宗教でも、形式や日数の考え方は異なりますが、故人を偲び、その想いを形にするという趣旨は共通しています。ご家族の宗教・宗派に即して、所属する寺院・教会・神社へ相談しながら進めましょう。
仏教宗派の1つである浄土真宗では、初七日法要の意味合いが、ほかの宗派と異なります。
浄土真宗では、故人が亡くなると阿弥陀如来のはたらきにより、すぐに極楽浄土へ往生できるとされています。そのため、初七日は「成仏を祈る供養の場」よりも、故人への感謝と仏縁を深める場としてとらえるのが基本です。
亡くなられた日(命日)から四十九日までの期間は、故人を偲び、喪に服して静かに過ごす「忌中(きちゅう)」とされています。忌中は、慶事や華美な振る舞いを慎むのが一般的です。
とくに初七日までは、次のような行動は控えるのが望ましいでしょう。
・旅行
・家の新築
・正月のお祝い
・神社へのお参り
・お祭りへの参加
・結婚式の実施や参加
あらかじめ予定が決まっている行事は時期を改めるか、やむを得ない場合でも規模を抑え、祝い事や華美な振る舞いを避けるなどの配慮を検討しましょう。ただし、上記は一般的な例であり、地域や宗派、寺院の方針によって扱いが異なる場合もあります。
初七日は、別日に行う伝統的な形式と、葬儀当日に合わせて行う現代的な形式があります。いずれの場合も、地域や寺院の方針、会場の運用によって段取りが変わるため、事前に菩提寺・葬儀社と流れを確認しておくと安心です。
ここでは、一般的な初七日法要の流れをご紹介します。
葬儀とは別日に初七日法要を行う伝統的な形式では、寺院や会館、ご自宅が会場となるのが一般的です。主な流れは以下のとおりです。
・開式の準備(到着・受付)
・読経(約30分〜45分)
・焼香(参列者の順に)
・僧侶からの法話(あれば)
・喪主・遺族代表の挨拶
・精進落とし(会食)
・解散、お布施のお渡し
祭壇には、白木位牌(内位牌)と遺影をおまつりし、供花・供物を整えます。読経ののち、参列順に焼香を行い、僧侶の法話、喪主・遺族代表の挨拶で締めくくります。
その後は、故人を偲ぶ場として「精進落とし(会食)」を行う場合もあります。お布施は、僧侶の退席直前または僧侶の控室でお渡ししましょう。
近年では、ご遺族や参列者の負担を軽減するために、初七日法要を葬儀と同日に行うケースが増えています。葬儀当日に初七日を行う場合は「繰り上げ法要」と「繰り込み法要」の二通りの方法があります。
「繰り上げ法要」とは、火葬後に葬儀場へ移動してから初七日法要を行う形式です。一般的な流れは、以下のとおりです。
・葬儀、告別式
・出棺
・火葬
・初七日法要
・精進落とし
・解散
繰り上げ法要は、遺骨(骨壺)をおまつりして落ち着いた雰囲気で営める点がメリットです。一方で、火葬場と会場の移動が発生して拘束時間が延びやすいため、僧侶の予定と火葬場スケジュールを踏まえた時間配分が鍵になります。
「繰り込み法要」とは、火葬前に初七日法要を行う形式のことです。一般的な流れは、以下のとおりです。
・葬儀、告別式
・初七日法要
・出棺
・火葬
・精進落とし
・解散
会場内で完結するため移動負担が少なく、参列者の拘束時間を短縮しやすいのがメリットです。ただし式全体が長時間化しやすく、参列者が多い場合は法話の短縮・省略となることもあります。また、地域や寺院によっては式中実施となる「繰り込み法要」を推奨しない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
近年、初七日法要を葬儀当日にまとめて行う(繰り上げ・繰り込み)や、7日ごとの法要を省いて「初七日と四十九日の二本立て」にするといった省略・一括化を選ぶケースが増えています。
その背景には、都市部を中心とした火葬場や式場の予約の取りにくさや、参列者の高齢化、遠方からの移動負担、学校・仕事の調整の難しさといった現代ならではの事情があります。
初七日の省略・一括化を選んだからといって、供養の心が減るわけではありません。初七日の省略・一括化のメリットや注意点を理解したうえで、本来の初七日に当たる日にご自宅で手を合わせたり焼香やお念仏を捧げたりなど、故人への供養の気持ちを各々で表すとよいでしょう。
ここからは、初七日の省略・一括化のメリットや注意点を紹介します。
初七日の省略や一括化には、移動や再集合の回数を減らせる、会場・寺院・火葬場の日程調整が一本化できる、返礼・送迎・会食手配の重複を避けやすいといった実務上の利点があります。
また、僧侶や会場の手配を葬儀と合わせて行うことで、希望の日取りが実現しやすくなる点もメリットです。
ご遺族にとっても拘束時間や準備の負担が軽くなり、気持ちを整えながら見送りに向き合えるでしょう。
初七日の省略・一括化に関しては、寺院の方針や地域慣習について事前の確認が欠かせません。葬儀当日に初七日を組み込むのが慣習的に難しい地域や、読経時間・法話の取り扱いに独自の定めがある寺院もあります。
また、葬儀当日に初七日法要を実施する場合は、案内状や式次第に方式(繰り上げ/繰り込み)と集合・解散時刻、参列範囲(親族のみ/一般会葬者も参加)を明記しておきましょう。精進落としの有無や人数、送迎動線もあわせて整えておくと安心です。
お布施・御膳料・お車代は用途ごとに封筒を分け、渡すタイミングや表書きは菩提寺の指示に従うのが基本です。
初七日の時点では、白木位牌(内位牌)を祭壇におまつりします。
白木位牌は、葬儀から四十九日までのあいだ用いる仮の位牌であり、塗りや装飾を施さない白木で仕立てられた一時的な礼拝具です。戒名(法名)や俗名、没年月日などを記し、四十九日までの期間、礼拝の中心となります。
一方、本位牌は四十九日までに用意し、当日に開眼供養(魂入れ)をして仏壇へ安置するのが一般的です。材質や意匠(塗り位牌・唐木位牌など)、文字の入れ方、連名位牌の可否には寺院や地域の考え方が反映されるため、事前に菩提寺へ確認して進めましょう。また、本位牌の名入れや仕立てには一定の期間を要するため、早めの手配が安心です。
役目を終えた白木位牌は、寺院での焚き上げや、寺院の指示に従った適切な納め方でお別れします。宗派や地域の慣習に違いがありますので、不明点は菩提寺に相談してください。
最後に、事前にチェックしておきたい初七日法要のマナーをご紹介します。
喪主は、葬儀と同様に黒の正喪服を着用します。参列者は準喪服の着用が基本ですが、略喪服の場合もあります。光沢の強い素材や派手な装飾は避けましょう。
アクセサリーは白・グレー系の一連パール程度にとどめ、髪型やメイクは控えめに整えます。
葬儀と同日実施の場合は、香典を葬儀分に含めるのが一般的です。別日実施の場合は、地域相場や故人との関係性に応じて包みます。
表書きは「御霊前」が広く用いられますが、浄土真宗では「御仏前」とする慣習があります。
喪主の挨拶は参列者への御礼と無事に執り行えたことの報告を簡潔に述べ、精進落としや解散の案内で締めます。
参列者は「心よりお悔やみ申し上げます」や「ご冥福をお祈り申し上げます」といったお悔やみの言葉を短く伝え、司会や導師の案内に従って焼香・着席を行います。
お布施の金額は寺院・地域差が大きいため、菩提寺へ事前に確認しておくといいでしょう。お布施・御膳料・お車代は用途ごとに封筒を分け、退席直前または控室で静かにお渡しします。また、表書き・水引・渡すタイミングは寺院の指示に合わせます。
初七日法要のあとに行う「精進落とし」は故人を偲び、支えてくださった方々に感謝を伝える会食です。献杯の挨拶は簡潔に行い、過度に賑やかになりすぎない進行を心がけましょう。
精進落としを行わない場合は、食事の代わりとしてお弁当や返礼品を渡します。僧侶には、お布施と一緒に御膳料をお渡しします。
初七日(しょなのか/しょなぬか)は、命日から7日目に営む最初の追善供養です。初七日の数え方には「数え日」と「満日」があり、地域や寺院の方針によって扱いが異なります。
初七日の法要は、葬儀とは別日に行う従来の形式のほか、近年では葬儀当日に行う「繰り上げ法要」や「繰り込み法要」が選ばれるのが一般的です。こうした初七日法要の意味や流れをあらかじめ確認しておくことは、穏やかなご供養につながるでしょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。