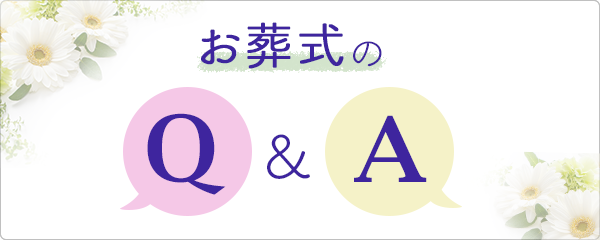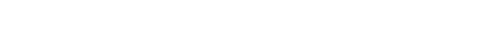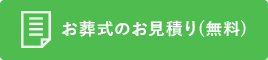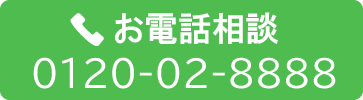通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/07/29
更新日:2025/07/29

 目次
目次親を亡くしたその日は、悲しみと混乱の中、何から手をつければいいのか分からず茫然としてしまうでしょう。しかし、葬儀の準備や役所への届け出、相続手続きなど、遺された家族が進めるべきことは数多くあります。
本記事では、親のご逝去後すぐに取りかかるべき手続きと準備を、当日から翌日、さらに翌々日までの流れに沿って丁寧に解説します。死亡診断書の受け取りや訃報連絡、葬儀社の選定から各種届出、さらにその後の相続手続きまで、ステップごとにわかりやすくご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。
● 親の葬儀のやることチェックリストが知りたい人
● 親が亡くなった当日にやることを知りたい人
● 親が亡くなった翌日・翌々日にやることを知りたい人
● 親が亡くなってから2週間以内にやることを知りたい人
● 親の葬儀以降の相続手続きについて知りたい人
親を亡くした直後は、悲しみのなかで何を優先すればよいか戸惑うことでしょう。そこでまずは、ご逝去当日から葬儀前、葬儀後、さらには相続手続きまで、時系列でやることをまとめたチェックリストをご用意しました。
|
時期 |
やること |
|---|---|
|
当日 |
●死亡診断書/死体検案書の受け取り |
|
翌日(2日目) |
●お通夜の準備・実施 |
|
翌々日(3日目) |
●葬儀(告別式)の実施 |
|
2週間以内 |
●世帯主変更届の提出 |
|
3ヶ月以内 |
●相続放棄の判断・借金の有無の確認 |
|
10ヶ月以内 |
●遺産分割協議 |
|
落ち着いたあと |
●葬祭費・埋葬料の請求(2年以内) |
ただし、ご逝去のタイミングや葬儀社、寺院との調整により、お通夜や葬儀・告別式のスケジュールに遅れが生じることもあります。具体的なスケジュールについては、葬儀社に相談して見ましょう。
ここからは、それぞれの項目について詳しく解説します。
まずは、親が亡くなった当日に行うべきことを詳しく見ていきましょう。
まずは、死亡が確認された場所に応じて医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取りましょう。これらの書類は後日、役所での「死亡届」の提出や火葬許可申請に必要になります。
病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合では、以下のように手続きの流れや対応が異なります。
ご臨終の確認後、担当医師から「死亡診断書」を受け取ります。
死亡が持病などで「自然死」と判断でき、かつ直近に診察を受けている(または医師が訪問して死因を確認できる)場合は、かかりつけ医からそのまま「死亡診断書」を発行してもらいます。
医師による診察ができないため、まずは警察に連絡し、警察官による検視ののち、検案医(警察医)が「死体検案書」を発行します。
大切な親を失ったショックの中でも、親族や関係者への連絡はできるだけ早めに行いましょう。事実を正確に伝えることで、後日の混乱を避けられます。
まずは、家族や親族に電話で連絡を入れます。当日に訃報連絡を行う親族は、3親等以内の方が一般的です。
この時点では、通夜や葬儀の日程が未定の場合が多いですが「○月○日に亡くなりました。詳細は追ってご連絡します」といった簡潔な伝え方で構いません。とくに高齢の親族や目上の方には、メールでの連絡は避け、対面や電話で丁寧に知らせるのがマナーです。
会社勤めの方は、上司や人事担当者に訃報を伝え、忌引き休暇の取得を申し出ます。
忌引き休暇は通常1週間程度が一般的ですが、各社の規定によって異なるため確認しましょう。また、香典や弔電の受け取り方法も事前に決めたうえで、詳細を会社に伝えます。香典や弔電の受け取りを辞退する場合は「お気持ちだけで結構です」と明確に伝えましょう。
忌引き休暇明けには、改めてお休みをいただいたお礼を述べることも忘れないように注意してください。
訃報の連絡と並行して、葬儀社の選定を行います。まずは故人が生前に示していた意向(遺言書やエンディングノート)を確認し、指定の葬儀社があれば優先的に連絡を取りましょう。とくに指定がない場合は、2〜3社から見積もりを取り、費用やプラン内容を比較検討するのがおすすめです。
葬儀社が決まったら、日程の調整や式場の手配を進めます。日程調整をする際は以下の点に注意しましょう。
・六曜や仏滅の配慮
・式場・斎場の空き状況
・喪主・親族の都合
・僧侶(司式者)の都合 など
「友引」は友を"引く"という解釈から葬儀を避ける習慣があり、斎場が休業となるケースもあります。近年は友引を気にしない方も増えていますが、希望日を決める際は六曜とあわせて斎場の営業日カレンダーを確認しましょう。
これらのポイントを踏まえ、葬儀社と綿密に相談しながら、参列者が無理なく集える最適な日程を設定してください。詳細は、下記の関連記事でも解説しています。
葬儀社が決まったら、まずはご希望やご予算、参列者の規模感に合った葬儀形式を選びます。以下の表では、一般的な4つの葬儀形式を比較しました。
| 葬儀形式 | 参列者数の目安 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般葬 | 60人~100人前後 | 150万円前後 | 1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式、火葬を行う。親族や友人・知人、同僚など広く参列を呼びかけるプラン。 |
| 一日葬 | 20人~40人前後 | 90万~100万円前後 | 通夜を省略し、告別式と火葬を同日に行うコンパクトなプラン。 |
| 家族葬 | 10人~25人前後 | 80万~90万円前後 | 親族やごく親しい友人のみで執り行うアットホームなプラン。通夜を行う一般葬形式と通夜を省略する一日葬形式がある。 |
| 直葬 | 20人前後 | 45万円前後 | 通夜、葬儀・告別式を省略し、火葬のみを行うシンプルなプラン。 |
葬儀の形式を決める際は、費用・参列者数のほか、故人のご意向や宗派のしきたり、参列者の移動・宿泊の負担などを総合的に考慮し、葬儀社と十分に打ち合わせを行うことが大切です。
メモリアルアートの大野屋では、故人やご家族のご意向に沿ったプランをご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。
また、我が家のようなくつろぎの空間で、お別れの時をお過ごしいただける「リビング葬」のプランもご用意しています。
葬儀費用は、式場使用料、祭壇費、僧侶へのお布施など項目ごとに異なります。見積書をもとに支払い方法や時期を確認し、不足がないように準備を進めましょう。
資金は故人の預貯金や葬儀保険、互助会の積立金、親族間での分担金で賄うのが一般的です。急な出費が困難な場合は、葬儀ローンを活用して分割払いにする方法もあります。
これらを踏まえ、家族で資金計画を立てておくことで、当日になって慌てずに対応できるでしょう。
葬儀社と連携し、病院またはご自宅から安置場所へのご遺体搬送を手配します。搬送料金や搬送車両の手配時間も事前に確認し、安置場所までスムーズに運べるようにしましょう。
搬送後は、斎場や安置施設の安置室で適切にご遺体を保冷・管理してもらいます。ご自宅での安置を希望する場合は、専用の安置用ベッドやドライアイス補充の手配についても葬儀社と相談し、衛生面と安全面に配慮できる環境を整えてください。
葬儀の準備が本格化する2日目は、お通夜の開催と並行して役所への手続きを進めることが大切です。参列者の案内や式場準備を進めながら、法的な届出を忘れずに行いましょう。
※一般的には、亡くなった翌日にお通夜、その翌日に葬儀が営まれますが火葬場に空きがないなどの状況により、スケジュールに遅れが生じることもあります。
お通夜は親族やご友人が故人を偲び、最後のお別れをするための儀式です。一般的な流れは以下のとおりです。
●受付
●式場内着席
●通夜開式
●読経
●焼香
●説教法話
●喪主の挨拶
●通夜終了
お通夜のあとに「通夜振る舞い」を行う場合もあります。通夜振る舞いとは、故人を偲びながら簡素な料理や飲み物を振る舞い、参列者同士や遺族が故人との思い出を語り合う場のことです。食事を通じて交流を深め、参列者の心を和ませる大切な時間となります。
お通夜の準備と並行して、市区町村役場での届出を行います。死亡届は「死亡診断書(または死体検案書)」を添えて、故人が亡くなった日から7日以内に提出してください。
届出を受理してもらうと同時に「火葬許可証」が交付されますので、これを火葬場に提出して火葬の手続きを進めましょう。役所窓口での手続きは平日のみの場合が多いため、スケジュールに注意しながら進めましょう。
続いて、親が亡くなった翌々日に行う葬儀・告別式から火葬、そして初七日法要について見ていきましょう。
※一般的には、亡くなった翌日にお通夜、その翌日に葬儀が営まれますが火葬場に空きがないなどの状況により、スケジュールに遅れが生じることもあります。
葬儀・告別式では、僧侶による読経に加え、開式の辞や喪主挨拶、焼香や釘打ちなどの儀式が行われ、故人との別れを偲びます。一般的な流れは以下のとおりです。
●受付
●式場内着席
●僧侶入場
●開式の辞
●読経
●焼香
●最後のお別れ
●釘打ち
●喪主挨拶
●出棺
なお、葬儀の式次第は宗教・宗派によっても異なります。
出棺後は火葬場へ移動し、火葬を行います。火葬中は待合室で待機し、火葬が終了したら骨上げ(納骨のための骨拾い)を行います。火葬後には、故人の好物や季節の料理を囲みながら「精進落とし」として簡単な食事会を開くこともあります。
初七日法要は、本来は亡くなってから七日目に行う儀式ですが、近年では参列者の負担を減らすため、葬儀と同日に執り行うのが一般的です。
初七日の法要を行うタイミングには次の2種類があります。
繰込式(火葬前)
告別式の最後に続けて初七日を行う方法です。火葬前に一連の儀式を終えられるため、参列者にとって負担が少ないのがメリットといえます。
繰上げ式(火葬後)
火葬後に改めて初七日を行う方法です。火葬場から戻ったあとすぐ、または後日に別会場で行うケースがあります。
その後も、四十九日法要や一周忌、三回忌など節目ごとに法要を重ねていきますので、スケジュールに合わせて準備を進めていきましょう。
関連記事:
・四十九日法要とは?服装や香典のマナー、挨拶も文例付きで解説
葬儀が終了したあとも、さまざまな届け出や手続きを期限内に進める必要があります。ここでは、逝去後2週間以内に対応すべき主要な項目を解説します。
被相続人(お亡くなりになった親)が世帯主だった場合は、市区町村役場で「世帯主変更届」を提出します。世帯票と住民票の世帯主欄が正しく更新されることで、各種行政サービスや証明書発行がスムーズになります。
亡くなられた親が加入していた生命保険や共済からは、所定の期間内に保険金の請求を行う必要があります。保険証券、死亡診断書、被保険者の戸籍謄本など必要書類を揃え、保険会社窓口または代理店へ提出しましょう。
故人が年金を受給していた場合は、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出して受給停止手続きを行います。手続きが遅れると未支給年金の返還請求が発生する場合があるので、早めに届け出を済ませましょう。
被保険者(第1号・第2号問わず)が亡くなった場合は、市区町村役場で「介護保険資格喪失届」を提出します。この手続きにより、介護保険料の徴収が停止され、介護サービス利用記録が整理されます。
親名義の電気・ガス・水道などの公共料金や、携帯電話、インターネット回線、新聞購読などの契約は、速やかに解約または名義変更します。
停止日や名義変更の手続き方法は各社によって異なるため、早めに連絡してスケジュールを確定しておきましょう。
葬儀や法要がひと段落したあとは、相続人として正式に資産・負債の整理と名義変更を行います。以下の流れを参考に、期限内に必要な手続きを進めましょう。
まずは被相続人(故人)が遺言書を残していないか、遺言保管所や自宅、弁護士・司法書士などに確認します。
公正証書遺言であれば法務局の「遺言書保管制度」で管理されていることが多く、家庭裁判所での検認手続きを省略できます。自筆証書遺言の場合は、自宅保管のものでも必ず家庭裁判所で「検認(開封許可)」を受ける必要があるため、早めに申請してください。
相続の選択肢には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
単純承認
故人の資産も負債もすべて承継する方法です。特に手続きは必要なく、何もしないまま相続人となったことを知った日(通常は葬儀後)から3か月が経過すると、自動的に単純承認となります。
限定承認
故人の財産の範囲内でのみ債務を負担する方法です。申述すると、資産総額を超える借金の返済義務を免れることができます。
申述の際には「①相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出すること」「②官報公告または債権者への個別通知による債権者への公告手続きを行うこと」が必要です。
手続きは「相続開始を知った日」(通常は葬儀後)から3ヵ月以内に、すべての法定相続人がそろって家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄
故人の財産も負債も一切承継しない方法です。借金が資産を上回る場合や相続人間のトラブルを避けたい場合に有効で、家庭裁判所への申述期限は限定承認と同じく「相続開始を知った日」から3ヵ月以内です。
以上のうち、申述手続きを行わなければ自動的に単純承認となります。相続方法を選択する際は、故人の試算額や借金の有無を正しく把握することが大切です。また、限定承認か相続放棄を選択する場合は、必ず期限内に家庭裁判所へ申述してください。
遺産分割協議とは、相続人全員で故人の財産(不動産、現金、預貯金、株式など)や負債の分け方を話し合い、その内容を「遺産分割協議書」にまとめる手続きです。協議は、遺言書がない場合や遺言書に定めのない財産項目がある場合に必要となります。
協議書には、相続人全員の署名押印が必要です。銀行口座の凍結解除や名義変更、不動産の相続登記など、多くの手続きで原本の提出が求められるため、作成後は原本を大切に保管しましょう。
なお、協議のタイミングは、葬儀後から1〜3ヵ月以内に行うのが一般的です。法的な期日はありませんが、預貯金口座の凍結解除や相続税申告(相続開始から10ヵ月以内)に必要なため、10ヵ月以内を目安に「遺産分割協議書」を作成・署名押印しておくといいでしょう。
葬儀が無事に終わり、日常生活が少し落ち着いてきたら、葬祭費や医療費の精算、遺族年金といった各種給付の請求手続きを進めましょう。期限を過ぎると請求できなくなるものもあるため、できるだけ早めに必要書類を準備して役所や保険者へ申請してください。
国民健康保険に加入していた故人が亡くなった場合や、社会保険(協会けんぽ・健康保険組合等)で葬儀費用の給付制度がある場合、それぞれ葬祭費(埋葬料)の請求が可能です。
申請先
●国民健康保険:市区町村役場の保険年金課
●社会保険:勤務先を通じて加入していた健康保険組合
主な必要書類
●申請書(各保険者所定様式)
●葬儀費用の領収書(葬儀社発行)
●戸籍謄本または死亡届受理証明書
●故人の保険証
請求期限
葬儀を行った日から2年以内
申請後、数週間程度で振込により給付されます。詳しい手続き方法は、お住まいの市区町村や健康保険組合にお問い合わせください。
故人が亡くなる前に高額な医療費を自己負担した場合、実際に支払った金額が「高額療養費」の自己負担限度額を超えていれば、その超過分を払い戻し請求できます。
請求先
故人の健康保険者(国保は市区町村、社保は組合)
必要書類
●高額療養費支給申請書(保険者所定)
●医療費の領収書(対象期間すべて)
●通帳コピー(振込先口座)
●戸籍謄本または死亡届受理証明書
申請期限
医療費を支払った月の翌月初日から起算して2年以内
手続き完了後、過払いとなっている分が指定口座に振り込まれます。
故人が公的年金(厚生年金・共済年金)に加入していた場合、ご遺族は遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取る権利があります。申請は亡くなった日から5年以内と期限が長めですが、早めの手続きが望まれます。
請求先
最寄りの年金事務所または日本年金機構の窓口
主な必要書類
●年金請求書(年金事務所窓口で入手)
●故人の年金手帳または基礎年金番号通知書
●戸籍謄本・住民票の除票(続柄がわかるもの)
●受給者の振込先通帳
●戸籍附票、婚姻・離婚の記録など(該当者のみ)
給付内容
●お子さまがいる場合は遺族基礎年金
●配偶者や子どもが受給可能な厚生年金加入者の場合は遺族厚生年金
申請期限
亡くなった日から5年以内
提出書類に不備があると手続きが遅れるため、窓口で詳細を確認しながらそろえてください。
親の葬儀は、深い悲しみの中で慌ただしく手続きを進める必要があります。死亡診断書の受取や訃報連絡、葬儀社の手配から法要、相続手続きまで、やることは多岐にわたります。
本記事でご紹介した時系列に沿ったステップを参考に、必要な手続きをひとつずつ着実に進めていきましょう。また、書類や日程調整、各種申請には期限や慣習上のポイントがあるため、早めの準備と確認が安心につながります。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。