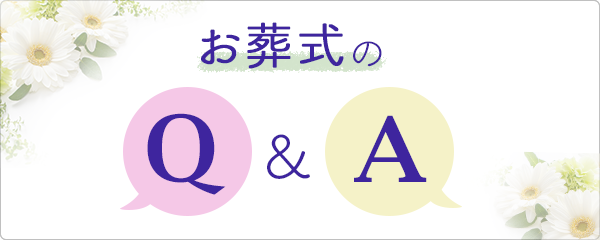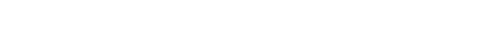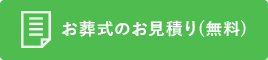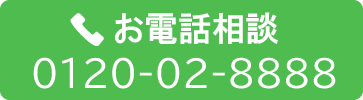通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/07/09
更新日:2025/07/09

 目次
目次密葬とは、ごく親しい身内だけで非公開に執り行う小規模なお葬式のことです。とくに故人が経営者や著名人などの場合、密葬を選ぶことで多くの弔問客への対応に追われることなく、ご遺族が落ち着いて故人との別れを偲ぶ時間を確保できます。
しかし一方で、参列者の範囲を明確に定めたり、情報漏洩を防いだりする配慮が欠かせません。
そこで本記事では、密葬の定義と選ばれる背景、家族葬・直葬との違い、メリット・デメリット、当日の流れと費用目安、さらに本葬後の通知や喪主・参列者のマナーまでを具体例を交えてわかりやすく解説します。大切な方を見送る準備として、ぜひ最後までご覧ください。
● 密葬の意味や背景を知りたい方
● 密葬と家族葬、直葬(火葬式)との違いを知りたい方
● 密葬のメリット・デメリットを知りたい方
● 密葬の流れを知りたい方
● 密葬の費用相場を知りたい方
● 密葬を行ったあとの対応を知りたい方
● 密葬の注意点を知りたい方
「密葬(みっそう)」とは、通夜や葬儀・告別式、火葬といった一連の儀式を、ごく近しい身内だけで非公開に執り行い、その後に改めて一般向けの「本葬」を催す葬儀形式です。
訃報の公開を控えたうえで身内のみで落ち着いて故人を見送り、後日に社葬や団体葬、あるいはお別れ会のようなセレモニーを行い、多くの参列者とともに故人を偲びます。
近年、故人のプライバシー保護や喪主・ご遺族の精神的負担の軽減を重視する動きが高まっています。
とくに、故人が著名人や経営者など社会的注目度の高い方の場合、訃報が大々的に伝わると、ご遺族は問い合わせ対応や弔問客への応対に追われ、本来ゆっくりと持つべきお別れの時間を確保できなくなる恐れがあります。また、多数の参列者を見込む葬儀では、会場や日程の調整が難航しがちです。
このような状況を避け、まずは身内だけで静かに故人をお見送りし、その後に本葬の準備を余裕をもって進められるのが「密葬」という形式です。
密葬、家族葬、直葬はいずれも少人数で行う葬儀形式ですが、それぞれ性質や流れに明確な違いがあります。本項では定義を整理しながら、密葬との相違点をわかりやすく比較します。
家族葬は、家族やごく親しい親族・友人のみを招いて一連の通夜・葬儀・告別式を行う小規模な葬儀形式です。一連のお別れの儀式を完結させるため、後日に本葬などは行わないのが一般的です。
一方、密葬は身内だけで一時的に葬儀を執り行い、その後に改めて一般参列者を招いた「本葬」を行います。
直葬(火葬式)は、通夜や告別式といった儀式を一切行わず、病院や自宅から直接火葬場へ向かい、火葬を執り行う最小限の葬儀形式です。遺体安置後すぐに火葬を行うため、時間も手続きもシンプルである反面、故人とのお別れの時間も短くなります。
密葬には、身内だけで儀式を行うことで得られるメリットがあります。ここでは、密葬ならではの主なメリットを3つ紹介します。
身内だけで行う密葬では、大規模な葬儀特有の慌ただしさや緊張感がなく、故人をゆっくりと偲ぶ時間を確保できます。通夜から告別式、火葬まで、親しい家族だけで過ごすことで、言葉にできない思いを心静かに伝えられるのが大きな特徴です。
著名人や経営者など、社会的に注目度の高い故人の場合、訃報が広まると問い合わせや弔問客の対応に追われます。こうした対応は、ご遺族にとって精神的にも身体的にも大きな負担となることも少なくありません。
密葬なら、事前に情報を抑えて身内のみで進められるため、過度な問い合わせ対応や参列者とのトラブルなどを未然に防ぐことができます。
密葬で火葬までを先に済ませておくことで、その後に本葬やお別れ会の準備に十分な時間的余裕を持つことができます。会場手配や日程調整を焦らず行えるため、ご遺族の精神的な負担も軽減できるでしょう。
また、柔軟な日程調整も可能となり、多くの参列者を招いた式典を計画しやすく、結果として質の高いセレモニーが実現できます。
密葬には大きなメリットがある一方、事前に理解しておくべきデメリットもあります。ここでは、密葬のデメリットとその対策について見ていきましょう。
密葬と本葬を別々に行う場合、会場使用料や祭壇設営、スタッフ人件費などが二度発生し、一般的な葬儀よりも費用がかさむことが考えられます。
こうした費用の増大を抑えるためには、密葬と本葬を同じ葬儀社にまとめて依頼し、プランを一括で契約する方法がおすすめです。葬儀社によっては、割引プランなどを用意していることもあるため、事前に見積もりを取り、項目ごとの内訳を比較しておきましょう。
身内のみで非公開の葬儀を行うと「なぜ知らせてくれなかったのか」「最後にひと目会いたかった」など、知人や関係先から疑問や不満が出る可能性もあります。
こうした心情的なわだかまりを防ぐために、密葬後は、できる限り速やかに死亡通知状を送付し「当日は身内のみで見送らせていただきましたが、改めてお別れの機会をご案内いたします」といったフォローを入れることが大切です。
密葬は、後日に広く参列者を招いて本葬を行うのが一般的です。しかし本葬を行わない場合、訃報を耳にした知人や関係先から、弔問やお別れ会についての問い合わせが相次ぎ、対応に追われてしまう可能性があります。
こうした辞退を避けるためには、あらかじめ案内状やウェブサイト上で「本葬・お別れ会は実施いたしません」と明確にお知らせし、問い合わせ窓口を一本化しておくとよいでしょう。もし、何らかの形でお別れのセレモニーを行う予定があれば、同時に周知しておくことで、参列希望者の不安を和らげられます。
密葬の流れは、一般的な葬儀とほぼ同様です。葬儀の内容やスケジュールに合わせて、1日で行う場合と2日間で行う場合があります。
密葬を1日で行う場合は、通夜を省略し、葬儀・告別式と火葬を同日中に行います。
通常、午前中あるいは午後の早い時間に葬儀会場や斎場に参列者(家族・近親者)が集まり、読経や弔辞、焼香を行ったうえで告別式を実施します。終了後はそのまま火葬場へ移動し、火葬の儀を経て収骨まで同日に行います。
参列者の負担軽減とご遺族の精神的余裕を考慮した、コンパクトなプランです。
故人との最後の時間をゆっくり確保したい場合は、儀式を2日間に分けて行います。
1日目の夕刻から通夜を行い、故人と最後の夜を家族で静かに過ごします。2日目は葬儀・告別式を行い、告別式後に火葬場へ移動して火葬の儀・収骨を行います。
1日目の夜間もご自宅や安置場所での付き添いができるため、ご遺族が故人と過ごす時間をしっかり確保できるプランといえます。
密葬の費用は、儀式の内容や規模によっても異なりますが、ここでは一般的な相場をご紹介します。
葬儀・告別式から火葬までを1日で行う場合の費用の目安は葬儀社への支払いが約30万円〜50万円、お布施(読経料)が10万円〜30万円ほどになります。
2日間に分けて行う場合は、葬儀社費用が80万円〜100万円、お布施が別途10万円〜30万円となり、1日で行う場合と比較して費用が高くなります。これは、式を分けることで会場使用料や人件費、搬送料、安置料などの諸費用がそれぞれ発生するためです。
ただし、葬儀の内容や規模によっては100万円以上かかる場合もあります。また、宗派や地域、戒名の位などによってお布施金額も変動します。
費用の詳細を知りたい方は、葬儀社に見積もりなどを相談してみることをおすすめします。
密葬を終えたら、その後の連絡と準備が重要です。とくに、死亡通知状の送付で密葬の実施を適切に説明し、本葬やお別れ会の日程を案内することで、知人・関係先の混乱を防ぎましょう。
密葬後はできるだけ速やかに死亡通知状を送付しましょう。文面には「葬儀は故人の遺志により近親者のみで相済ませました」と経緯を簡潔に伝え「お別れ会を下記のとおり予定しております」と案内日程を明記します。
【例文】
お別れ会のご案内
拝啓 春寒の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび□□年□月□日、□□(故人氏名)は□□にて永眠いたしました。
葬儀は故人の遺志により、近親者のみで相済ませました。
誠に恐れ入りますが、ご香典・ご供物は固くご辞退申し上げます。
ここに生前のご厚誼を深謝し、下記のとおり「お別れ会」を執り行いますので、ご多用中恐縮ではございますが、ご参席賜りますようご案内申し上げます。
記
日時:令和○年○月○日(○) 午前11時より
場所:○○ホテル (〒123-4567 東京都○○区○○町1-2-3/TEL 03-1234-5678)
会費:8,000円(当日、会場受付にて申し受けます)
服装:平服にてお越しください
なお、ご都合のほどを□□月□□日までに同封の返信はがきにてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
敬具
令和○年○月
喪主 □□□□
(連絡先)□□□□
通知状の文例やマナーについては、以下の記事もご参照ください。
本葬やお別れ会は、密葬に参列できなかった方々が故人を偲ぶための大切な機会です。
本葬は社葬や団体葬といった企業・団体主催の儀式形式を指し、参加者は社員や仕事関係者が中心となります。規模が大きく費用は企業負担となるのが一般的です。
一方、お別れ会はご遺族や友人が主催する、セレモニー的な形式です。宗教儀式を行わない場合も多く、会場や進行も自由度が高いのが特徴です。
本葬やお別れ会は、密葬後1週間〜1カ月以内を目安に規模に応じた会場を押さえ、早めに日時を告知しましょう。社葬では読経や献花といった宗教儀式を中心に行いますが、お別れ会では写真スライドや思い出スピーチ、会食を組み合わせると故人らしい式になります。
香典辞退の場合は受付表示を明示し、供花や弔電は別枠で受け付けられる体制を整えておくといいでしょう。
密葬は身内だけで静かに執り行う形式だからこそ、事前の段取りと内外への配慮が欠かせません。ここでは、喪主として押さえておきたいポイントを解説します。
参列対象となる親族や関係者をあらかじめリスト化し、案内状や電話で確実に連絡を取りましょう。招待範囲を明文化しておくことで、後のトラブルも防げます。
訃報を公開せずに行う密葬では、故人の安置場所や式次第の詳細も極力非公開で管理することが求められます。安置施設への立ち入りを制限し、SNSやメールでの情報拡散が行われないように最新の注意を払いましょう。
密葬は故人へのお別れを身内だけで静かに執り行う形式のため、従来の葬儀を想定していた親族から驚きや不満が生じることがあります。
事前に親族会を開き、密葬を選ぶ理由や進行の流れ、今後予定している本葬の計画などを丁寧に説明して理解を得ておくことが重要です。こうしておくことで、誤解や感情的な対立を未然に防ぎ、後の親族間トラブルを避けられます。
密葬では参列者がごく近親者に限られるため、儀式の雰囲気を落ち着かせるためにも、形式的な弔辞は省略するのが一般的です。
代わりに、通夜振る舞いやお別れ会の場で親しい方が簡単に思い出を語る程度にとどめると、故人を偲ぶあたたかな時間を保つことができます。
会社や団体に所属していた場合は、社内向けの最低限の訃報連絡を行い、忌引休暇の取得や弔意の手配をスムーズに行えるようにしましょう。
密葬後に行う本葬(お別れ会や社葬など)の開催時期・会場はあらかじめ仮押さえしておくと安心です。密葬当日に会葬案内状を手配できるよう、式次第や予算も早めに確定しておきましょう。
密葬では、訃報の伝達範囲や参列者リストの作成、本葬・お別れ会の準備など、細やかな配慮と調整が求められます。スムーズに葬儀の準備・進行を行うためには、密葬の実績がある葬儀社との連携が重要です。
実績豊富な葬儀社であれば、非公開での案内文作成から式場の手配、当日の進行管理まで一括してサポートを受けられるため、不慣れな遺族が直面しやすい「誰に何を伝えるべきか」「どのタイミングで次のセレモニーを案内するか」といった判断ミスや情報漏れを防げます。
また、本葬やお別れ会の規模や形式を事前に共有し、プランを一元管理しておくことで、重複する手配や過剰なコスト発生のリスクも抑えられるでしょう。
メモリアルアートの大野屋には、密葬をはじめ、ご遺族さまのお気持ちに寄り添うさまざまな葬儀プランの実績があります。ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
また、我が家のようなくつろぎの空間で、お別れの時をお過ごしいただける「リビング葬」のプランもご用意しています。
密葬はごく限られた身内で非公開に行われるため、参列者には特別な配慮と礼儀が求められます。参列前には必ず主催者に確認を取り、以下のポイントを守りましょう。
密葬の最大の前提は「訃報を伏せて行うこと」です。参列のご案内を受けた方は、式が終わるまでは決して外部に漏らさないように注意してください。SNSやメール、口頭での二次拡散が思わぬトラブルや遺族の心情に影響を及ぼすことがあります。
密葬の服装マナーは、一般的な葬儀と同様です。参列者は喪服(男性はブラックフォーマル、女性は黒のワンピースやアンサンブルなど)を着用するのが一般的です。派手なアクセサリーや装飾品は避け、故人やご遺族への敬意を示す落ち着いた装いを心がけましょう。
密葬ではご遺族の意向で香典や供花を辞退している場合があります。持参の前に必ず喪主や受付担当者に「香典をお持ちしてよいか」「供花は受け付けているか」を確認し、辞退されている場合は無理に準備しないようにしましょう。
密葬は葬儀を近親者のみで非公開に行い、後日に本葬やお別れ会を開催する葬儀形態です。著名人や社会的地位の高い方など、葬儀に多くの方が参列するケースで採用されています。密葬は、故人のプライバシー保護や落ち着いた見送りが可能といったメリットがある反面、費用がかさんだり訃報対応で誤解が生じたりする可能性がある点に注意が必要です。
密葬を行う場合は、細やかな配慮が必要となるため、実績豊富な葬儀社に相談するのがおすすめです。メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。