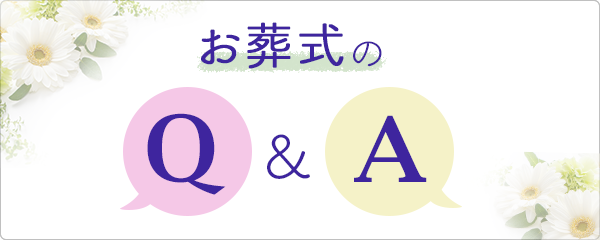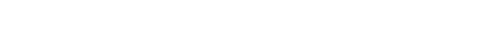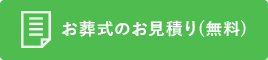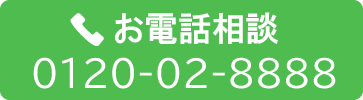通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/05/22
更新日:2025/07/14

 目次
目次● 喪主として告別式を営む予定の方
● 通夜と告別式の違いを知りたい方
● 将来喪主を務める可能性のある方
告別式とは、故人に最後のお別れを伝える儀式のこと。遺族や参列者がそれぞれの思いを胸に故人を偲び、互いの悲しみを分かち合う場でもあります。喪主やご遺族にとっては、多くの方々の思いにふれながら故人を送り出す大切な時間といえるでしょう。
告別式の他にも、故人とのお別れの儀式には通夜や葬儀があります。ここでは、告別式と葬儀・通夜との違いを解説します。
現代では、「葬儀・告別式」としてまとめて行われることが主流となっていますが、本来、葬儀と告別式はそれぞれ役割が異なるものです。「葬儀」は宗教的な儀式であり、たとえば仏式の場合は、僧侶による読経や参列者による焼香を行い、亡くなった方の冥福を祈ります。一方の「告別式」は、参列者が故人にお別れを告げるための社会的な儀式であり、宗教的な意味合いはありません。
「通夜」は、亡くなった方と最後の一晩をともに過ごす、仏教における儀式です。宗教的な儀式である点において告別式とは異なり、僧侶の読経や参列者による焼香が行われます。もともとは遺族やごく近しい関係者のみで行われていましたが、現代では仕事の都合などで日中に行われる告別式への参列が難しい場合に一般会葬者が参列するケースも増えてきました。基本的には、通夜は故人が亡くなられた翌日の夜に行われ、告別式は通夜の翌日に行われます。
通夜・葬儀・告別式は、2日間で行うことが一般的です。以下に、2日間で行う場合の基本的な流れをご紹介しますが、地域や宗派などによっても異なるため、おおよその目安としてお役立てください。
基本的には、亡くなった翌日に通夜を行います。18時頃から始まることが多く、所要時間は1時間〜1時間半ほどです。一般的な通夜の流れは、以下の通りです。
通夜の翌日に葬儀・告別式を行い、終了後、遺族は火葬場へ移動して火葬・収骨を行います。火葬が終わると、再び葬儀場に戻り、同日に繰上げ初七日法要や精進落としを行うことが一般的です。
開始30分前から始まることが多い
喪主、遺族、親族、参列者が着席
一同で僧侶を迎える
司会者による開式の挨拶
僧侶による読経
喪主、遺族、親族、参列者の順に焼香
喪主と遺族、親族らが棺に花を入れて故人の周りを飾る(別れ花)。
棺のふたを閉じたあとに釘を打ち込む儀式。近年は省略することが多い
霊柩車に棺をのせて、見送りに並んだ参列者に対して会葬のお礼を述べる
遺族・親族は火葬場へ移動
通夜を行わず、2日目の葬儀・告別式のみ営むお葬式を「一日葬」と呼びます。通夜を行わないことを除いて、当日の流れなどは一般的なお葬式と変わりません。遺族や参列者の負担を軽減したい場合など、葬儀時間をできるだけ短縮したいときに選ばれることの多い葬儀形式です。
告別式は、故人と最後のお別れをする大切な場です。喪主の挨拶は、参列者への感謝を伝えるとともに、故人に対する思いを互いに共有するという役割も担っています。告別式の中で喪主や遺族が挨拶を行う場面はいくつかありますが、それぞれの場にふさわしい言葉を選び、参列者に失礼のない振る舞いを意識しましょう。とはいえ、大切な方を亡くした深い悲しみの中、慣れない挨拶を行い、大勢の参列者に対応することはそれだけで負担が大きいものです。告別式の挨拶は、基本を理解しておけばそれほど難しいものではありません。必要以上に形式にとらわれたり緊張したりすることなく臨むことができるよう、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。
告別式で喪主および遺族が行う挨拶のタイミングやポイントについて、例文を添えてご紹介します。
僧侶が到着されたときやお見送りをする際に、感謝の気持ちをお伝えします。お見送りの際は、挨拶とともに用意しておいたお布施をお渡しします。
(出迎え時の例文)
「お忙しい中ご足労いただき、誠にありがとうございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。なにぶん不慣れなため、ご指導くださいますようお願いいたします」
(見送り時の例文)
「本日は大変ご丁重なお勤めを賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで無事に葬儀を執り行うことできました。(お布施をお渡しして)どうぞお納めください」
告別式の開式前など、参列者をお迎えするときに挨拶をすることがあります。お悔やみの言葉をいただいたら、感謝の気持ちをシンプルに伝えましょう。
(例文)
「本日はご足労いただき、ありがとうございます。生前は◯◯が大変お世話になりました」
喪主自身が受付に立つケースは少ないですが、遺族や親族が受付を担当する場合は、参列者に対して丁寧に挨拶を行い、香典の受け取りや記帳のご案内を行います。
(例文)
「本日はご多用の中お越しいただき、ありがとうございます」
「(香典を受け取り)お預かりいたします」
「(芳名帳を指し)こちらにご記帳をお願いいたします」
葬儀・告別式に参列してくださった方々に会葬のお礼を伝えます。タイミングとしては、出棺の際、見送りに並んでくださった方々にご挨拶することが一般的です。
(例文)
「本日はお忙しい中、◯◯の葬儀・告別式にご会葬いただきまして、誠にありがとうございました。このように多くの皆様方にお見送りいただき、故人もさぞかし喜んでいることと存じます。亡き◯◯に代わりまして生前のご厚情に心から御礼申し上げますとともに、私ども家族に対しましても、今後とも変わらぬお付き合いの程をお願い申し上げます。本日は最後までお見送りいただき、誠にありがとうございました。」
告別式では、喪主であっても故人や他のご遺族に配慮した言葉選びが大切です。日常的に使われる言葉でも、葬儀の場ではタブーとされる「忌(い)み言葉」というものがあります。一般に、弔事では以下のような言葉や表現の使用を避けることがマナーとされています。
「死ぬ」「消える」「落ちる」「終わる」など、不吉とされる言葉は避けましょう。また、数字の「4」や「9」も、「死」や「苦」を連想させるものとされています。
「亡くなった」「死亡した」といった直接死をあらわす表現に加えて、「生きる」「生きていた」など生命に関わる直接的な表現も控えましょう。「逝去」「永眠」などの丁寧な表現に言い換えたほうが無難です。
「重ね重ね」「ますます」「くれぐれも」など、同じ語を繰り返す表現は、不幸の繰り返しを連想させるため弔事の場では用いないことがマナーとされています。
関連記事:
・はじめての喪主~役割と準備ガイド~
告別式では喪服や略喪服を着用することが一般的ですが、故人との関係や立場によって服装のマナーは異なります。喪主は参列者を迎える立場として、故人への敬意と参列者への礼儀を形に表す必要があります。ここでは、告別式における喪主の服装や持ち物について解説します。
喪主は、もっとも格式の高い「正喪服」または「準喪服」を着用することが基本です。
<男性の場合>
・正喪服(洋装ならモーニングスーツ、和装なら黒紋付羽織袴)
・準喪服(ブラックフォーマル)
モーニングスーツやブラックフォーマルのスーツには、白無地のワイシャツを合わせます。ネクタイは、黒無地で光沢のないものを選びましょう。足元は、黒の革靴に、黒色の無地の靴下を合わせます。ネクタイピンや腕時計など、目立つ装飾品はできるだけ控えます。
<女性の場合>
・正喪服(洋装ならブラックフォーマル、和装なら黒紋付の着物)
・準喪服(ブラックフォーマル)
洋装の場合は、光沢のない黒のワンピースにボレロ、またはアンサンブルやスーツといったブラックフォーマルが基本です。スカート丈は、ひざが隠れるくらいの長さのものを選びます。足元は、黒い透け感のあるストッキングに、黒のパンプスが基本です。靴の素材は、布製や革製を選び、エナメルなど光沢のあるものは避けましょう。アクセサリーは、結婚指輪と一連のパールネックレス程度にとどめ、派手にならないよう注意が必要です。
告別式に持参する、喪主の持ち物について解説します。
・数珠(じゅず)、念珠(ねんじゅ)
仏式の告別式には必ず用意しましょう。宗派によっては形が異なる場合もあるので、事前に確認するとよいでしょう。
・ハンカチ
涙を拭くときや手を清めるときなどに使います。白か黒の無地を選び、柄入りやタオル地のものは避けましょう。
・筆記用具
確認のサインや参列者の記録など、さまざまな場面で必要になることがあります。黒のボールペンとメモ帳を用意するとよいでしょう。
・香典、袱紗(ふくさ)
喪主の場合は告別式を執り行う側なので、香典や袱紗(ふくさ)を用意する必要はありません。
告別式を行うにあたり、喪主として心得ておきたい注意点やマナーを以下にまとめました。喪主はすべての儀式を中心になって執り行わなければならず、当日もやるべきことがたくさんあります。慣れないことが多く不安に思う場面もあるかと思いますが、できるだけ落ち着いて対応できるよう、あらかじめ当日の流れやマナーについて理解しておくと安心です。
告別式では、喪主が式全体の責任者であり調整役となります。葬儀社から渡される式次第やスケジュールの流れを事前に把握しておきましょう。進行を全て覚える必要はありませんが、ポイントごとに自分がどう動くべきかを理解しておくと、当日不安なく対応できます。
喪主は遺族の代表者であると同時に、故人に代わって参列者に感謝の気持ちを伝え、最後のお別れをする立場でもあります。失礼のないよう一人ひとりに心を込めた対応を心がけましょう。当日は多くの参列者と接することになるため、相手によって態度を変えたり、他の参列者への対応をおろそかにして特定の人と話し込んでしまったりすることのないよう意識することが大切です。
故人の遺族を代表して弔辞を述べる場合は、2〜3分程度で簡潔にまとめるのが一般的です。故人との関係や感謝の思いを素直に言葉に込めた、心のこもった内容が好まれます。焼香は喪主が最初に行うため、所作に注目が集まりやすいシーンです。焼香の作法は宗派によって異なるので、葬儀社に確認しておくと安心です。
喪主の務めは非常に多岐にわたり、すべてを一人で担うのは困難です。親族や家族と役割を分担し、協力しながら進めると、スムーズな運営につながるとともに精神的な不安も軽減されます。最も大切なことは、葬儀や告別式を滞りなく進行して後悔のないよう故人を送り出すことです。喪主としての負担が大きいと感じる場合は、無理をせず周囲の人にサポートをお願いしましょう。
近年、香典返しは「当日返し」が一般的になりつつあります。会葬御礼の品や挨拶状とともに準備をしておきましょう。ただし、高額の香典をいただいた方には、後日改めてお礼や追加の返礼品が必要となる場合もあります。香典帳など記録の整理も忘れずに行いましょう。
・ 葬儀が読経や焼香を行う宗教的儀式であるのに対し、告別式には宗教的要素はない
・ 通夜は故人が亡くなった翌日の夜に行う宗教的儀式。告別式は通夜の翌日に行う
・ 現代では、葬儀と告別式をまとめて行うことが主流となっている
・ 一日目に通夜、2日目に葬儀・告別式を行い、同日中に火葬を行うことが多い
・ 「一日葬」は、通夜を行わない以外、儀式の流れなど基本的には一般葬と同じ
・ 当日、喪主は挨拶を含めてやるべきことが多いため、事前に流れを把握しておくと安心
・ 遺族代表として参列者に失礼のないよう、基本的なマナーは前もって確認しておく
・ すべて一人で担うのは負担が大きいので、家族や親族にもサポートをお願いする
・ 故人に代わって参列者に心をこめて対応し、安心して故人を送り出すことが重要
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常に待機し、お客様それぞれのお悩みやご事情に沿ったご提案やご相談をさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。