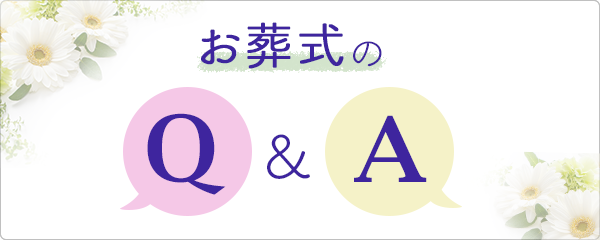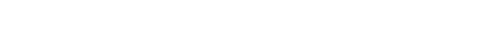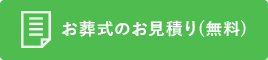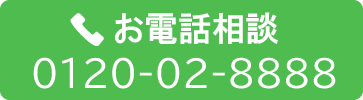通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/09/30
更新日:2025/09/30

 目次
目次大切な方を見送った後には「忌明け(きあけ/いみあけ)」という言葉を耳にすることがあります。忌明けとは、故人を偲びつつ過ごした一定期間を終え、日常生活へ戻る節目のことです。
ただし、忌明けの時期や意味は宗教・地域で異なり、忌中に控えるべきことや法要、香典返しや挨拶状の作法など、迷いやすい点も多いでしょう。
そこで本記事では、忌明けの定義や時期、宗教ごとの違いから、法要準備や挨拶状の文例までをわかりやすく解説します。この記事を参考にしながら、落ち着いて準備を整えていきましょう。
● 忌明けの意味を知りたい人
● 忌明けがいつになるのか知りたい人
● 忌中から忌明けにかけてのマナーを知りたい人
● 四十九日法要(忌明け法要)についてを知りたい人
● 忌明けの挨拶状、お礼状の書き方を知りたい人
「忌明け」とは、故人を偲び、喪に服して一定期間を過ごしたあと、日常生活へと戻る節目を指します。「きあけ」または「いみあけ」と読みます。
忌明けは仏教の考え方に由来しています。仏教では、人が亡くなると七日ごとに法要を営み、七七日(しちしちにち=四十九日)をもって一区切りとするのが一般的です。この日を「満中陰(まんちゅういん)」とも呼び、忌みの期間が終わることから「忌明け」とされます。
「忌」という言葉には、死を悼み祝い事を控えるという意味があります。そのため、忌中は結婚式や神社への参拝など慶事を控え、慎ましく生活する期間とされています。忌明けを迎えることで、こうした制約から解放され、社会生活へ戻っていくことができると考えられてきました。
また、「忌明け」と密接に関わるのが「忌中」「中陰」という考え方です。忌中は故人の死から忌明けまでの期間を指し、中陰は仏教でいう四十九日のあいだを表します。
「忌中」と「喪中」は混同されやすい言葉ですが、意味や期間が異なります。
一般に、故人が亡くなってから四十九日(宗派によっては三十五日や五十日)までの期間を指します。祝い事や神社参拝を控えるなど、宗教的な意味合いが強い時期です。
故人を亡くした悲しみを抱きながら過ごす期間で、慣習的に一周忌までとされます。この間は新年を祝う年賀状は控え、寒中見舞いや喪中はがきで挨拶を行うのが一般的です。
つまり、忌中は宗教儀礼に基づく「一定期間」、喪中は社会生活や挨拶の慣習にかかわる「一年間」を目安とする期間といえます。
忌明けが四十九日とされる背景には、仏教の「追善供養(ついぜんくよう)」の考え方があります。追善供養とは、遺された人が供養や善行を行い、その功徳を故人に回向して冥福を祈ることをいいます。
初七日から始まり、二七日、三七日と七日ごとに法要を営み、そして四十九日で一区切りを迎えるのも、この追善供養の考えに基づいています。忌明け法要にあたる四十九日法要は、単に日数の区切りというだけでなく、追善供養を行い、故人の冥福を祈る大切な節目なのです。
忌明けの時期は、宗教や宗派、地域の慣習によって異なります。多くの場合は仏教の教えをもとに四十九日を忌明けとしますが、神道やキリスト教では考え方が異なります。
ここでは代表的な宗教ごとの違いを見ていきましょう。
仏教では、人が亡くなった日から七日ごとに法要を営み、七七日(しちしちにち=四十九日)で一区切りを迎えると考えられています。そのため、多くの宗派では「四十九日が忌明けの基準」となります。
ただし、地域によっては三十五日(五七日)で忌明けとする場合もあり、また法要を繰り上げて行った場合には、その日をもって忌明けとすることもあります。
また、浄土真宗では「人は亡くなるとすぐに阿弥陀如来のはたらきによって極楽浄土へ往生する」とされているため、中陰(四十九日)の考え方は本来ありません。ただし、実際には他宗派や地域の習わしに合わせて四十九日の法要を営み、これを忌明けとするケースもあります。
神道では、仏教のように「中陰」という考えはありませんが、故人の魂が穢れ(けがれ)から清まるまでの期間を「忌服(きぶく)」と呼びます。その節目となるのが「五十日祭」で、これをもって忌明けとするのが一般的です。
五十日祭の翌日に「清祓(きよはらい)の儀」が営まれることも多く、この儀式を終えることで日常生活へと戻ることができます。地域や神社によっては細かい作法が異なるため、氏神様の神社や神職に確認すると安心です。
キリスト教には本来「忌明け」という考え方はありません。死は神のもとへの旅立ちであり、仏教や神道のように「喪に服す一定の期間」を明確に区切る習慣を持っていないためです。
ただし、故人を偲ぶ節目として、カトリックでは「死後30日目の追悼ミサ」が営まれることがあります。また、プロテスタントでも「召天記念日」や「死後1か月前後の記念式」が行われることが多く、これらを区切りとして生活を整えるケースも見られます。
キリスト教ではこうしたタイミングを「忌明け」ではなく「追悼の節目」と考える方が自然です。ただし、教会ごとに慣習が異なるため、悩んだ際は司祭や牧師に相談するのが望ましいでしょう。
忌中は故人を偲び、慎ましく過ごす期間とされています。そのため祝い事や派手な行動は控えるのが基本ですが、どこまで慎むべきかは迷いやすい点です。
ここでは代表的な事例について整理しておきましょう。
忌中に新年を迎える場合は年賀状を出さず、事前に喪中はがきで欠礼を伝えるのが一般的です。喪中はがきを出せなかったときは、松の内(1月7日または15日)を過ぎてから寒中見舞いを送ります。初詣も忌中は控え、忌明け後に参拝するのが望ましいです。
入籍や結婚式といった慶事は、忌中には行わないのが基本です。どうしても日程の変更が難しい場合は、両家や菩提寺に相談して判断します。また、喪中のあいだも盛大な披露宴は避けたり時期を改めたりするケースが一般的です。
子どもの成長を祝う七五三も、忌中は避けるのが一般的です。日程をずらして参拝するか、写真撮影のみ先に行い、お祝いの行事は後日に改めて行うとよいでしょう。
死を「穢れ」と捉える神道の考え方から、忌中は神社への参拝は控えるのが習わしです。仏閣への参拝は問題ないとされますが、神社の場合は忌明けを待ってから参拝するとよいでしょう。
お中元やお歳暮は相手を思いやる贈り物のため、忌中であっても送ること自体は失礼にあたりません。
ただし、相手が気にする場合もあるため、忌明け後に「寒中見舞い」として贈る方法もあります。表書きは「御中元」「御歳暮」ではなく「御礼」「志」などに替える場合もあります。
旅行に行くこと自体は禁じられていませんが、忌中は控えるのが望ましいとされます。やむを得ず出かける場合は、派手な行楽や大人数での旅行は避け、慎ましく過ごすことを意識するとよいでしょう。
新居への引っ越しや家の新築といった新しい生活の始まりも、忌中は避けるのが無難です。特に地鎮祭や上棟式など神事を伴う場合は、忌明けまで待つのが一般的です。
法要の会食などを除き、忌中は賑やかな宴席や酒席への参加を控えるのが基本です。忌明け後もすぐに華やかな場へ行くことに抵抗を感じる人もいるため、周囲への配慮を心がけましょう。
四十九日法要は、故人を偲ぶ大切な節目であり、忌明けを迎える儀式でもあります。滞りなく進めるためには、事前の段取りと当日の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、四十九日法要(忌明け法要)準備と、当日の進め方を解説します。
四十九日法要は参列者や僧侶が関わるため、早めの準備が欠かせません。以下に、法要前に整えておきたい事前準備をまとめました。
菩提寺やお世話になる寺院に日程を相談し、読経をお願いしましょう。
自宅や寺院、本堂、斎場などから選びます。参列者の人数やアクセスも考慮しましょう。
親族を中心に案内を出し、出席者を把握します。
法要後の会食の手配をします。また、参列者へのお礼として、食品や日用品など「消えもの」を用意します。
四十九日にあわせて白木位牌から本位牌へ切り替える場合は、位牌や過去帳を整え、僧侶に依頼します。
法要後に納骨を行う場合は、石材店に墓石彫刻や納骨スケジュールを早めに相談しておくと安心です。
四十九日法要(忌明け法要)当日の大まかな流れは以下のとおりです。
僧侶による読経や焼香を行い、故人の冥福を祈ります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
墓地や納骨堂に遺骨を納めます。石材店や寺院と連携して進めましょう。
法要後の会食で、忌明けを迎えた親族同士の労をねぎらいます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
僧侶へ読経のお礼としてお布施をお渡しします。表書きは「御布施」とし、新札ではなく折り目のあるお札を用意するのが一般的です。また、寺院から自宅や会場へ来てもらう場合は、交通費として「お車代」を別に用意します。
四十九日を終え、忌明けを迎えた後には、いくつかの整理や手続きがあります。ここでは代表的な事項を確認しておきましょう。
忌明け後に欠かせないことの1つが「香典返し」です。香典返しは、いただいた香典への感謝を込めてお返しするもので、相場はいただいた金額の「半返し」または「1/3返し」が目安とされています。
品物は、お茶や菓子、海苔や石鹸といった、使ってなくなる「消えもの」が一般的です。これらは日常生活で気軽に使えるため、相手に負担をかけにくい点でも好まれています。一方で、刃物や長く残る置物などは、弔事の贈り物としては避けるのがマナーです。
掛け紙は慶事で用いる「のし」ではなく弔事用の掛け紙を使用します。表書きは仏式なら「志」や「満中陰志」、神式では「偲び草」、キリスト教では「志」「感謝」などとするのが一般的です。香典返しは四十九日を過ぎてから、1か月以内を目安に発送するとよいでしょう。
香典返しに添える挨拶状やお礼状は、弔事ならではの作法に沿って記すことが大切です。
文章をしたためる際には、句読点を用いないのが一般的とされています。これは手紙を途切れなく続けることで、悲しみが絶え間なく続かないようにという意味が込められています。また、「重ね重ね」「再び」といった重ね言葉や「死ぬ」「終わる」といった忌み言葉も避けなければなりません。
こうした言葉を不用意に使うと相手に不快感を与えてしまうため、文例を参考にしながら丁寧に表現すると安心です。挨拶状、お礼状の文例については次の章で宗教別にご紹介します。
忌明けを迎えたら、葬儀で用いた白木位牌から本位牌へ切り替えます。本位牌は寺院で戒名を彫刻してもらい、開眼法要(魂入れ)を経て仏壇に安置します。仏壇を新しく用意した場合も同様に開眼法要が必要です。
また、四十九日に納骨を行わなかった場合は、寺院や石材店と相談し、改めて日程を決めて執り行います。
仏式での忌中と同じく、神道では死を「穢れ」ととらえるため、葬儀後に神棚を半紙で封じる「神棚封じ」を行います。
忌明けにあたる五十日祭を終えたら、この封じを解き、通常どおりお参りできるようにします。神職に相談のうえ、地域の慣習に従いながら行うのが望ましいとされています。
忌明け後には、香典や弔電、供花をいただいた方へ挨拶状・お礼状を送るのが一般的です。弔事ならではの形式や言葉遣いがあり、宗教によっても表現が異なります。
ここでは、代表的な宗教ごとのポイントと文例集をご用意しました。
・四十九日法要を終えたことを「満中陰」と表現
・表書きは「満中陰志」や「志」
・冥福を祈る言葉を用いる
【文例】
謹啓
亡父 ○○儀 去る○月○日に永眠いたし 四十九日法要を滞りなく相営みましたことを謹んでご報告申し上げます
その節はご厚志を賜り誠にありがとうございました
ここに満中陰志として心ばかりの品をお届け申し上げます
本来であれば拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
謹白
・節目は「五十日祭」
・表書きは「偲び草」や「志」
・「冥福」ではなく「安らかに」などの言葉を用いる
【文例】
謹啓
亡父 ○○儀 去る○月○日に帰幽いたし このたび五十日祭を滞りなく相済ませましたことをご報告申し上げます
その折には御弔意ならびにご厚志を賜り誠にありがとうございました
ここに偲び草として心ばかりの品をお届けいたしますので 何とぞご受納ください
本来であれば拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます
謹白
・「召天」という表現を用いる
・節目は「召天一か月記念式」など
・神への感謝と支援へのお礼を中心に書く
【文例】
謹啓
亡母 ○○儀 ○月○日に召天し このたび召天一か月の記念式を無事に終えることができました
その節はお祈りとご厚志を賜り誠にありがとうございました
ここに感謝のしるしとして心ばかりの品をお届け申し上げます
本来であれば拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
皆様のうえに主の慰めと平安がありますようお祈り申し上げます
謹白
・「永眠」という表現を用いる
・節目は「三十日目の追悼ミサ(30日ミサ)」
・「永遠の安息」「神の御許に召された」などの表現を用いる
【文例】
謹啓
亡父 ○○儀 ○月○日に永眠し このたび三十日目の追悼ミサを無事に終えることができました
その折にはお祈りとご厚志を賜り誠にありがとうございました
ここに感謝のしるしとして心ばかりの品をお届けいたします
本来であれば拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
故人の永遠の安息をともにお祈りいただけますと幸いに存じます
謹白
忌明けとは、故人を偲びながら慎ましく過ごしてきた日々を終え、日常生活へと戻る大切な節目です。一般的には仏教の四十九日を基準としますが、神道やキリスト教では考え方や時期が異なり、地域の慣習によっても違いがあります。
また、忌中には控えるべきことが多く、忌明けを迎えた後には香典返しや挨拶状、本位牌への切り替えや納骨など、行うべき準備が少なくありません。こうした習わしは宗派や地域によって異なるため、迷ったときは菩提寺や教会、神社に相談することが望ましいとされています。
忌明けの意味を正しく理解し、故人への感謝を込めて丁寧に準備を整えていきましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。