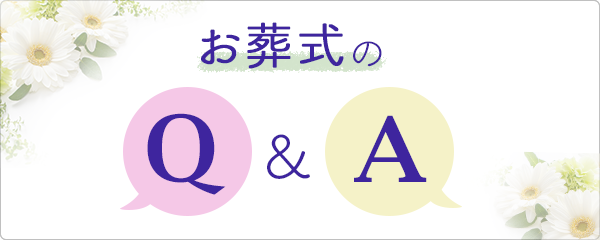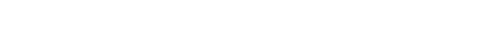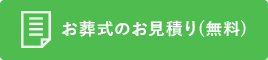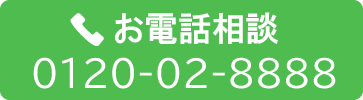通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/11/12
更新日:2025/11/12

 目次
目次葬儀を行うためには、葬儀の見積もりを取って内容を確認し、納得のうえで依頼することが大切です。しかし実際には、「どのように見積もりを取ればいいのか」「何を基準に比較すればよいのか」「どこまでが費用に含まれているのか」など、悩んでしまうこともあるでしょう。
葬儀の見積もりは、費用の把握だけでなく、内容やサービスの違いを理解し、納得のいく形を選ぶための大切なステップです。
そこで本記事では、見積もりを取るタイミングや依頼先の種類、見積書で確認すべきポイント、費用を抑える方法までを分かりやすく解説します。もしものときに慌てないよう、事前に正しい知識を身につけておきましょう。
● 葬儀の見積もりのタイミングを知りたい人
● 葬儀の見積もりの依頼先を知りたい人
● 葬儀の見積もりの取り方を知りたい人
● 葬儀の見積もりの内訳を知りたい人
● 葬儀の見積書の注意点を知りたい人
● 葬儀費用を安く抑える方法を知りたい方
葬儀は、大切な方との別れを偲ぶ大切な儀式です。限られた時間のなかで多くの決定を迫られるため、費用や内容を十分に確認しないまま進めてしまうと「思っていたより高額だった」「希望していた形式と違っていた」と感じることも少なくありません。
こうした後悔を防ぐためには、葬儀を依頼する前に「見積もり」を取り、内容を丁寧に確認しておくことが重要です。
見積もりの段階で葬儀の形式や参列人数、希望するサービスを整理しておけば、費用の全体像を把握しやすくなり、ご家族の意向に沿った形を選ぶことができます。また、あらかじめ見積もりを確認しておくことで、葬儀当日に慌てることなく進行でき、費用面でも納得して依頼できます。
終活の一環として、事前に葬儀の見積もりを取っておけば、比較検討する時間や心の余裕も生まれ、ご家族の負担を軽減することにもつながります。
葬儀の見積もりは、状況に応じて「生前に見積もりを取る場合」と「亡くなられた後に取る場合」の2つに分けられます。
悔いのない葬儀を行うためには「生前に見積もりを取っておく方法」がおすすめです。本人が元気なうちに葬儀社へ相談しておけば、希望する葬儀の形式や会場、予算などをじっくりと検討できるうえ、比較検討の時間も確保できます。
また、本人の意向を事前に整理しておくことで、ご家族が判断に迷う場面が少なくなり、葬儀の準備をスムーズに進めることができます。家族にとっても、精神的・金銭的な負担を軽減できる点が大きなメリットです。
一方で、急な葬儀となった場合は、事前に見積もりを取る時間がないこともあります。その場合は、故人が亡くなられた時点で、できるだけ早めに葬儀社へ連絡しましょう。
一般的には、病院で死亡宣告を受けた直後に、葬儀社へ「搬送」と「見積もり相談」を同時に依頼します。搬送後は、葬儀の日程や規模、希望内容を確認しながら初回の見積もりを提示してもらう流れとなります。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要の事前相談を承っております。お気軽にご相談ください。
葬儀の見積もりを取る際は、どのような葬儀社に依頼するかによって、費用やサービス内容が大きく異なります。
主な依頼先は「葬儀専門会社」「葬儀仲介会社」「互助会・協同組合」の3つです。それぞれの特徴を把握しておくことで、自分に合った依頼先を選びやすくなります。
葬儀の企画から式場の手配、運営までを一貫して行う葬儀の専門業者です。担当スタッフが打ち合わせから当日の進行までサポートしてくれるため、安心して任せることができます。
また、地域に密着した会社も多く、地元の風習や寺院との関係にも精通しています。
・専門知識を持つスタッフが丁寧に対応してくれる
・希望や予算に合わせて柔軟にプランを調整できる
・トラブル時の対応やアフターサポートも手厚い
・葬儀の規模や内容によっては費用が高くなる場合がある
インターネット上で複数の葬儀社を紹介・比較するサービスを運営する会社です。見積もりを一括で依頼できる手軽さが特徴で、相場感をつかみたい場合に向いています。
・複数の葬儀社の見積もりを簡単に比較できる
・費用の目安を短時間で把握できる
・実際に対応するのは提携先の葬儀社で、品質に差がある
・担当者との直接的なやり取りが少なく、細かな要望が伝わりにくいこともある
互助会や協同組合は、月々の掛け金を積み立てて、将来の葬儀や冠婚葬祭の費用に充てる仕組みです。あらかじめ会員として登録しておくことで、葬儀時に割引価格でサービスを利用できる場合があります。
・掛金の積立で、将来の葬儀費用をあらかじめ準備できる
・会員特典や割引が利用できる
・利用できるサービスや会場が限定される
・積立途中で解約すると返金額が少なくなる場合もある
・解約時に手数料が発生することがある
このように、葬儀の見積もりの依頼先にはそれぞれ特徴がありますが「希望に沿ったプランを柔軟に選びたい」「担当者と直接相談しながら進めたい」といった場合は、専門知識と実績を持つ葬儀専門会社に依頼するのが安心です。
葬儀の見積もりは、電話やメール、インターネットから依頼できるほか、葬儀社に直接来店して相談する方法もあります。いずれの場合も、正確な見積もりを出してもらうためには、希望条件をできるだけ具体的に伝えることが大切です。
ここでは、見積もりを依頼する際に押さえておきたい基本の流れと、注意すべきポイントを紹介します。
まずは、葬儀の基本条件を整理しておきましょう。主な確認項目は以下のとおりです。
■葬儀の形式(一般葬・家族葬・直葬など)
■参列予定人数
■式場や火葬場の場所、宗教・宗派の有無
■希望する日程や規模
■故人・ご家族の意向(静かに送りたい、華やかに見送りたい など)
これらを明確にしておくことで、葬儀社側もより正確な見積もりを提示できます。
見積もり依頼の時点で不明点がある場合は、その場で質問しても構いません。担当者が丁寧に説明してくれるかどうかも、信頼できる葬儀社を見極める重要なポイントになります。
複数の葬儀社に見積もりを依頼する場合は、同じ条件を伝えることが大切です。条件が異なると、単純な金額比較ができず、サービス内容の違いを正しく判断できなくなってしまいます。
また、金額だけで判断せず、見積書に記載された内容や担当者の説明のわかりやすさ、対応の丁寧さなども比較しましょう。「安い」ことだけを重視すると、必要なサービスが含まれていなかったり、後から追加費用が発生するケースもあります。
見積もりを取る際は、費用と内容のバランスを確認しながら、納得できる葬儀社を選ぶことが大切です。
葬儀の見積書には多くの項目が並びますが、大きく分けると「葬儀にかかる基本費用」「人数や日数によって変動する費用」「宗教者へのお礼費用」の3つに分類されます。
それぞれの内容や注意点を理解しておくことで、見積書を受け取った際に内容を把握しやすくなります。
葬儀の基本費用は、葬儀の規模や参列者数に関わらず必ず発生する、いわば「固定費用」です。主に以下の費用が含まれます。
■祭壇費用
■棺の費用
■遺影写真費用
■受付用品費用
■式場の設営費
■スタッフの人件費など
多くの葬儀社では、これらをまとめて「基本プラン」や「セット料金」として提示しています。
葬儀の基本費用は、プラン内容によって価格差がありますが、プランに含まれる項目が葬儀社によって異なる点には注意が必要です。同じ「基本セット」と表記されていても、祭壇の種類や式場設備、搬送距離などが異なる場合があります。基本プランやセット料金といった固定費用に何が含まれているかを確認し、希望に沿っているかを必ずチェックしましょう。
変動費用とは、参列者の人数や葬儀の日数によって金額が増減する費用です。主に以下のような費用が該当します。
■通夜や告別式で提供する料理・飲み物の費用
■返礼品(会葬御礼品など)の費用
■会葬礼状の印刷費用
■安置期間に応じたドライアイスの追加料金
■搬送距離の延長による車両費
■会場使用日数の延長費用 など
これらは参列者数や葬儀の規模によって大きく変わるため、見積もりの際には想定人数や安置期間を具体的に伝えておくと安心です。
後から費用が増える原因の多くは、この「変動部分」にあります。事前に確認しておくことで、予算オーバーを防ぐことができます。
葬儀費用の中でも、意外と見落としやすいのが宗教者へのお礼です。僧侶や神職、司祭などにお渡しする「お布施」「御車代」「御膳料」は、葬儀社を通さず直接お渡しするのが一般的なため、見積書には記載されないことが多い項目です。
また、地域や施設によっては火葬場の使用料、控室の利用料、役所への手続き代行費などが別途かかる場合もあります。
見積書を確認する際は、「この金額の中に何が含まれているのか」「別途必要となる費用はあるか」を担当者に確認しておきましょう。こうした「見積書に含まれない費用」を事前に把握しておくことで、後から思わぬ出費に戸惑うことなく、安心して準備を進めることができます。
葬儀の見積書には、「基本料金」や「セット料金」として、祭壇や棺、式場の設営、スタッフの人件費など、葬儀を行ううえで欠かせない費用がまとめられています。これらはいわば葬儀の"基本パッケージ"にあたる部分ですが、葬儀社によって内容や範囲が異なる点には注意が必要です。
見積書を受け取ったら、各項目を1つずつ確認し、不明な点はその場で担当者に質問しましょう。とくに「プランに含まれる範囲」と「別途料金になる項目」の境界を確認しておくことで、後からのトラブルを防ぐことができます。
見積書を確認する際は、人数や日数によって金額が変わる「変動費用」や、希望に応じて追加できる「オプション費用」にも注意が必要です。
たとえば、通夜や告別式で提供される料理・飲み物代、参列者への返礼品、会葬礼状の印刷費などは、参列者の人数によって金額が大きく変わります。また、安置日数が延びた場合のドライアイスの追加料金や、搬送距離の延長による車両費なども見積もり額に影響します。
さらに、祭壇のグレードアップや生花の追加、遺影写真のサイズ変更など、希望によって発生する「オプション費用」もあります。
これらは初回見積もりには含まれていないことが多いため、必要に応じて追加料金が発生するかを事前に確認しておきましょう。
葬儀の見積書を確認する際は、金額だけでなく「単価」「数量」「参列者数」が正しく反映されているかを必ず確認しましょう。
料理や返礼品、会葬礼状などは「単価 × 数量(人数)」で計算されるため、見積書の内訳を丁寧に確認しておくことが大切です。たとえば、参列予定者が増減した場合、費用も大きく変わる可能性があります。
また、車両費やドライアイス費用なども、搬送距離や安置日数によって金額が変わります。これらの数量や条件設定が適切かどうかを担当者に確認し、見積書の内容が実際の予定に合っているかをチェックしましょう。
数字の根拠を明確にしておくことで、後から「思っていたより高かった」「追加料金が発生した」といったトラブルを防ぐことができます。
葬儀の見積もりは、必ず書面で受け取るようにしましょう。口頭での説明や電話・メールのやり取りだけでは、後から内容を確認できず、費用トラブルにつながるおそれがあります。
書面(またはPDFなどのデータ)で受け取っておけば、見積りの内訳を後から見直したり、他社と比較したりする際にも役立ちます。金額だけでなく、項目名や数量、単価の明記があるかを確認し、不明点はその場で質問しておくことが大切です。
さらに、見積書の発行日や有効期限、担当者名が記載されているかどうかもチェックしておきましょう。これらを控えておくことで、見積内容に変更が生じた場合も適切に対応でき、安心して葬儀を進められます。
複数の葬儀社から見積もりを受け取ったら、金額だけで判断せず、内容や対応の丁寧さにも注目しましょう。同じような金額でも、葬儀の進行サポートやアフターフォロー、担当者の説明力などに差が出る場合があります。
まず、見積書に記載されている項目の明確さを確認します。費用の根拠がわかりやすく整理され、説明が丁寧である葬儀社は、信頼できる対応を行っていることが多いです。
一方で、「プランに含まれる内容が曖昧」「質問に対して明確な回答が得られない」といった場合は注意が必要です。
また、担当者の態度や説明の分かりやすさも大切な比較ポイントです。見積もりの段階から誠実に対応してくれる葬儀社であれば、実際の葬儀の進行も安心して任せられるでしょう。
見積書は、費用を比較するためだけのものではなく、葬儀社の信頼性を見極める重要な判断材料です。「丁寧な説明があるか」「追加費用の説明があるか」といった点を確認しながら、納得できる葬儀社を選びましょう。
葬儀の費用を抑えるためには、プラン内容をよく確認することはもちろん、利用できる制度やサービスを上手に活用することが大切です。ここでは、費用の負担を軽減する主な4つの方法をご紹介します。
まず、自治体や健康保険組合から支給される助成金・補助金制度を確認しましょう。
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費として数万円〜7万円程度が支給されることがあります。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保、共済組合に加入していた場合には、埋葬料として一律5万円が支給されます。
いずれも申請期限が2年と定められているため、手続きは忘れずに行いましょう。
葬儀保険は、葬儀費用をまかなうことを目的とした死亡保険の一種で、生前に加入しておくことで、万一の際に保険金を葬儀費用に充てられます。
各社によって補償内容や保険料が異なるため、複数のプランを比較して検討するとよいでしょう。
あらかじめ葬儀内容を決めておく生前予約も費用を抑える方法のひとつです。事前に希望を整理し、見積もりを取っておくことで、必要な費用を把握できるほか、当日に慌てることもありません。
メモリアルアートの大野屋では、生前予約サービス「アンシア」を通じて、希望に沿った内容でお見積もりを作成し、費用面でも安心してご準備いただけます。
葬儀社の会員制度を利用するのもおすすめです。
メモリアルアートの大野屋では、"もしもの時"に葬儀や仏事全般のサポートや割引特典を受けられる無料会員制度「もしも会員」をご用意しています。
もしも会員にご加入いただくと、お葬式やお墓・お仏壇の費用優待だけでなく、相続や遺品整理といった終活支援、日常生活に役立つ提携サービスの割引など、多彩な特典が利用可能です。
詳しくは『費用のかからない大野屋の会員「もしも会員」』をご覧ください。
葬儀が終わったあと、受け取った請求書の金額が見積もりと異なり、戸惑う方も少なくありません。金額に差が出るのは決して珍しいことではなく、多くの場合、実際の葬儀で発生した追加費用や条件の変更が原因です。
まず、見積もりと請求書が異なる主な理由としては、参列者の人数増加や安置日数の延長、料理や返礼品の追加注文などが挙げられます。また、当日の進行上の都合で車両を増やしたり、ドライアイスの使用回数が増えたりする場合もあります。
これらは見積もり時点では正確に予測できないため、実際の請求書に反映される形になります。
一方で、プラン内容の勘違いや、説明不足によって請求額が想定以上になるケースもあります。そのような場合は、慌てずにまず請求書と見積書を照らし合わせ、差額の理由を確認しましょう。
追加費用が発生している場合は、「どの項目が」「なぜ必要になったのか」を具体的に説明してもらうことが大切です。
差額の説明を受けても不明点が残る場合は、領収書や契約書を確認し、担当者へ再度質問します。誠実な葬儀社であれば、費用の内訳や変更理由を丁寧に説明してくれるはずです。
納得できないまま支払いを進めるのは避け、疑問点をきちんと解消してから手続きを行いましょう。
見積もりと請求額に違いが生じることは珍しくありませんが、事前の確認と透明な説明があれば、トラブルは防げます。葬儀前の段階から、不明点をそのままにせず担当者と丁寧にコミュニケーションを取ることが大切です。
葬儀の見積もりは、費用を知るためだけでなく、内容やサービスの違いを理解し、納得のいく葬儀を実現するための大切なステップです。生前に見積もりを取っておけば、本人やご家族の希望を反映した計画を立てやすく、急な葬儀でも慌てずに対応できます。
見積書を確認する際は、「基本料金に何が含まれているか」「人数や日数で変わる費用」「宗教者へのお礼」などを事前に把握し、金額だけでなく説明の丁寧さや対応の誠実さにも注目しましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。