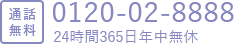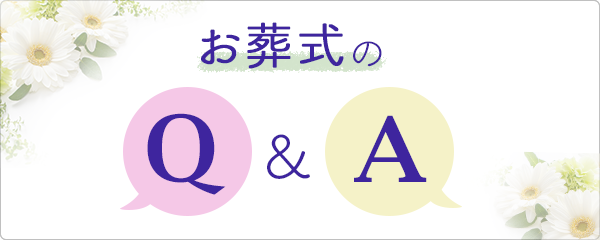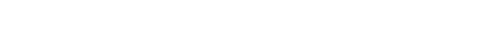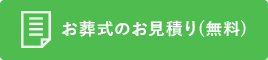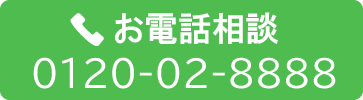もしものために備えておきたい!葬儀費用について徹底解説
公開日:2023/06/23
更新日:2025/07/08
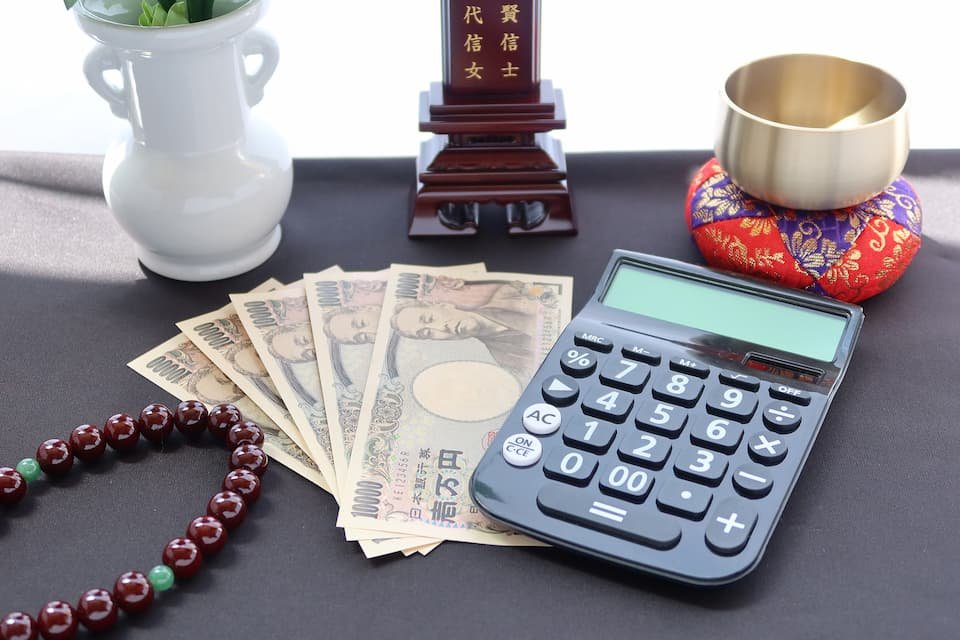
● 葬儀費用の平均相場を知りたい方
● 費用の内訳について知りたい方
● 葬儀の種類や特徴を知りたい方
● 葬儀形式別の費用の目安を知りたい方
● 葬儀費用を抑えたいとお考えの方
1. 葬儀の種類は大きく分けて4タイプ
葬儀費用は、葬儀の形式や規模、内容によって変動します。かつて葬儀といえば、大勢の方が参列するスタイルが一般的でしたが、近年は高齢化や核家族化などを背景に、都市部を中心に葬儀のあり方も大きく様変わりしてきました。葬儀形式には、大きく分けて四つのタイプがあります。まずは葬儀にはどのような種類があるのかを知り、その違いを理解しておくことは、大切な故人とのお別れにふさわしい葬儀形式を選ぶときに役立つはずです。ここでは、それぞれの葬儀形式の特徴をご紹介します。
■一般葬
通夜と告別式を行う、一般的な葬儀のことです。参列者の制限がなく、家族や親族のほか、友人・知人、職場関係者、ご近所の方々など多くの方が参列します。四つの葬儀形式の中で最も参列者が多く、50~300名ほど参加されるのが一般的です。故人とご縁のあった大勢の方々が最後のお別れをする機会を用意できる点はメリットである反面、どのくらいの人数が訪れるのかを事前に把握することが難しいため、想定より多くの方が参列し、見積もりに対して葬儀費用が高くなることも少なくありません。
■家族葬
家族や親族、仲の良かった友人など、故人と関係の深かった方を中心に少人数で行われる葬儀です。小規模ではあっても、一般葬と同じく通夜と告別式を行います。参列者数に決まりはありませんが、20〜50名程度で行われることが多く、故人と親しい方だけでゆっくりお別れの時間をもてることがメリットです。一般葬に比べて参列者が少なく、会場の規模も小さくなるため、費用の総額を抑えられる傾向があります。ただ、家族葬では香典を辞退するケースも多く、また受け取る場合でも、そもそもの参列者の数が少ないため、多くの額を期待できないことはあらかじめ理解しておきましょう。
■一日葬
一般葬や家族葬が、通夜から告別式まで二日間かけて行われるのに対し、一日葬では通夜を行わず、葬儀・告別式を1日で済ませます。通夜がないだけで、葬儀の流れは一般葬と同じです。また、参列者の範囲や人数を限定する家族葬と異なり、一日葬では参列者についての制限などはありません。葬儀にかかる日数が1日だけで済むので、遺族の精神的、体力的、経済的な負担を軽減できる点が大きなメリットといえます。とはいえ、省略されるのは通夜にかかわる部分だけであり、1日で済むからといって葬儀費用も半額になるわけではないことは注意しておきたいところです。
■直葬(ちょくそう)
通夜・告別式を行わず、火葬のみで故人を送る葬儀形式です。「火葬式」ともいいます。葬儀会場を借りることなく、身内やごく親しい方だけで火葬場に集まってお別れをするため、最も費用を抑えられる葬儀形式といえます。故人が高齢で友人・知人がすでに他界されている場合など、参列者が少ないことが予想される場合や経済的な負担をできるだけ軽減したいときに選ばれることが多いようです。斎場などでの儀式は行わないものの、火葬の手続きなどは葬儀社に依頼して行う必要があるため、その費用はかかります。また、希望によって火葬場の炉前などで僧侶による読経を依頼する場合も費用が必要です。
【葬儀形式ごとの主な流れ】
| 亡くなった当日 | 一日目 | 二日目 | ||||
| 葬儀形式 | ご遺体の移送・安置 | 納棺 | 通夜 | 告別式・葬儀 | 出棺 | 火葬・拾骨 |
| 一般葬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家族葬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 一日葬 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 直葬 | ◯ | ◯ | ─ | ─ | ◯ | ◯ |
| ◯ 行う ─ 行わない | ||||||
葬儀形式や規模が決まったら、その葬儀形式に対応している葬儀会場の手配が必要です。メモリアルアートの大野屋では、関東の500カ所以上で提携する葬儀場・斎場の中から、お客様のご希望にあった場所とお葬式のプランをご提案します。以下のリンクから、ご希望の地域の葬儀場・斎場が検索できますので、ぜひご活用ください。
2.葬儀費用の内訳と種類別の平均相場
葬儀にかかる費用は、(1)葬儀一式費用、(2)飲食接待費用、(3)宗教者に対する費用、と大きく三つの要素に分けられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)葬儀費用一式
遺体の搬送から通夜・告別式、火葬まで、お葬式を行うためにかかる費用です。祭壇や棺、遺影などにかかる費用、寝台車や霊柩車など車両関係の費用、式場の利用にかかる費用、火葬料、スタッフの人件費などが含まれます。「一式」というとすべてが含まれているように誤解されがちですが、参列者の人数によって変動する飲食代などは含まれていません。また、葬儀社によって「一式」、「セット」、「プラン」という呼び方で、その中に含まれるサービス内容は異なるため、事前にしっかり確認することが重要です。
(2)飲食接待費用
参列者に対するおもてなしにかかわる費用です。通夜から葬儀・告別式までの飲食にかかる費用と、会葬返礼品や香典返しにかかる費用などが含まれます。飲食代や返礼品などは、参列者の数によって変わることを理解しておきましょう。
(3)宗教者に支払う費用
僧侶、神父、牧師、神官など、宗教者に支払う謝礼やおもてなしにかかわる費用のことです。お布施(読経や戒名料)とは別に、御車代や御膳料などを払う場合もあります。お布施は、一般的に喪主から直接宗教者に手渡すものであり、葬儀社からの請求には含まれていませんので注意が必要です。
■ 葬儀費用には追加料金が発生することも
葬儀費用には、見積もりを確認した時点では想定できなかった状況により、追加料金が発生する場合があります。たとえば、予定していた数よりも多くの参列者が訪れた場合、参列者の人数によって変動する料理、香典返し、人件費などが増加します。そのほか、基本プランにオプションをつける場合や当日想定外の対応が必要になった場合も、追加料金が生じるケースがほとんどと考えていただいて構いません。
セットプランに含まれているサービス内容は葬儀社によって違いがあり、希望するサービスがプランには含まれておらず、オプション扱いになっていることもあります。また、棺や祭壇飾り、生花、料理などをグレードアップする場合も、追加料金が発生する可能性が高いといえるでしょう。
想定外の対応の例としては、たとえば真夏で気温が高く、ご遺体の安置に必要なドライアイスの使用量が増えた場合や遺体の搬送距離が予定よりも長くなった場合などがあります。どのようなときに、どのくらい追加料金が生じるのかをあらかじめ把握しておくことで、費用をめぐるトラブルを回避したいものです。
【葬儀費用の内訳】
| 内訳 | 主な内容 |
|---|---|
| (1)葬儀一式費用 |
遺体の安置・搬送から、通夜・告別式、火葬までお葬式を行うためにかかる費用 |
| (2)飲食接待費用 |
参列者へのもてなしにかかわる費用 |
| (3)宗教者に支払う費用 |
宗教者に支払う謝礼、もてなしにかかわる費用 僧侶・神職・牧師などへの謝礼/御車代・御膳料など |
■葬儀形式別のお葬式の費用相場
それでは、気になるお葬式の費用について、全国の平均相場を見てみましょう。鎌倉新書が2022年に実施した「第5回お葬式に関する全国調査」によると、葬儀費用の平均は約110.7万円。費用の内訳は、基本料金(葬儀一式の費用)が約67.8万円、飲食代が約20.1万円、返礼品が約22.8万円(お布施の費用を除く)となっています。
なお、前回2020年に行った「第4回お葬式に関する全国調査」では、基本料金は約119万円となっており、2年ぶりの調査では葬儀費用が50万円近く低下しています。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、葬儀の規模を縮小し、参列者が減少したケースも多かったことから、葬儀費用全体の平均相場が下降したためと考えられます。
次に、葬儀形式別の平均相場を比較してみると、一般葬の基本料金の平均は83万8,900円、家族葬は67万3,200円、一日葬は52万7,800円、直葬は42万2,300円となっています。これは、飲食代や返礼品、お布施などを除いた基本料金だけの金額です。四つの葬儀形式の中では、告別式や葬儀を行わない直葬が最も価格を抑えられ、一日葬、家族葬、一般葬と、規模が大きくなるにしたがって基本料金も高くなっていることがわかります。
【葬儀形式別にみる費用相場】
| 葬儀形式 | 基本料金 |
| 一般葬 | 83万8,900円 |
| 家族葬 | 67万3,200円 |
| 一日葬 | 52万7,800円 |
| 直葬 | 42万2,300円 |
| 引用:「第5回お葬式に関する全国調査」(2022年/鎌倉新書) | |
「葬儀の規模が小さいほど費用を安く抑えられる傾向がある」とはいえ、葬儀形式にはハッキリとした定義がなく、葬儀社によってもプランの内容が異なるため、一概に葬儀形式だけで葬儀費用が決まるとはいえません。また、お葬式の内容は、規模や会場の広さ、故人や遺族の希望、地域の風習などによっても変化するものです。ここに挙げたデータをあくまで目安としながら、葬儀の種類や費用相場を参考にして、自分たちはどのようなお葬式にしたいのかをイメージしていくと良いでしょう。
3.費用を安く抑える方法は?
葬儀の費用相場がわかったところで、「理想のお葬式を行いたいけれど、できるだけ費用は抑えたい」とお考えの方も多いことでしょう。まずは、予算に合わせて葬儀プランや内容を吟味することが基本となりますが、さらに費用の負担を抑えるためにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、四つの方法をご紹介します。
①助成金・補助金制度を利用する
故人が保険や組合に加入していた場合、葬儀終了後に遺族が手続きを行うことで、給付金を受け取ることができる制度があります。
たとえば、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、自治体から「葬祭費」を受け取ることができます。金額は自治体によって異なりますが、数万〜7万円程度が相場です。なお、葬儀を行わず火葬のみを行う直葬の場合、自治体によっては葬祭費が支給されない場合があるので、申請する際には支給要件を確認しましょう。
一方、故人が全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保・共済組合などの社会健康保険組合に加入していた場合は、「埋葬料」として一律5万円が支給されます。こちらは、社会保険事務所、または該当の健康保険組合への申請が必要です。
いずれも申請には期限があり、葬祭費は「葬祭を行った日の翌日から2年以内」、埋葬料は「亡くなった日の翌日から2年以内」と決められているので、手続きを忘れないよう注意しましょう。
②葬儀保険に加入する
葬儀保険とは、生命保険(死亡保険)の一種で、自身が死亡した後に支払われる保険金を葬儀費用に充てることを目的とした保険です。各保険会社でプランが用意されており、「終活」という人生の終わりについて考える活動が話題となっている昨今、残された家族の負担にならないようにと加入する方が増えています。故人が亡くなった後では対応できないため、各社のプランを比較検討した上で事前に加入しておくと安心です。
③葬儀の生前予約をする
生前のうちから葬儀形式や内容を計画し、葬儀社に予約しておくことを生前予約といいます。費用面の安心感だけでなく、事前に葬儀内容を決めておくことで、いざというときにご遺族も慌てることなく、精神的にも時間的にも余裕をもって、ゆっくりと最後のお別れができることも大きなメリットです。
メモリアルアートの大野屋では、送る方、送られる方の想いを反映させた葬儀ができるよう、葬儀の生前予約「アンシア」をご用意しています。葬儀内容について納得いくまでじっくりとご相談いただき、ご希望に沿った内容でお見積もりを作成できますので、必要な費用を事前に把握できて安心です。
④葬儀社の会員制度を利用する
葬儀社の会員制度に入会すると、葬儀費用の割引などのサービスを受けられることがあります。葬儀プランや式場を会員価格で利用できるほか、特典や優待サービスが付帯していることも多いので、興味がある場合は加入を検討してみるとよいでしょう。
大野屋の会員サービス「もしも会員」は、"もしも"のときの葬儀にかかわる割引はもちろん、相続や家系図作成、ご自宅の安全見守りなど、会員価格で幅広いサービスをご提供・ご紹介しています。入会金無料・年会費無料でご登録いただけますので、ぜひご検討ください。
4.葬儀費用にまつわるトラブルの例
お葬式で提供されるサービスは、種類が多く内容も複雑であることから、葬儀費用をめぐってトラブルが生じることも少なくありません。ここでは、葬儀費用に関連するトラブルについて想定されるケースをいくつかご紹介するとともに、回避するためのポイントをあわせてお伝えします。大切な故人とのお別れの場面で余計な禍根を残さないよう、事前に対策することでトラブルを防ぎましょう。
■トラブル事例1 「高額な追加料金を請求された」
葬儀社と契約する際、希望する葬儀形式や内容について打ち合わせを行い、提示された見積もり金額に納得した上で契約を行った。しかし、葬儀が終わって請求書を見ると、追加サービスやオプションの費用が加算されており、当初の見積もり額を大きく上回る金額を請求された。
【トラブルを防ぐために】
葬儀費用に関するトラブルで最も多いのは、見積もりより高い費用を請求され、料金に納得がいかないとしてトラブルに発展するケースです。通常、葬儀社と契約をする際は、葬儀社が作成した見積書が提示されます。まずはこの段階で、見積もり金額が適正かどうか、葬儀形式や含まれるサービスは希望に沿っているか、などを細かくチェックすることが大切です。プラン自体が低価格に設定されていても、必要なサービスを追加することにより、予定していた金額を大幅に上回るケースもあるため注意しましょう。
また、契約する側の葬儀に関する知識や経験が十分でない場合、価格やサービス内容について正確に理解していなかったり、葬儀社の説明が不足していたりすることにより、認識のずれが生じてトラブルにつながることもあります。葬儀社の担当者とコミュニケーションをとり、分からないことは積極的に質問して疑問や不安を解消することもトラブルを防ぐために必要です。
■トラブル事例2 「理想のお葬式ができなかった」
お葬式にあまり費用をかけたくないと考えていたことから、相場より低価格なプランを紹介している葬儀社を選んで契約した。しかし、そのプランには希望していた儀式やサービスが含まれておらず、後から追加もできなかったため、思い通りの葬儀ができず不満が残った。
【トラブルを防ぐために】
近年は格安のプランを提供している葬儀社も多く見受けられますが、希望する商品やサービスを追加できなかったり、反対に必要のないサービスを削ることができなかったりと、様々な制約が設定されているパターンも少なくありません。イメージしていた葬儀とかけ離れてしまうことがないよう、金額のみに気をとらわれず、希望している儀式やサービスが含まれているか、どのサービスで追加料金が発生するかなど、プラン内容を精査することが重要です。
■トラブル事例3 「香典で葬儀費用をまかなうことができず赤字になった」
多くの参列者が集まると見積もり、受け取った香典を葬儀費用の支払いに充てるつもりで葬儀を行った。しかし、実際には予想よりも参列者の数が少なく、思った以上に金額が集まらなかったため、葬儀費用の工面が難しくなった。
【トラブルを防ぐために】
大切な方とのお別れは突然訪れることも多く、そのようなケースにおいて葬儀費用は予想外の大きな出費といえるでしょう。しかしながら、一般的に香典で葬儀費用をまかなうことは難しいものです。一般の参列者の香典の相場は、3千円〜1万円程度と言われており、たとえば参列者が100名訪れて1万円ずつ香典をいただいたとしても、合計額は100万円。その金額で100名が参列する規模の葬儀を行うことはあまり現実的ではありません。このような前提のもと、葬儀費用の負担を減らすためには、家族葬など小規模な葬儀を選ぶことが有効です。また、葬儀社によってはクレジットカードで支払いができるほか、分割払いを選択できる場合もあります。すぐに費用を準備することが難しい場合は、葬儀社を選ぶ際に相談してみるとよいでしょう。
5.まとめ
●葬儀費用はお葬式の種類や内容によって大きく変わる
・葬儀形式には「一般葬」、「家族葬」、「一日葬」、「直葬」の4種類がある。
・本人や家族の希望に合った葬儀形式を選ぶことが大切。
●費用の内訳は「葬儀一式費用」「飲食接待費用」「宗教者に支払う費用」の三つ
・葬儀形式に明確な定義はないため、プラン内容は葬儀社により異なる。
・追加サービスやオプションにより追加料金が発生することがある。
●費用を抑えて納得ゆく葬儀を行うためには事前の確認や準備が重要
・契約時には見積もりを受け取り、サービスや内容をしっかりと確認しておく。
・助成金・補助金制度や葬儀保険、生前予約、会員制度などを活用する。
・トラブルを回避するためには、葬儀に関する知識を習得しておくことも必要。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀・法要についてベテランスタッフが常に待機しており、お客様それぞれの質問や、必要な事をお聞きした上で、お悩みに沿ったご提案やご相談をさせていただきますので、安心して いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。