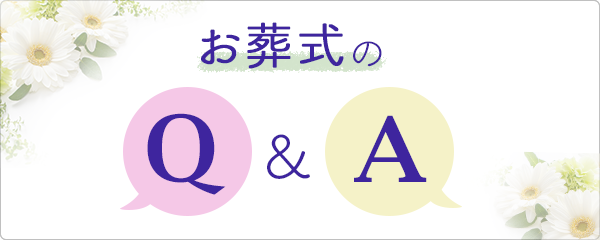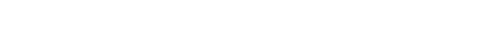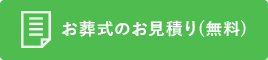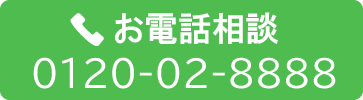通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/10/30
更新日:2025/10/30

 目次
目次葬儀や法事の会食で唱和される「献杯(けんぱい)」は、故人への敬意と追悼の思いを静かに表す大切な所作です。しかし「乾杯との違いは?」「誰が挨拶するの?」「グラスは合わせるの?」などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、献杯の意味や乾杯との違い、基本的なやり方などを詳しく解説します。献杯の挨拶のマナーや挨拶文例などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
● 献杯の意味を知りたい人
● 献杯と乾杯の違いを知りたい人
● 献杯のマナーや注意点を知りたい人
● 献杯の流れを知りたい人
● 家族葬での献杯について知りたい人
● 献杯の挨拶文例を知りたい方
献杯(けんぱい)とは、故人への敬意と追悼の意を込めて杯を捧げる儀式のことです。葬儀後の会食(精進落とし)や法要のお斎(おとき)、お別れ会などで行われるのが一般的で、参加者全員が心を合わせて故人を偲びます。
献杯を行う人に明確な決まりはありませんが、喪主から依頼を受けた親族代表や友人など、故人と縁の深い方が務めるのが一般的です。
献杯の慣習は古くから日本に根付いており、神仏や亡き人に酒を供える文化とともに受け継がれてきました。
献杯と乾杯はどちらも杯を掲げる行為ですが、その意味合いと目的はまったく異なります。
献杯は、故人の冥福を祈り、敬意をもって盃を捧げる弔事の儀式です。静かな声で「献杯」と唱え、参列者全員が心を合わせて故人を偲びます。
一方、乾杯は結婚式や祝賀会など慶事で行われるもので、喜びや祝福の気持ちを共有するための行為です。「杯を乾かす」ことを意味し、明るく賑やかに発声するのが特徴です。
また、献杯と乾杯とでは、所作にも明確な違いがあります。
献杯では杯を胸の高さまで静かに掲げ、乾杯のようにグラスを打ち合わせる動作は行いません。また、グラスに軽く口をつける程度にとどめ、乾杯のように飲み干すことは行いません。乾杯が「これからを祝う」行為であるのに対し、献杯は「故人を偲ぶ」静かな祈りの時間といえるでしょう。
献杯の際は、姿勢を正してグラスを右手で持ち、左手をグラス下に添えて胸の高さに掲げるのが基本です。
音頭を取る人が挨拶を行い、最後に「それでは、故人のご冥福をお祈りし、献杯いたします。献杯」と発声したら、参列者も同様に「献杯」と静かに唱和して、グラスを口もとに運びます。その際、グラスを鳴らして音を立てたり、拍手をしたりするのは控えましょう。
献杯のタイミングに明確な決まりはありませんが、一般的には次のような場面で行われます。
お通夜の後に、弔問に訪れた方々へ感謝の気持ちを伝えるために振る舞われる食事を「通夜振る舞い」といいます。もともとは参列者へのおもてなしの意味合いが強く、献杯を正式に行うことはあまり多くありません。
ただし、少人数の家族葬や親族中心の通夜では、喪主や親族代表が「皆さまで故人を偲びながら献杯いたしましょう」と声をかけ、簡単な献杯を行う場合もあります。
葬儀や告別式の後に行われる会食は「精進落とし」と呼ばれます。参列者への労いと感謝、そして故人を偲ぶ場として行われ、献杯のもっとも一般的な機会です。
代表者の発声のあとに献杯の唱和を行い、杯を掲げて心を合わせることで、故人への思いを静かに共有できます。
四十九日や一周忌などの法要後に行われる会食を「お斎(おとき)」と呼びます。僧侶や参列者への感謝と故人の供養の意味を持つ食事の前に、参列者一同で献杯を行うのが一般的です。
近年は、葬儀後に改めて故人を偲ぶ「偲ぶ会」や「お別れ会」「追悼式」などが行われることも増えています。形式にとらわれず、親しい人々が集い、思い出を語りながら静かに献杯を行うことで、故人の人柄やつながりを改めて感じることができます。
献杯は、会食の始まりに行われることが多く、流れをあらかじめ理解しておくと安心です。ここでは、葬儀後の精進落としや法要のお斎で行う場合の一般的な進行を紹介します。
葬儀や法要が終わると、参列者はスタッフの案内で会食会場に移動します。席次の決まりは厳密ではありませんが、僧侶や年長の親族が上座、喪主や遺族はもてなす側として下座に座るのが一般的です。参列者は案内に従い、静かに着席します。
参列者の着席後、スタッフや遺族によって飲み物が配られます。飲み物はビールや日本酒といったアルコール類のほか、お茶やソフトドリンクなどが用意されているのが一般的です。
献杯の発声があるまでは、飲み物に手をつけず静かに待ちましょう。自分で注ぐ必要はなく、スタッフまたは喪主側が用意します。
全員の準備が整ったら、司会または喪主が「これより献杯を行います」と案内します。続いて、献杯の発声を行う代表者(親族代表や友人など)を紹介し、挨拶をお願いする流れとなります。
代表者は立ち上がり、故人への想いと参列者への感謝を簡潔に述べます。挨拶の最後に「それでは、故人のご冥福をお祈りし、献杯いたします」と発声し、落ち着いた声で「献杯」と唱えます。参列者も同時に「献杯」と唱和し、グラスを胸の高さで掲げましょう。
唱和の後、参列者はグラスを胸の高さで静かに掲げ、軽く口をつけます。飲めない方は、口元へグラスを運ぶ仕草だけでも構いません。グラスを合わせたり音を立てたりするのは避け、厳粛な雰囲気を保ちます。
献杯が終わったら、司会者や喪主が「どうぞお召し上がりください」と声をかけ、会食が始まります。食事中は故人の思い出を語り合いながら、穏やかに過ごすのが望ましいでしょう。
献杯の発声や挨拶を任された人は、会の雰囲気を整える大切な役割を担います。進行を円滑に行うためにも、事前の準備と当日の所作に注意を払いましょう。
献杯は、乾杯のようにグラスを高く掲げたり、他の人と打ち合わせて音を立てたりする行為は行いません。厳粛な場であることを意識し、静かに杯を胸の高さに掲げて「献杯」と唱えるのが基本です。
拍手や賑やかな声も控え、故人に心を向けて穏やかに行うよう心がけましょう。
献杯の挨拶を行う際は、遺影に背を向けない立ち位置を意識することが大切です。
具体的には、祭壇の斜め前方など、遺影と参列者の両方を見渡せる位置に立つのが理想です。体の向きをやや遺影側に向けることで、故人への敬意と参列者への配慮がどちらも伝わります。
献杯の挨拶では、「ますます」「重ね重ね」「終わる」「死ぬ」など、忌み言葉や不吉な表現を避けましょう。代わりに「ご生前」「永眠」「逝去」「静かに旅立たれた」などの言葉を選ぶと、穏やかで丁寧な印象になります。
また、「4」や「9」などの数字も避けるのが望ましいとされています。言葉選びに不安がある場合は、あらかじめ葬儀社や会場スタッフに確認しておくと安心です。
献杯の挨拶は、長くなりすぎないように注意しましょう。故人との思い出をすべて語ろうとすると時間がかかり、会食の進行を妨げてしまうこともあります。
挨拶は「参列者への感謝」「故人へのひと言」「献杯の発声」の三部構成を意識し、30秒から1分程度にまとめます。メモを手元に置いて話しても失礼にはあたりません。落ち着いて、丁寧に言葉を届けることが何より大切です。
参列者側も、献杯の基本的なマナーを知っておくことで、ご遺族や周囲に対しても丁寧な印象を与えられます。ここでは、参列時に気をつけたい主なポイントを紹介します。
献杯の際に、自分でグラスや盃に飲み物を注ぐのは避けましょう。会場ではスタッフや遺族が、順に飲み物を用意してくれるのが一般的です。小規模な会食では、喪主が参列者に飲み物を注いで回る場合もあります。
自分で用意しようとせず、全員に飲み物が行き渡るまで静かに待つのがマナーです。
献杯が行われる前に料理や飲み物に手をつけるのは失礼にあたります。挨拶が始まったら、会場全体が厳粛な雰囲気に包まれるため、私語や物音も控えましょう。
代表者の「献杯」という発声が終わってから、静かに杯を掲げて唱和するのが正しい作法です。
献杯の場では、乾杯のようにグラスを打ち合わせたり音を立てたりすることはマナー違反です。厳粛な場で音を立てることは、故人に対して軽率な印象を与えるおそれがあります。
グラスは自分の胸の高さで静かに掲げ、落ち着いた所作で唱和しましょう。賑やかな声や拍手も控え、静かな祈りの気持ちを大切にします。
家族葬は、故人のご家族やごく親しい関係者だけで静かに見送る葬儀の形です。規模が小さい分、進行や挨拶の方法にも自由度があります。
ここでは、家族葬で献杯を行う際の考え方や注意点を紹介します。
家族葬の場合も、献杯の挨拶を行う人に明確な決まりはありません。一般的には、喪主から依頼を受けた親族や故人と親しい友人が務めます。
まれに喪主自身が挨拶を兼ねるケースもありますが、進行を担う役割との両立は難しいため、別の方にお願いするのが望ましいでしょう。
挨拶を依頼する際は、事前に趣旨と所要時間を伝えておくと、当日も落ち着いて臨むことができます。小規模な家族葬では、親族が順に杯を掲げながら故人を偲ぶなど、形式にとらわれない進行も見られます。
家族葬では、必ずしも献杯を行う必要はありません。ただし、法要や会食の前に簡単な献杯の挨拶を取り入れることで、場の区切りをつけ、故人を正式に見送る節目とすることができます。
挨拶の内容は、感謝の言葉と故人を偲ぶひと言を添える程度で十分です。形式を簡略化しても「皆で心を合わせて故人を想う」という意味は変わりません。
時間の都合や宗派の理由などで献杯を省略しても、失礼にはあたりません。代わりに、食事の前に喪主が「本日はお集まりいただきありがとうございます。故人を想いながらお過ごしください」と一言添えるだけでも、十分に丁寧な弔いになります。
また、黙祷や合掌を行うなど、宗教色を強めずに静かに故人を偲ぶ方法もあります。家族葬では形式にこだわるよりも、ご家族が心から納得できる形で故人を送ることが何より大切です。
献杯の挨拶では、献杯を誰が行うかによっても挨拶の内容が少し異なります。ここでは、喪主、故人の子ども、親族代表、友人・知人のそれぞれでの挨拶文例をご紹介します。また、法要や追悼会での献杯挨拶の文例についてもご紹介します。
本日はお忙しい中、葬儀にご参列いただき誠にありがとうございます。皆さまに見送っていただき、故人も安らかに旅立つことができたと思います。
感謝の気持ちを込めて、故人の冥福をお祈りし、献杯いたします。献杯。
本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。父(母)は、生前、皆さまに温かくお付き合いいただき、本当にありがとうございました。家族一同、心より感謝申し上げます。
どうぞ本日は、故人を偲びながら、穏やかなひとときをお過ごしください。献杯。
ご紹介にあずかりました〇〇の親族の〇〇でございます。本日はご多用の中、ご参列いただき誠にありがとうございます。
故人を偲びながら、皆さまとともに穏やかな時間を過ごせれば幸いです。それでは、故人の冥福をお祈りし、献杯いたします。献杯。
〇〇さんとは長年の友人であり、いつも前向きな姿に励まされてきました。突然のお別れとなり、言葉もありませんが、
これまでの感謝を胸に、故人の冥福をお祈りいたします。献杯。
本日は〇〇の一周忌(または三回忌)にお集まりいただき、ありがとうございます。皆さまと共に、故人を偲びながら穏やかな時間を過ごせればと思います。
それでは、故人の冥福を祈り、献杯いたします。献杯。
無理にお酒を口にする必要はありません。お茶や水、ソフトドリンクなど、どのような飲み物でも問題ありません。会場のスタッフにひと言伝えれば、ノンアルコールの飲み物を用意してもらえることが多いので、遠慮せず相談しましょう。
また、お酒が飲めない場合は、グラスを胸の高さに掲げ、軽く口元に運ぶしぐさだけでも十分に敬意が伝わります。
厳密な決まりはありませんが、一般的には「それでは故人のご冥福をお祈りし、献杯いたします。」がよく使われます。間違って「乾杯」と発声しないように注意しましょう。
献杯には特定の期限はありません。葬儀後の精進落としや法要のお斎、一周忌、三回忌など、故人を偲ぶ会食の場で都度行われるのが一般的です。
また、正式な法要の場でなくても、親しい人が集まって思い出を語る場で献杯を行っても差し支えありません。
献杯は、故人を想う気持ちを形に表す大切な儀式です。乾杯のように賑やかに行うのではなく、静かな所作の中に感謝や祈りを込めることで、故人への敬意を伝えることができます。
挨拶や作法に難しい決まりはありませんが、場の雰囲気を尊重し、落ち着いた心で臨むことが何より大切です。マナーを理解しておくことで、初めての場でも戸惑うことなく、故人を想う時間に集中できます。心を込めて杯を掲げ、故人の安らかな旅立ちを祈りましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。