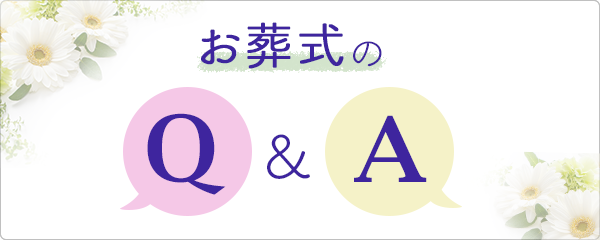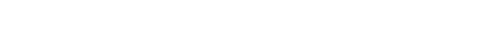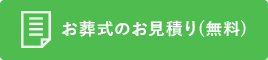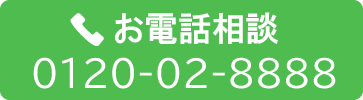通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/10/21
更新日:2025/10/21

 目次
目次● 菩提寺とは何かを知りたい方
● 菩提寺がわからずお困りの方
● 菩提寺を持つメリットを知りたい方
葬儀や法要の場で「菩提寺(ぼだいじ)」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、家の葬儀や法要をお願いするお寺のこと。普段の生活ではあまり意識する機会がないものの、いざというときに欠かせない存在でもあります。
日本では古くから、家と寺院とが密接に結びつき、支え合う関係を築いてきました。その背景には、江戸時代に幕府が定めた「寺請(てらうけ)制度」があります。当時すべての人がどこかの寺院の「檀家(だんか)」として所属することが義務づけられ、寺院は檀家の家族の死亡や出生を記録・管理する役割を担いました。これにより、寺院は単なる宗教施設にとどまらず、地域社会を支える存在となったのです。寺請制度は明治時代に廃止されたものの、人々は家族の供養や信仰を支えるお寺を「菩提寺」と呼んで大切にし、現在に至るまでその関係性は続いています。
「菩提寺」と似た言葉に「檀那寺(だんなでら)」があります。現在では菩提寺とほぼ同義で使われることもありますが、厳密にはその意味は異なります。檀那寺とは、檀家がお布施などを納めて経済的に支援し、葬儀や法要を依頼するお寺のことを指します。菩提寺と違って、そのお寺の土地に先祖代々のお墓があるとは限りません。一方、菩提寺は、経済的支援の有無に関わらず先祖代々の供養をお願いしているお寺のことをいい、家の信仰を代々受け継ぐお寺という意味合いがより強い言葉といえます。
「檀家」とは、特定の寺院に属し、供養や葬儀をお願いする家のことを指します。檀家となることで、葬儀や法要の際に僧侶に読経を依頼できる他、お墓の管理や仏事の相談などもお願いできます。また、お寺の運営を支える立場として、年に一度の護持会費(寺院維持のための費用)を納めたり、行事や法要に参加することもあります。檀家制度は、信仰を通じて互いに支え合う関係で成り立っています。
近年では、都市部への人口集中や核家族化の影響により、菩提寺との関係が希薄になっている家庭も少なくありません。自分の家の菩提寺がわからない、そもそも菩提寺を持たない、という家も増えています。地方の実家には菩提寺があるものの遠方のため日常的にお参りができない、または世代交代とともに寺院とのつながりが途絶えてしまった、というケースもめずらしくないでしょう。その他、宗教を問わない形式の葬儀・供養に対するニーズが以前より広がりつつあることや、継承者の不在により一代限りのお墓を建てる人が増えていることも、菩提寺を持たないという選択につながっているようです。
一方で、地域や世代よっては伝統的な檀家制度を一般的と捉える方がまだまだ多いのも事実です。菩提寺を持つべきかどうかは、それぞれの家庭の状況や価値観と照らし合わせながら、親族ともよく話し合って慎重に判断することが重要といえるでしょう。
菩提寺がある、ということは、葬儀や法要を行う際に大きな支えとなります。信頼できるお寺があることで、宗派に沿った形式で供養ができ、困ったときにも相談できる心強い存在になります。ここでは、菩提寺を持つことによる代表的なメリットをご紹介します。
菩提寺があると、葬儀や法要を行う際に新たに僧侶を探す必要がなく、遺族の負担軽減につながります。宗派に沿った正しい形式で葬儀や法要をお願いできるため、安心してお任せすることができるでしょう。また、菩提寺の境内にお墓がある場合、定期的な墓地の清掃や点検などの管理もお願いできますので、遠方に住んでいて頻繁に足を運ぶことが難しい方にとっても安心です。
菩提寺の僧侶は、葬儀や法要の形式、慣習などを熟知しています。葬儀の日程や法要の時期、供養の方法など、わからないことがあれば気軽に相談できる点もメリットといえるでしょう。家族の信仰や地域の風習に合わせたアドバイスが得られるのも、代々お付き合いがある寺院ならではといえます。
菩提寺に先祖代々のお墓がある場合、新たにお墓を用意する必要はありません。自分や家族が亡くなった場合は、そのお墓に入ることができます。新しい墓地を探して新規にお墓を購入する必要がないので、精神的にも経済的にも負担が軽くなります。また、代々受け継がれてきたお墓があることで、家族や親族も集まりやすく、永続的に守られていく安心感があります。
関連記事:
・お葬式の流れ(臨終~告別式終了まで)
菩提寺を持つことで多くの安心が得られる一方、お寺との信頼関係を維持するために知っておきたいことがあります。以下に、菩提寺を持つ上での留意点をまとめました。ただし、寺院によって考え方やルールは異なるため、わからないことがある場合は菩提寺または葬儀社に相談されることをおすすめします。
葬儀や法要をお願いする際は、戒名や読経、供養に対して「お布施」をお渡しするのが慣例です。お布施は「気持ち」であるため金額に明確な決まりはなく、地域や寺院、行う儀式の内容によっても異なります。不安な場合は、葬儀社や菩提寺に事前に相場を確認しておくと安心です。 また、菩提寺を持つと、お布施とは別に「護持会費(ごじかいひ)」を年に一度納める必要があります。護持会費とは、寺院の維持管理費用のことで、お墓の管理に必要な人件費・光熱費・備品費などにあてられます。金額はお寺ごとに異なりますが、年間5千円から2万円程度が目安とされています。
菩提寺にお墓がある場合、墓地全体の管理はお寺が行ってくれますが、個別のお墓の維持管理については家族が責任を持って行うことが望まれます。遠方に住んでいる場合は、お盆やお彼岸など節目の時期にお参りし、お墓や区画内の清掃を行うなど無理のない形でお付き合いを続けるとよいでしょう。
まれに、故人やご家族の意向により菩提寺以外で葬儀を行った場合、菩提寺にあるお墓に納骨できなくなるケースがあります。トラブルを避けるためにも、葬儀の形式や僧侶の依頼については、必ず事前に菩提寺や葬儀社へ相談しましょう。
葬儀や法要を行う際、「自分の家に菩提寺があるのかわからない」「菩提寺はあるけれど、遠方に住んでいる場合はどうすればいいだろう」と戸惑う方は少なくありません。いざというときに慌てず対応できるよう、ケース別の対応方法を知っておくと安心です。ここでは、菩提寺の有無や不明時、遠方の場合など、それぞれの状況に応じた進め方を紹介します。
仏式で葬儀や法要を行うときは、お寺の僧侶に読経をお願いすることが一般的です。自分の家の菩提寺がわかっている場合は、まずお寺へ一報を入れましょう。日程や式の内容を決める際は、菩提寺の予定を優先しながら、葬儀社とも相談して調整を進めるとスムーズです。お墓が菩提寺の境内にある場合は、納骨の日程や手順も一緒に確認しておくと良いでしょう。
近年は、実家の菩提寺が遠方にあるケースも増えています。この場合、まずは菩提寺の僧侶に来ていただけるかどうかを確認しましょう。その際、交通費や宿泊費についてもあらかじめ相談しておくとトラブルを避けられます。
もし来ていただけない場合は、住まいの近くにある菩提寺と同じ宗派のお寺をご紹介いただけることがあるので尋ねてみましょう。僧侶が来られず、お寺のご紹介もない場合は、葬儀社を通じて近隣のお寺にお願いする方法があります。その際は葬儀後に菩提寺へ報告を行い、法要や納骨の際に改めて依頼するなど、丁寧な連絡を心がけて良好な関係を保ちましょう。
特定のお寺とご縁がない場合でも、葬儀や法要を行うことは可能です。そのようなケースでは、葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらう方法が最も一般的でしょう。納骨を希望する場合は、公営や民営の墓地、永代供養墓などを選択することもできます。このとき、葬儀でお世話になったお寺を菩提寺にしなければならないのでは、と考える方もいらっしゃるようですが、現代においては住んでいる近くのお寺で葬儀を行い、葬儀後に実家近くの菩提寺に位牌を移すという人は多くいます。もちろん、こうしたご縁をきっかけに新たに菩提寺を持つこともあるでしょうし、葬儀を行ったお寺を菩提寺にしなかったからといって特にマナー違反などにはあたりません。ご家族の事情や生活環境に合った形を選びましょう。
自分の家に菩提寺があるかどうか不明の場合、まずは実家や親戚に、遺骨を埋葬するお墓がどこにあるかを確認することが最も確実です。また過去に法要をお願いしたお寺がある場合、その寺院が菩提寺である可能性が高いでしょう。その他、位牌や仏壇から宗派を特定できることがあります。また、位牌の裏面や仏壇内の掛け軸に宗派名や寺院名が記されている場合があるので、まずは確認してみましょう。
それでもわからない場合は、前述の「菩提寺がない場合」と同様、信頼できる葬儀社に相談すれば、僧侶を紹介してもらうこともできます。その他の葬儀・法要についての不安なことも、あわせて相談してみると良いでしょう。
・檀那寺とは、檀家が経済的に支援し、葬儀や法要を依頼するお寺のことを指す
・菩提寺と異なり、檀那寺には先祖代々のお墓が必ずしもあるとは限らない
・檀家とは、特定の寺院に所属し、葬儀や供養をお願いする家のこと
・近年は、菩提寺との関係が希薄になり、菩提寺を持たない家も増えつつある
・葬儀・法要を行う際に新たに僧侶を探す必要がなく、遺族の負担を軽減できる
・菩提寺の境内にお墓がある場合、墓地の清掃や点検などの管理面でも安心
・先祖代々のお墓がある場合、新たに墓地を探してお墓を購入する必要がない
・境内にお墓がある場合、個別のお墓の維持管理は家族が責任を持って行う
・異なる宗派の形式で葬儀を行うと、お墓に納骨できなくなる場合もある
・菩提寺が遠方にある場合、まずは僧侶に来ていただけるかどうかを確認する
・遠方で来ていただけない場合、近くの同じ宗派のお寺をご紹介いただけることも
・トラブルを避けるためにも、葬儀・法要については早めに菩提寺に相談しておく
・菩提寺がわからないときは、家族や親戚に確認することが確実な方法
・位牌や仏壇を確認することで、宗派や菩提寺がわかる場合もある
・葬儀を行ってもらった寺院を菩提寺にしなければならないわけではない
もしものときは突然訪れることが多いものです。いざというときに慌てず対応できるよう、菩提寺があるか一度調べておき、情報を整理しておくとよいでしょう。わからない方は菩提寺や葬儀社に早めに相談しておくことが、安心してお見送りするための準備につながります。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。