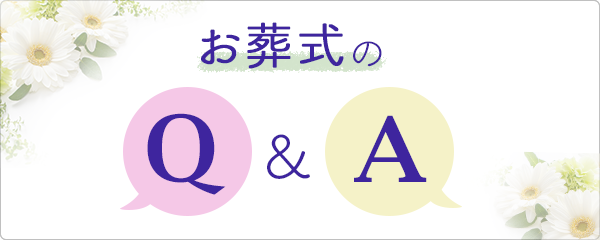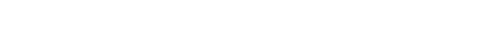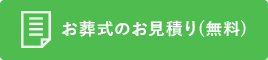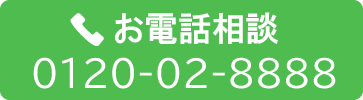通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/08/21
更新日:2025/08/21

 目次
目次親を亡くしたその日は、悲しみと混乱の中、何から手をつければいいのか分からず茫然としてしまうでしょう。しかし、葬儀の準備や役所への届け出、相続手続きなど、遺された家族が進めるべきことは数多くあります。
本記事では、親のご逝去後すぐに取りかかるべき手続きと準備を、当日から翌日、さらに翌々日までの流れに沿って丁寧に解説します。死亡診断書の受け取りや訃報連絡、葬儀社の選定から各種届出、さらにその後の相続手続きまで、ステップごとにわかりやすくご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。
● 火葬の定義や歴史を知りたい方
● 火葬の流れやマナーについて知りたい方
● 火葬に必要な手続きを知りたい方
日本では、葬儀や告別式を終えた後、ご遺族やご親族が故人のご遺体とともに火葬場に移動して、火葬を行うことがほとんどです。お見送りのかたちとして日本で当たり前のように行われている「火葬」ですが、そもそもどのような意味があり、どのようなルールに基づいて行われているのでしょうか。ここでは、日本における火葬の定義やその位置付けについて解説します。
火葬とは、故人の遺体を焼却して遺骨にする葬送の方法であり、現代の日本において最も一般的な形式です。火葬は日本の法律で定められた手続きに従って行われ、現在は国内のほとんどの自治体において火葬が義務付けられています。
日本における火葬率は約99.99%。これは世界的に見て非常に高い水準です。国内に火葬が普及した背景には、宗教的な価値観の変化や社会構造の変化など、さまざまな理由があります。特に都市部では土葬のスペースを確保することが難しく、限られた土地でご遺体を処理できる火葬が合理的な選択肢とされてきました。また、日本の公衆衛生の維持という観点からも、火葬は重要な役割を果たしています。
火葬および埋葬に関する基本的なルールは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって定められています。墓埋法には、「火葬」とは"死体を葬るために、これを焼くことをいう"と定義されており、火葬を行うには市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないこと、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければならないこと、火葬場以外の施設で行ってはならないこと、などが規定されています。
現代の日本では、人が亡くなると当たり前のように火葬が行われていますが、かつては土葬が主流でした。それでは、火葬はどのように日本国内に普及し、なぜ主流になってきたのでしょうか。ここでは、日本における火葬の歴史についてまとめました。
日本における火葬の歴史は、飛鳥時代にまでさかのぼります。仏教が伝来する中で、その教えとともに火葬の文化が伝えられ、僧侶や上流階級の間で火葬が少しずつ受け入れられるようになりました。このように一部の限られた人々の間で行われていた火葬が、一般庶民にも行われるようになったのは江戸時代の頃。都市の人口密度が高まり、感染症や悪臭といった衛生上の課題が生じてきたことから、都市部を中心に庶民の間にも火葬の文化が広がっていきました。
その後、明治時代に入ると、近代化政策の流れで一時的に火葬が禁止されたものの、公衆衛生の観点から、その必要性が見直されて間もなく解禁。さらに、法律や施設の整備が進み、衛生面の向上や土地の有効利用にもつながることから、火葬は全国的に広く普及しました。現在も日本の法律で土葬は禁止されていませんが、自治体の条例や墓地の管理規約によって制限されていることが多く、国内のごく限られた地域でしか土葬を行うことはできません。
火葬を行うためには、事前にいくつかの手続きが必要です。また、火葬を行うタイミングには法律上の決まりがありますので、以下にご紹介します。
火葬を行う前提として、人が亡くなったときは死亡を知った日から7日以内に「死亡届」を提出する必要があります。このとき、医師が記入した「死亡診断書」も必要となりますが、死亡診断書の書類は死亡届と一体になっている場合がほとんどです。
さらに、ご遺体を火葬するためには「火葬許可証」が必要です。火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、葬儀の前に必ず取得しなければなりません。火葬許可証の申請は、死亡届の提出と同時に行われることが一般的です。死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、この書類を火葬場のスタッフに提出することでご遺体の火葬が可能になります。
日本では、死亡後すぐに火葬を行うことは認められていません。「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」に、死亡を確認してから24時間を経過しないと火葬してはならないと規定されているためです。墓埋法が施行された当時は、現代に比べて医療が発達していなかったことから、誤診や仮死状態の可能性を避けるための措置として定められました。これにより、火葬は死亡の翌日以降に行われることが原則となっています。ただし例外として、エボラ出血熱などの一類感染症で亡くなった場合は、感染拡大のリスクを避けるため死後24時間以内にご遺体を火葬することが義務づけられています。
火葬が終わると、火葬場から「火葬済み」の印が押された火葬許可証が返却され、この書類がそのまま「埋葬許可証」となります。納骨の際に必要になりますので、それまでは自宅で保管しておき、実際に納骨を行うときに墓地や霊園に提出しましょう。万が一、紛失した場合は再発行の手続きを行う必要があります。申請には手間も時間もかかるため、失くさないよう大切に保管しましょう。
火葬をスムーズに進めるためにも、全体の流れをあらかじめ理解しておくと安心です。以下に、火葬場の予約から当日までの基本的な流れをまとめました。
火葬場を利用する際は、事前に予約が必要です。実際には、ご遺族が直接予約を行うケースは少なく、葬儀社が代行して手続きを行うことが一般的です。地域や時期によっては火葬場が混み合い、火葬場の空き状況に合わせて葬儀の日取りが決まることも少なくありません。また、自治体によっては公営火葬場の利用に一定の制限が設けられている場合もありますので、公営火葬場の利用を検討している場合はあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
当日の持ち物で特に重要なものは、「火葬許可証」・「遺影写真」・「位牌」の3点です。「火葬許可証」を忘れると火葬を行うことができないので、忘れずに持参しましょう。その他、お供えやお花などを必要に応じて用意します。
火葬当日は、おおむね以下のような流れで進行します。
火葬そのものにかかる時間は、おおよそ40分から1時間程度です。ただし、これは一般的な目安であり、火葬場の設備、棺の種類、故人の年齢や体格などによっても変動します。また、火葬場の混雑状況によっては、火葬を行う順番を待つ時間が発生する場合もありますので、時間に余裕をもっておくと安心です。
火葬が行われている間は、火葬場内の控室で待機します。控室は共有スペースであるため、大声で話すなどの賑やかな振る舞いは慎み、他の利用者にも配慮して静かに過ごしましょう。待ち時間にお茶や軽食が提供される場合もありますが、飲食や持ち込みに関するルールは火葬場ごとに異なるため、気になる場合は事前に確認しておくとよいでしょう。火葬に参列する際の服装は、一般的には喪服が基本です。ただし、家族葬などごく身内のみで行う場合は、黒やダークグレーといった落ち着いた色合いの平服でも問題ありません。
「骨上げ(こつあげ)」とは、火葬した故人の遺骨を、遺族や親族が骨壷に納める儀式のことをいいます。二人一組になり、長い箸を使って遺骨を拾い、骨壷に納めていく作法が一般的です。日常において、箸から箸へと食べ物を受け渡す「箸渡し」がマナー違反とされるのは、この骨上げを連想させるためです。
ご遺骨は初めに足の骨から拾い、徐々に上へと進め、最後に喉仏を納めます。これは、喉仏には故人の魂が宿るとされているためです。所作や順序には地域や宗派による違いもありますので、当日は係員の案内に従って行いましょう。
火葬式(直葬)とは、通夜や告別式といった儀式を省略し、火葬のみを行う葬儀形式です。ご遺族やごく親しい方が火葬場で故人にお別れを告げた後、そのまま火葬を行います。儀式や会食を行わないため所要時間はトータルで2時間前後と、他の葬儀形式と比較して短時間で完結することが特徴です。
近年、直葬を選ぶ方が増加している背景には、故人が生前から「葬儀を簡素に済ませたい」と希望するケースが増えている他、昔に比べて地域や職場のつながりが希薄になり、葬儀に多くの人を招く必要性が減ってきたことなどが挙げられます。また、コロナ禍を経て「少人数・短時間」の葬儀形式が一般的に受け入れられるようになってきたことも、直葬の広がりを後押ししているといえるでしょう。
直葬には経済的・時間的なご遺族の負担を軽減できるメリットがある反面、菩提寺がある場合は"直葬を選べない可能性が高い"、"故人と十分なお別れができない場合がある"、"伝統的な流れや慣習を重んじる方からは理解が得られないことがある"といったデメリットもあります。選択する際は、家族や親族とよく話し合った上で慎重に決めることが大切です。
火葬を行うにあたっては、いくつか注意しておきたいことがあります。ここでは、火葬を行う前に知っておきたいポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にされてください。
火葬場には、「公営」と「民営」があります。費用や設備、予約の取りやすさなど、両者には異なる点が多いため、あらかじめ違いを理解しておくとよいでしょう。
公営の火葬場は自治体が運営しており、住民であれば比較的安価に利用することができます。ただし、地域によっては予約がとりづらい場合もあるので注意が必要です。費用相場は、住民が利用する場合で0〜5万円程度、住民以外の方が利用する場合は5〜10万円程度とされています。
一方、民営の火葬場は利用条件がゆるやかで、設備やサービスが充実している施設も多いことが特徴です。ただし、公営に比べて費用は高くなる傾向があり、地域や立地などによっても異なりますが、費用相場は5〜15万円程度とされています。
故人の棺に、生前愛用していたものや思い出の品などを一緒に入れたいと考える方も多いことでしょう。しかし、火葬の妨げになるものや発火・破裂のおそれがあるものなど、棺には入れてはいけないものがあります。アクセサリーや時計といった金属製品、革製品、ガラス製品、ライターや電池、お金などがその一例です。故人が身につけていたメガネや結婚指輪なども、棺に入れることはできないので気をつけましょう。判断に迷う場合は、火葬場や葬儀社に前もって確認しておくと安心です。
火葬を待つ間も、火葬場を利用する他のご遺族への配慮を忘れないように過ごしましょう。大声での会話は控える、喫煙所以外では喫煙を行わないなど、火葬場内でのマナーを守ることが大切です。
・日本の火葬率は99.9%となっており、世界的に見ても非常に高い水準にある
・火葬に関するルールは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって定められている
・かつては土葬が主流だったが、明治時代以降、衛生面などの観点から火葬が主流になった
・ただし、一類感染症で亡くなった場合は、死後24時間以内に火葬しなければならない
・火葬を行うためには「火葬許可証」が必要。「死亡届」と同時に申請を行うことが一般的
・受領した「火葬許可証」は、火葬場のスタッフに提出する
・「火葬許可証」を忘れると火葬を行うことができないため、当日忘れずに持参する
・火葬にかかる時間は、約40分から1時間程度。待ち時間は控室で騒がずに過ごす
・金属製品や発火の恐れがあるもの、お金など、棺には入れてはいけないものがある
・火葬後は「埋葬許可証」を受領し、納骨まで自宅で大切に保管する
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。