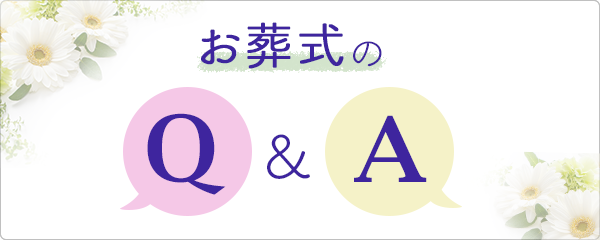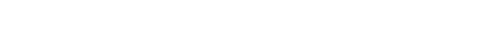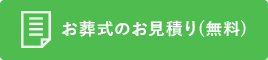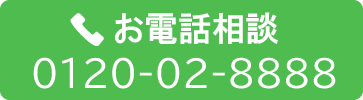通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/08/15
更新日:2025/08/15

 目次
目次葬儀で祭壇中央に置かれる白木位牌は、故人が亡くなってから四十九日法要まで用いられる仮のお位牌です。本位牌の準備が整うまでの大切な礼拝具ですが、使う期間や安置方法、役目を終えた後の処分など、迷うことも多いものです。
本記事では、白木位牌の意味や役割から本位牌への切り替え手順、処分方法、宗派ごとの違いまで詳しく解説します。
● 白木位牌の意味や役割を知りたい人
● 白木位牌の使用期間を知りたい人
● 白木位牌と本位牌の違いを知りたい人
● 白木位牌の作り方・準備方法を知りたい人
● 白木位牌から本位牌への切り替え方法を知りたい人
● 白木位牌の処分方法を知りたい人
そもそもお位牌とは、故人の戒名や没年月日などを記した礼拝具で、故人の魂が宿るとされます。ただしお位牌には、一般的には葬儀から四十九日まで用いる「白木位牌」と、それ以降に長く安置する「本位牌」の2種類があります。
ここでは、白木位牌について、その意味や役割を解説します。
白木位牌は、漆や金箔などの装飾を施さず、白木のまま仕立てた仮のお位牌で、「仮位牌」と呼ばれることもあります。葬儀から四十九日法要までの限られた期間に用いられ、本位牌ができあがるまでの間、故人の魂をお祀りします。
急なお別れに際して、本位牌(塗り位牌や唐木位牌など)を一から製作すると、漆塗りや彫刻、金箔仕上げなどの工程に時間がかかり、葬儀に間に合わないことがあります。そのため、短期間で準備でき、葬儀直後から礼拝に用いることができる白木位牌がまず用意されます。こうした経緯から「仮のお位牌」とされるのです。
また、地域や宗派によっては、白木位牌を大小2本用意することもあります。大きいほうを「内位牌(うちいはい)」と呼び、自宅で安置した後、本位牌へ移す際の元となります。小さいほうは「野位牌(のいはい)」といい、納骨の際に墓地へ持参し、お焚き上げや納骨時の供養に用いられることがあります。
白木位牌は四十九日法要までの仮のお位牌であるのに対し、本位牌は長期安置用の正式な位牌です。本位牌にも、白木位牌と同様に故人の魂が宿る依り代として礼拝の対象となり、日々の供養や年忌法要、盆・彼岸などで手を合わせる役割があります。
本位牌は、塗り位牌や唐木位牌、モダン位牌など、漆塗りや銘木仕上げで耐久性や格式を備えており、装飾や形状も多様です。また、白木位牌から本位牌へ移す際には、宗派や菩提寺の決まりに従い、冠字や梵字、上文字、置字などを省略する場合があります。
白木位牌は、葬儀から四十九日法要までの限られた期間に使用する仮のお位牌です。ここでは、具体的な使用期間と、その間の安置場所や扱い方について解説します。
白木位牌は、故人が亡くなった直後から四十九日法要まで使用します。葬儀では祭壇中央に置かれ、通夜・告別式の間は参列者が礼拝できるように設けられます。
仏教では、故人の魂は亡くなってから四十九日までの間、あの世とこの世を行き来し、七日ごとの審判を受けるとされます。四十九日目は「忌明け」にあたり、来世の行き先が決まる大切な日です。この節目に本位牌を用意し、白木位牌から魂を移す「魂入れ(開眼供養)」を行い、本位牌を仏壇に安置します。
やむを得ず四十九日までに本位牌の準備が間に合わない場合は、お盆や命日などの節目に切り替えることもありますが、できる限り四十九日法要に合わせるのが望ましいとされています。
葬儀後、白木位牌は「後飾り(あとかざり)祭壇」と呼ばれる仮の祭壇に安置します。後飾り祭壇はご遺骨や遺影とともに置かれ、四十九日法要まで日々の礼拝の場となります。
直射日光や湿気、冷暖房の風が直接当たる場所は避け、安定した環境で安置しましょう。白木は塗装をしていないため汚れや傷みに弱く、手で触れる際は手袋を使用するか、できるだけ直接触れないようにします。
また、必要に応じてお位牌用の透明カバーや布カバーをかけると、ホコリや湿気から保護できます。お手入れでは、柔らかい乾いた布で軽くホコリを払う程度にとどめ、水拭きや薬品の使用は避けましょう。
白木位牌は、葬儀社が用意したものに、僧侶が戒名や没年月日などを記して準備するのが一般的です。記載内容には宗派や地域の慣習による違いがあり、特に享年・行年の表記には注意が必要です。
ここでは、白木位牌の準備方法と主な記載項目について解説します。
白木位牌は多くの場合、葬儀を依頼した葬儀社が用意します。葬儀の日程が決まると、僧侶から授与された戒名(浄土真宗では法名)、俗名、生年月日や没年月日などを、葬儀社スタッフが墨書きまたは印字して作成します。地域や寺院によっては、僧侶自らが記入する場合もあります。
漆や金箔などの装飾を施さないため製作期間が短く、急な葬儀にも間に合うのが特徴です。依頼者が自ら準備する必要はほとんどありませんが、戒名や日付の誤りがないか、事前に確認しておくと安心です。
白木位牌には、故人を特定し、供養の対象とするための情報が記されます。主な内容は以下のとおりです。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 戒名(法名・法号) | 僧侶から授けられる仏教徒としての名前 |
| 俗名 | 生前の氏名 戒名の裏面に記されることが多い |
| 没年月日 | 命日 |
| 享年または行年 | 亡くなった時の年齢 ・享年:数え年で表した年齢(生まれた年を1歳とし、以降は元旦で加齢) ・行年...満年齢で表した年齢(誕生日ごとに加齢) |
また、享年と行年のどちらを用いるかは、宗派や地域の慣習、あるいは菩提寺によって異なります。かつては享年表記が主流でしたが、最近では満年齢での表記(行年)を選ぶケースも増えています。不明な場合は、必ず菩提寺や葬儀社に確認しましょう。
戒名の上下に冠字や梵字、下部に「位」や「霊位」といった文字が入ることもあります。これらの要素は宗派によって異なり、本位牌に移す際に省略される場合もあります。
白木位牌はあくまで仮のお位牌であり、一定期間を過ぎたら本位牌へ切り替えます。切り替えは宗教的な儀式を伴うため、時期や準備を間違えないことが大切です。
ここでは、切り替えの流れや本位牌の種類、宗派ごとの違いについて解説します。
本位牌への切り替えは、四十九日法要にあわせて行うのが一般的です。
まず、白木位牌から故人の魂を抜く「魂抜き(閉眼供養)」を行います。これは僧侶が読経して礼拝対象としての性格を外す儀式で、「お性根抜き」とも呼ばれます。
続いて、本位牌へ魂を移す「魂入れ(開眼供養)」を行い、新たに仏壇へ安置します。魂入れは「お性根入れ」とも呼ばれ、これにより本位牌が正式な礼拝具として機能します。この2つの儀式は、四十九日法要の中で続けて行われます
本位牌にはいくつかの種類があります。
| 本位牌の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 塗り位牌 | 木地に漆塗りを施し、金箔や金粉で装飾した伝統的なお位牌 |
| 唐木位牌 | 黒檀や紫檀などの銘木で作られ、木目の美しさが特徴 |
| モダン位牌 | ガラスやアクリル、寄木など現代的な素材・デザインのお位牌 |
| 回出位牌 (くりだしいはい) |
複数の札板を一つにまとめて収納できるお位牌 |
本位牌に刻む文字は、白木位牌の内容をもとにしますが、宗派や菩提寺の方針によっては、白木位牌に記されていた冠字や梵字、上文字、置字などを省く場合があります。本位牌の製作にあたっては、必ず白木位牌を持参するか写真を添えて依頼し、文字や日付に誤りがないようにしましょう。
関連ページ:
・位牌の選び方
「位牌分け」とは、1つの戒名を複数の本位牌に刻み、兄弟姉妹や分家などでそれぞれ安置することです。例えば、実家の仏壇と自宅の仏壇の両方に同じ故人のお位牌を祀りたい場合に行われます。
位牌分けをする際も、開眼供養をそれぞれの本位牌に行うのが望ましいため、菩提寺や僧侶に相談して手順を決めましょう。
本位牌の有無や形式は宗派によって異なり、使用する場合も記載内容や形状に決まりがあります。ここでは、代表的な宗派ごとの違いを紹介します。
原則としてお位牌を用いず「法名軸」や「過去帳」を用います。浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに成仏すると考えるため、お位牌による供養という考え方がありません。法名軸には、故人の法名(戒名に相当)や没年月日などを記し、仏壇内に掛けて安置します。過去帳は、歴代の先祖の法名や没年月日を記した帳面で、命日の確認や法要時に使用します。
お位牌は必須とされ、戒名の上部に宗派ごとの梵字(例:釈迦如来を表す「バク」字)や冠字を記すことがあります。また、裏面には俗名や没年月日、享年(行年)を記載します。
真言宗では、戒名の上に「ア字の梵字」を入れ、下に「位」を記す形式が見られます。本位牌に移す際、一般的には梵字や冠字、上文字を残すケースが多く見られますが、寺院の方針や地域の慣習によっても異なります。
戒名は「法号」と呼び「南無妙法蓮華経」の題目を併記する場合があります。戒名の上に「妙法」や「法名」といった冠字が入り、裏面に俗名や没年月日を記載します。
戒名の上に「空」や「妙法」などの冠字を入れ、裏面には俗名と享年(行年)を記す形式が一般的です。
ただし、同じ宗派でも地域や寺院によって細かい違いがあるため、表記や省略の可否は菩提寺に確認しましょう。
白木位牌は本位牌への切り替えに伴い、その役目を終えます。しかし、故人の戒名や没年月日などが記されているため、適切な方法で処分することが大切です。
ここでは、正しい処分の流れや注意点、お焚き上げの概要と費用相場を解説します。
白木位牌には、故人の魂が宿るとされています。そのため、処分前にはまず僧侶による「魂抜き(閉眼供養)」を行い、礼拝対象としての役割を終えてから処分します。
魂抜きを行った後は、寺院や仏具店に依頼してお焚き上げをしてもらうのが一般的です。お焚き上げには、炎によって故人を天に送り返す意味があり、供養の一環とされています。
魂抜きを済ませた白木位牌は、宗教的にはただの木の板と考えられますが、戒名や没年月日などの個人情報が記載されているため、家庭ごみとして廃棄するのは望ましくありません。感情的にも心理的にも抵抗を感じる方が多く、またごみとして処分すると近隣や家族に誤解を招く可能性もあります。
そのため、できる限り寺院や専門業者に依頼し、適切な供養と焼却処分を行うことが推奨されます。
白木位牌のお焚き上げは、依頼先によって流れや費用が異なりますが、一般的には次のような手順です。
1. 寺院や仏具店、供養専門業者に依頼
2. 指定日までに白木位牌を持参または郵送
3. 魂抜きの読経(すでに済んでいる場合は省略)
4. 専用炉や境内での焼却供養
5. 供養終了の報告(証明書や写真を送付する場合もあり)
費用相場は、寺院での魂抜きとお焚き上げを合わせて5,000円〜1万5,000円程度が一般的です。郵送供養サービスの場合は、送料が別途かかることがあります。事前に流れや料金、受付方法を確認しておきましょう。
お位牌の形状は共通していても、刻まれる戒名の形式や表記方法、適切なサイズは宗派によって異なります。ここでは、宗派別の戒名の特徴と、お位牌のサイズや形状の注意点を解説します。
戒名(法名・法号)は、宗派ごとに構成や呼び方、付け加える文字が異なります。
位号は宗派ごとの教義や伝統に基づくため、本位牌を作る際は必ず菩提寺に確認し、表記を統一しましょう。以下の関連記事に詳しく解説しているのでご参照ください。
お位牌は宗派を問わず、ご本尊よりも高さが大きくならないように選ぶのが基本です。また、既に仏壇内にほかのお位牌がある場合は、形状やサイズをそろえることで全体のバランスが保たれます。ただし、宗派や寺院によっては、寸法や形状について具体的な指定がある場合もあるため注意しましょう。
新しくお位牌を作る際は、文字数なども考慮したうえで、菩提寺や仏具店に相談しながら作成することをおすすめします。
白木位牌は、故人が亡くなってから四十九日法要までの間お祀りする仮の位牌で、本位牌が完成するまでの大切な礼拝具です。使用期間や安置場所、記載内容には宗派や地域ごとの違いがあり、本位牌への切り替えや処分にも決まった流れがあります。
本記事では、白木位牌の役割や意味から始まり、使用期間と安置の仕方、作り方や記載内容、本位牌への切り替え手順や注意点、そして役目を終えた後の処分方法までを解説してきました。これらを理解しておくことで、葬儀後の慌ただしい時期にも迷わず対応でき、故人を丁寧にお見送りする準備が整います。
大切な方を心を込めてお見送りするために、事前に流れを把握し、菩提寺や信頼できる葬儀社と相談しながら進めていきましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。