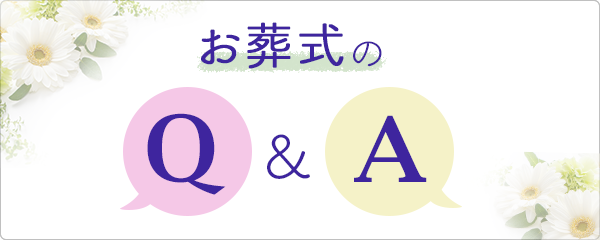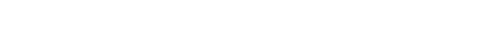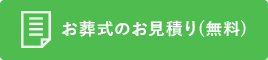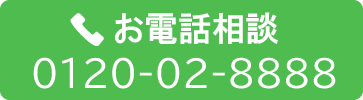通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/07/18
更新日:2025/07/18

 目次
目次● 葬儀に呼ぶべき人数にお悩みの方
● 一般葬と家族葬の違いを知りたい方
● 家族葬のメリット・デメリットが気になる方
家族葬を営むにあたり、どの範囲まで親族を葬儀に呼ぶべきか頭を悩ませる方は多いのではないでしょうか。葬儀に誰を呼ぶかを考える上で、まずは「遺族」と「親族」の違いを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、その違いや親族の範囲を示す「親等」について詳しく解説します。
一般的に、「親族」とは血縁や婚姻によるつながりのある人のことをいいます。「遺族」とは、その中でも"故人と生計を共にしていた人"を指し、より身近で日常的に関わりのあった人であることを意味します。亡くなった方と一緒に生活していた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は「遺族」に該当します。一方、離れて暮らす甥や姪、おじ・おば、いとこは「親族」とみなされますが、父母や祖父母、兄弟姉妹であっても、独立して生計が別であれば遺族ではなく「親族」とされる場合があります。
なお、民法では「親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族まで」と定められており、誰が該当するかは、以下で解説する「親等」によって判断されます。
「親等」とは、民法において親族間の世代数を示す単位のことです。自分から見て、どれだけ血縁や婚姻関係による親族関係が近いか遠いかをあらわします。民法上の親族関係は、「血族」と「姻族」に分けられ、「血族」とは血縁関係にある人のことを指し、実際に血のつながりがある人だけではなく、養子縁組によって法律上親子関係が生じた場合も含まれます。「姻族」とは、婚姻によって親族関係が生じた人のことをいい、配偶者の血族と、血族の配偶者が該当します。なお、配偶者は、血族でも姻族でもありません。
| 親等 | 関係 |
|---|---|
| 1親等 | 親、子 |
| 2親等 | 祖父母、孫、兄弟姉妹 |
| 3親等 | 曾祖父母、ひ孫、おじ・おば、甥・姪 |
| 4親等 | いとこ |
| 親等 | 関係 |
|---|---|
| 1親等 | 配偶者の父母 |
| 2親等 | (本人の)兄弟姉妹の配偶者 配偶者の祖父母、兄弟姉妹 |
| 3親等 | (本人の)甥・姪の配偶者 配偶者のおじ・おば、甥・姪 |
| 4親等 | (本人・配偶者の)いとこ |
ここでは、家族葬に呼ぶべき人数と親等の関係について葬儀の規模別に解説します。ただし、たとえば故人の兄弟姉妹が多い場合は参列者の数が増えるなど、状況によっても大きく変動しますので、あくまでも一般的な目安としてお役立ていただければ幸いです。
参列者が10名ほどの小規模な家族葬では、遺族と2親等までの親族で行うことが一般的です。故人と生計をともにしていた家族、両親や兄弟姉妹、その配偶者や子どもなど、ごく近親者のみで執り行うケースが多くなります。ただし、故人の兄弟姉妹が多い場合など必然的に10名を超えることもありますので、無理に葬儀の規模に合わせて人数を抑えようとせず、状況に応じて判断しましょう。
20〜30名程度の中規模な家族葬では、3〜4親等までの親族を含めるケースが多いようです。おじ・おば、いとこ、甥や姪など、遠方に住んでいてなかなか会えない方であっても、生前に親しかった方や関わりの深かった方には声をかけるとよいでしょう。
参列者が30名を超える場合、家族葬としてはやや大きな規模になります。遺族や親族に加え、故人と生前親しかった友人などをお呼びすることが多いようです。「家族葬」だからといって、遺族・親族のみに範囲を限定する必要はありません。「故人と最後のお別れをしていただきたい方に来ていただく」という気持ちを大切にしましょう。
一般葬は、「参列者に制限を設けない」葬儀形式であり、あらかじめ参列者の人数を把握することは難しいものです。目安として、30人から100人程度の規模になるケースが多いとされていますが、故人の交友関係や社会的立場、地域性などによって大きく異なります。
葬儀を行うにあたり、家族葬と一般葬のどちらを選択するかで悩まれる方も多いでしょう。家族葬と一般葬には、参列者の人数以外にも異なる点があります。ここでは、それぞれの違いについてご紹介します。
家族葬と一般葬の最大の違いは、「参列者を限定するかどうか」という点です。家族葬では、ごく近しい親族や親しかった方のみをお呼びするのに対し、一般葬では制限を設けることなく仕事関係や地域の方など広く参列を受け入れます。
一般葬では、香典を持参して参列することが基本となっており、地域によっては供花や供物が並ぶこともあります。一方、家族葬では「香典辞退」や「供花はご遠慮ください」と事前に伝えるケースも多く、儀礼的なやりとりを簡素にする傾向があります。
参列者を制限しない一般葬では、当日どのくらいの参列者が弔問に訪れるか予測することが難しいため、広めの葬儀会場を選ぶ必要があります。家族葬では、参列者の数をあらかじめ把握できるので、葬儀の規模や会場の広さを調整することが可能です。広い会場を用意する必要もなく、比較的費用を抑えやすい形式といえます。
一般葬は、通夜・告別式の2日間で行うことが基本です。対して家族葬では、通夜を省略して一日で完結する「一日葬」や、通夜・告別式を行わない「直葬」という形式を選ぶことも可能です。また、参列者は遺族や親族、ごく親しい友人に限られるため、日程の調整がしやすい点も特徴といえます。
| - | 家族葬 | 一般葬 |
|---|---|---|
| 参列者 | 親族やごく親しい友人に限定 | 制限はなく幅広い人が訪れる |
| 葬儀会場 | 小規模な式場 | 大規模な斎場・会館 |
| 内容 | 遺族・故人の意思を反映しやすい | 一般的な流れに沿った形式 |
| 会食 | 行わないことも多い | 多人数の精進落としや通夜ぶるまい |
| 返礼品 | 簡素化される傾向がある | 香典の半額程度の品 |
| 費用相場 | 90〜100万円前後 | 150万円前後 |
家族葬に対する関心は年々高まっています。単に「小規模だから」「費用が抑えられるから」という理由だけではなく、故人やご遺族の想いを大切にできる葬儀形式として家族葬を選ぶ方も増えているようです。とはいえ、やはり従来の一般葬とは異なる新しい葬儀形式であることから、家族葬を選ぶ際にはあらかじめ注意しておきたい点があります。ここでは、家族葬の主なメリットとデメリットについて解説します。
従来の形式にとらわれず、故人の希望やご家族の想いを内容に反映しやすいことが家族葬の大きな魅力です。読経などの宗教的な儀式の代わりに故人が好きだった音楽で構成する「音楽葬」や、好みの花で祭壇を飾る「花祭壇」など、自由度の高い葬儀にも柔軟に対応することができます。
気心の知れた人のみで葬儀を行うため、参列者の対応に追われることなく静かにお別れの時間を過ごすことができます。落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりと思い出を語り合うことができるのは、家族葬ならではのメリットといえるでしょう。
多くの参列者が弔問に訪れる一般葬では、遺族が様々な対応に追われて個別にお礼を伝えることが難しい場合が少なくありません。家族葬は、参列者一人ひとりに丁寧な対応ができる点も魅力といえます。
葬儀に呼ぶ人数が限られているため、会場の選定や返礼品・会食などの準備にかかる負担を軽減することができます。あわせて、受付やご案内など、当日の負担も少なくて済みます。
参列者の数が少なく、会場の規模もコンパクトにできるため、一般葬に比べて費用を抑えられる点もメリットの一つです。ただし、式の内容やオプションによって費用は変動しますので、希望する内容がある場合は事前に確認しましょう。
「どの範囲まで声をかけるか」は、家族葬で多くの方が悩むポイントです。家族間で意見が分かれると後々トラブルに発展しかねないため、家族葬を検討する際は十分に話し合うことが必要です。
参列者が少ない分、受け取る香典が少なくなるため、実質的な費用負担が一般葬より大きくなってしまうことがあります。特に香典を辞退する場合は、その点を見越した準備が必要です。
家族葬は近年広まってきた新しい葬儀形式であり、一般葬と比べてどうしても簡略的な葬儀になることから、中には受け入れられない方もいます。気持ちよく故人を見送るためにも、事前に意図や内容を伝えておくなど、家族葬という形式を理解してもらえるよう丁寧に説明することが重要です。
家族葬が済んだ後、「葬儀に参列できなかったので改めてお別れをしたい」と、後日弔問に訪れる方も少なくありません。弔問客への対応が続くなど、葬儀後に遺族の負担が増える可能性があることも注意しましょう。
家族葬は、故人やご遺族の想いを大切にできる葬儀形式ですが、関係者への対応や進め方によっては思わぬ誤解や不満につながることもあります。無用なトラブルを避けるためにも、ここでは家族葬を行う上で注意したいポイントについて解説します。
近年、家族葬という葬儀形式への理解は広まりつつありますが、すべての方に受け入れられているとは限りません。親族の中には、「もっと多くの人に見送ってもらうべき」、「あらかじめ知らせてほしかった」など、家族葬という形式そのものに不満を抱く方がいらっしゃるかもしれません。近しい親族には、事前に家族葬であることを明確に伝え、できれば家族葬を選択した理由や想いを共有しておきたいところです。
参列者の制限を設けない一般葬とは異なり、葬儀に呼ぶ人の範囲を柔軟に決められることは家族葬の特徴の一つです。一方で、故人と親交の深かった友人など、最期のお別れの場に立ち会えないことを残念に感じる方がいる可能性もあります。特に葬儀を済ませてからの事後報告となった場合、「葬儀に参加したかった」と寂しさや戸惑いを感じさせてしまうことも少なくありません。後日弔問に訪れたときにお詫びの言葉をお伝えするなど、葬儀に参列できなかった方の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
家族葬で参列者の範囲を制限した場合、参列できなかった方々から、葬儀後に個別での弔問を希望されることも少なくありません。葬儀後に心身ともに疲れている中での連絡や訪問対応は、ご遺族にとって負担が大きいため、「弔問は控えていただく旨を知らせておく」、「香典は辞退する意思を伝える」など、あらかじめ対応方針を決めておくことをお勧めします。
家族葬は参列者が少ない分、一般葬に比べて香典収入が減少するため、葬儀全体の費用負担が増えることになります。小規模な葬儀であっても、会場費や火葬費、返礼品など、葬儀には様々な費用がかかるものです。特に香典を辞退する場合は、余裕をもって葬儀費用を用意しておく必要があります。
家族葬への参列をお願いしない方には、葬儀後に報告をすることが大切なマナーです。葬儀が終わって1〜2週間ほどのタイミングでお知らせをしましょう。お相手は、突然の訃報を事後報告という形で知らされることになるため、伝え方には十分な配慮が必要です。葬儀前にお知らせしなかった理由やお詫びを添えるなど、気持ちを込めて丁寧にお伝えすることを心がけましょう。
・ 民法では「親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族まで」とされている
・ 「親等」とは、親族間の世代数を示す単位で、「血族」と「姻族」に分けられる
・ 参列者が10名ほどの小規模な家族葬では、遺族と2親等までの親族が一般的
・ 20〜30名程度の中規模な家族葬では、3〜4親等までの親族を含めることが多い
・ 30名を超える場合は、遺族や親族に加え、親しい友人なども呼ぶ傾向にある
・ ただし、故人の兄弟姉妹が多ければ参列者も増えるなど、状況によって変動する
・ 親族や親しい友人のみで行う家族葬に対し、一般葬では広く参列を受け入れる
・ 参列者数の予測が難しい一般葬では、広めの会場を用意する必要がある
・ 一般葬では参列者の香典持参は普通だが、家族葬では辞退するケースも多い
・ 葬儀の自由度の高さやお別れの時間をゆっくり過ごせることが家族葬のメリット
・ 家族葬は参列者数が少ないため、準備や費用の負担を軽減できることも魅力
・ 参列者の選定が難しく、親族の中に家族葬に反対する人がいる可能性もある
・ 香典収入が少なくなる他、葬儀後の弔問客の対応なども考える必要がある
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常に待機し、お客様それぞれのお悩みやご事情に沿ったご提案やご相談をさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。