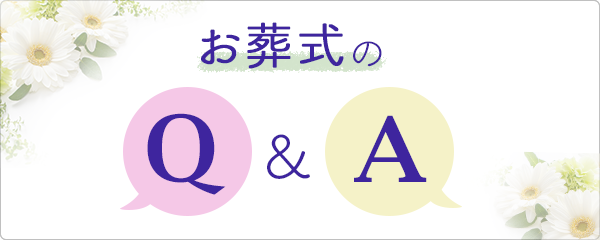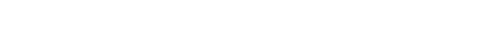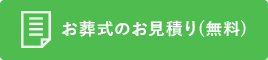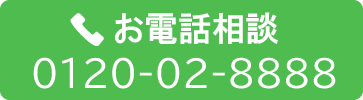通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/04/30
更新日:2025/07/08

 目次
目次日蓮宗は鎌倉時代の宗祖・日蓮聖人が開いた日本仏教の宗派です。「法華経」を唯一の経典として説き、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」の題目を唱和することによる現世利益と救済を重視しています。
本記事では、日蓮宗の教えが葬儀にどのように反映されるのかを解説しながら、葬儀の特徴や流れ、知っておくべきマナー、注意点を詳しく紹介します。さらに、法号授与に伴うお布施の相場や仏壇の飾り方まで、日蓮宗の葬儀・供養を総合的に解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
● 日蓮宗の歴史や主な教えを知りたい方
● 日蓮宗の葬儀の特徴や流れを知りたい方
● 日蓮宗の葬儀におけるマナーや作法を知りたい方
● 日蓮宗の葬儀のお布施の相場を知りたい方
● 日蓮宗の祭壇・仏壇の飾り方を知りたい方
日蓮宗は、お釈迦様の説かれた「法華経」を唯一の根本教典とし、その教えを身をもって広めた日蓮聖人(1222年〜1282年)を開祖とする日本仏教の一派です。法華経こそが仏の真意を説く「正法」であり、題目を唱えることが仏道修行の要とされる点が大きな特徴です。
まずは、日蓮宗の成り立ちや基本的な教えについて見ていきましょう。
日蓮宗は鎌倉時代の建長5年(1253年)、宗祖・日蓮聖人が千葉県の小湊で「法華経」の妙義を悟り、一乗教(法華経のみを信仰の拠り所とする教え)を掲げたことにはじまります。
その後、京都や鎌倉をはじめ各地で法華経の布教に努め、やがて「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」の唱和運動を確立し、多くの信徒を獲得しました。
日蓮信徒は「法華経」こそが釈迦の真の教え(正法)であると位置づけ、唱題と呼ばれる「南無妙法蓮華経」をひたすら繰り返すことを最上の修行としています。
この唱題には、単に言葉を口にするだけでなく、信仰心を日々の行いにまで一体化させる力があるとされています。たとえば、病気平癒や家内安全、商売繁盛といった現世における願い(現世利益)を成就するとともに、死を迎えた故人と遺族の心の救済にも繋がると考えられているのです。
こうした日蓮宗の教えは、葬儀の場にも色濃く反映されます。日蓮宗の葬儀は、導師と参列者が一体となって題目を唱えることで故人の成仏を祈願し、「仏道修行」の第一歩を踏み出す行事と位置づけられています。
日蓮宗で最も重んじられる根本経典は「妙法蓮華経(法華経)」そのものです。
法華経の真髄を一字一句に込めた「南無妙法蓮華経」を唱和し、その功徳を日々の信行とします。その他にも、法華経講義書として日蓮聖人の著作「開目抄」「観心本尊抄」などが講義の要とされることもありますが、葬儀など儀式の中心は常に「法華経の読誦」と「唱題」にあります。
日蓮宗の総本山は山梨県・身延山 久遠寺(みのぶさん くおんじ)です。
身延山 久遠寺は、建長5年(1253年)、日蓮聖人自身が草庵を結んだ地に、弟子の曽谷教信(そやきょうしん)が整備したお寺です。久遠の仏法を象徴する「久遠の本師釈迦牟尼仏」を本尊とし、全国の末寺を統括しています。
その他にも、日蓮聖人の遺骨を奉安する静岡・清澄寺(きよすみでら)や、鎌倉・大巧寺(だいぎょうじ)など、ゆかりの寺院も多く存在し、各地で法華経布教の拠点となっています。
日蓮宗の葬儀には、「法華経」を中心に据えた独自の儀式が数多く取り入れられており、その他の仏教宗派には見られない特徴が際立ちます。ここでは、特に押さえておきたい日蓮宗の葬儀の3つのポイントをご紹介します。
日蓮宗の葬儀最大の特色は、式中に僧侶だけでなく参列者全員が一体となって「南無妙法蓮華経」を唱える「題目読誦(だいもくどくじゅ)」です。
読経や焼香の合間に、お経ではなく題目を全員で声を合わせて唱えることで、故人の成仏を祈念するとともに、遺族・参列者一人ひとりが、仏道修行への第一歩を踏み出すという意味が込められています。
日蓮宗の葬儀では「妙鉢(みょうばち)」や「木柾(もくしょう)」といった打楽器が用いられ、題目唱和の節目を厳かに、力強く彩ります。
妙鉢は金属製の小鉢を打ち鳴らすもので、読経や唱題の区切りを示します。一方で、木柾は木製の棒で節を刻み、読経や唱題のリズムを支えます。このような鳴り物が加わることで、一同の唱和がより一層引き締まったものとなるのです。
「しきみ(樒・しきび)」は、多くの仏式葬儀で用いられる常緑樹です。1年中衰えない深い緑の葉は、仏教において「永遠の命」の象徴とされており、また毒性を持つことから邪気を払う力があるとも信じられています。
なかでも、日蓮宗の葬儀では、しきみが重要視されています。棺の周囲や祭壇にしきみを配することで、故人が煩悩や悪縁を断ち切り、清浄な環境のもとで仏道へ旅立つことを祈念します。さらに、常緑の葉が遺族に「仏の教えは変わることなく常にそばにある」という安心感を与える役割も果たし、日蓮宗ならではの葬儀空間を創り出します。
日蓮宗と日蓮正宗は、ともに宗祖・日蓮聖人を拠り所としながらも、後世の教義解釈や組織運営の違いから分かれていった宗派です。
ここでは、まず日蓮宗と日蓮正宗の教義的背景と歴史を簡潔に振り返り、そのうえで葬儀における具体的な相違点を紹介します。
日蓮宗は、鎌倉時代の建長5年(1253年)、日蓮聖人が千葉県小湊で法華経の深義を体得し、一乗教(法華経のみを頼る教え)を掲げたことにはじまります。誰もが題目唱和を通じて仏性を顕現できるとする「開かれた教義」を特徴とし、全国に約5,000の末寺を擁しています。
一方、日蓮正宗は、日蓮聖人の直弟子・日興上人が大石寺(静岡県富士宮市)を拠点に教団を整備したのが起源です。日蓮正宗は「末法救済(まっぽうきゅうさい)」を重視しており、仏法が衰え乱れる末法の時代にあっても、題目や御本尊を通じて衆生を救い導く実践を大切にしています。また、信徒以外の参列や儀式参加を制限する厳格な門戸管理を行う点も、日蓮正宗の特徴です。
日蓮宗と日蓮正宗の葬儀は、それぞれの教義の違いから以下のような相違点があります。
| 日蓮宗 | 日蓮正宗 | |
|---|---|---|
| 参列の制限 | 多くの寺院で一般参列を歓迎 | 信徒のみ、または信徒の紹介がなければ参列を制限 |
| 題目唱和 | 僧侶と参列者が一体となって「南無妙法蓮華経」を唱和 | 僧侶中心の唱題が基本 参列者の唱和は行われない場合もある |
| 読経形式 | 法華経を中心に、開経偈・宝塔偈など複数の経典を使用 | 大御本尊への礼拝を含む厳格な定型読経 |
| 焼香回数 | 1〜3回(寺院の指示に準じる) | 1回のみが基本 |
| 香典袋の表書き | 「御霊前」「御香典」 | 「御霊前」または「御仏前(四十九日以降)」 |
| 供える花 | しきみや季節の花を使用 | 日蓮正宗指定の荘厳具のみ |
このように、日蓮宗は比較的開かれた形式で参列者も参加しやすいのに対し、日蓮正宗は信徒のみに絞った厳格な葬儀運営を行う点が大きな違いです。
創価学会は、日蓮正宗の外郭団体として1928年に発足した宗派です。しかし、御本尊の教義解釈の相違から、1991年に日蓮正宗から破門され、現在は独立した新興宗教法人となっています。
日蓮宗の葬儀は、約1時間~1時間半ほどで執り行われます。日蓮宗特有の仏具や音具が用いられ、導師と参列者が一体となる参加型の要素が強いのが特徴です。
ここからは、一般的な式次第を簡単にご紹介します。
葬儀の開始にあたり、声明曲である道場偈を流して諸仏や諸尊を迎え入れます。
「起(たち)」「居(すわり)」の動作を組み合わせ、仏・法・僧の三宝に対して礼拝を行います。起居礼(ききょらい)とも呼ばれます。
久遠実乗の本師釈迦牟尼仏や四菩薩、宗祖・日蓮聖人などをお迎えし、場を仏法の境地へと清めます。
開経偈を唱えた後、法華経の読誦や題目の唱和が行われます。節目では妙鉢や木柾による咒讃鐃鈸で、厳粛に区切りを付けるのが特徴です。
棺の前で導師が焼香を行います。その後、導師が棺のふたに軽く杖などを当て、開棺の偈を唱えながらふたを外し、故人への最後のお別れをします。
導師が故人に語りかけるように法語を唱え、払子(ほっす)などを用いて仏の世界へ導きます。
参列者一同で焼香を行います。続いて祖師の教えを説く祖訓を拝聴し、再び「南無妙法蓮華経」の唱題を行います。
宝塔偈を唱え、法華経の功徳を故人へ授けることで成仏を祈念します。
四誓では、人々を救う誓いの言葉を唱え、仏・法・僧の三宝への帰依を誓う三帰を行います。その後、故人を仏道に送る奉送の儀式を行います。
導師が閉式の辞を述べ、参列者一同で合掌の後、葬儀は終了となります。
以上が、日蓮宗の葬儀における一般的な式次第です。参列の際は、一連の流れをイメージしておくと落ち着いて式に臨めるでしょう。
日蓮宗の葬儀では、故人供養の中心に据えられる仏具と、法要を彩る音具が欠かせません。これらを用いることで、式全体に厳粛さと一体感が生まれ、導師と参列者がともに故人の成仏を祈念する場となります。
ここでは代表的な仏具や音具を紹介します。
曼荼羅本尊は、祭壇の最奥に掲げられる掛軸で、中央には「南無妙法蓮華経」が力強く書かれています。その周囲を十界曼荼羅などが取り囲むことで、故人と参列者が題目を通じて仏と一体になる世界観を示し、式場全体を法華経の境地へ導きます。
木柾は、長めの木製棒を杖木状に加工した打楽器です。読経や唱題の際、リズムを刻むように打ち鳴らすことで、声を合わせるタイミングを示し、一同の心をひとつにまとめます。金属音に比べ柔らかい響きが、厳かでありながら温かみのある空気を演出します。
妙鉢は、小ぶりの金属製鉢を木槌で打ち鳴らす音具です。読経や唱題の区切りや節目をはっきり示すために用いられ、高く澄んだ音色が法要の厳粛さを強調します。同時に、参列者の心を静め、故人への祈りを新たに引き締める役割も果たします。
ここでは、日蓮宗の葬儀に参列する際に知っておきたい4つのマナーをご紹介します。
日蓮宗で正式に用いられる数珠は「勤行数珠」と呼ばれるものです。主玉108個に親玉や天玉、数取玉などを配して二重にした独特の仕様になっています。
房の本数や位置は釈迦如来・多宝如来を象徴し、数取玉を動かして唱題の回数を数えることができ、黒壇や紫壇など堅牢な素材が好まれています。
ただし、すでに他宗派の数珠をお持ちの場合は、お手持ちの数珠を使用しても差し支えありません。
日蓮宗の焼香では、まず数珠を左手にかけ、両手を合掌して軽く一礼します。次に右手の親指と人差し指で抹香をひとつまみ取り、額の高さまで掲げて心を込める「押しを頂く」動作を行ってから、香炉にそっと振りかけます。
僧侶(導師)は儀式の際に焼香を3回行うのが正式ですが、一般の参列者の焼香は1回、または状況に応じて2〜3回行います。焼香を終えたら、再び合掌一礼してから静かに席へ戻ります。
回数は地域や寺院によって違いがあるため、葬儀スタッフの指示に従うといいでしょう。
日蓮宗の香典の表書きは、四十九日以前の法要では「御霊前」または「御香典」、四十九日以降が「御仏前」または「御香典」とします。
詳しくは、以下の関連記事もご覧ください。
日蓮宗の葬儀でも、参列者の服装のマナーは一般的な仏式葬儀と大きな違いはありません。男性はブラックフォーマルの喪服、女性はブラックフォーマルのスーツやワンピースが基本です。
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
日蓮宗では、亡くなった方に「戒名」ではなく「法号(ほうごう)」を授与します。法号は必ず「日」の文字を含み「仏の弟子として新たに生まれ変わる」ことを象徴します。
たとえば「日○○居士」「日○○大姉」といった形で、性別や社会的立場に応じた位号を付けます。授与された法号は位牌や納骨壇に記され、故人が仏の世界へ歩み出した証として大切に扱われます。
お布施は読経料や法号授与料に加え、僧侶の交通費をまかなう「お車代」、通夜振る舞いを辞退した際の「御膳料」なども含める場合もあります。
一般的なお布施の相場は20万~50万円前後ですが、寺院の格式や地域差、故人とのご縁によっても異なります。そのため、事前に葬儀社や担当の寺院とお布施の額について相談しておくといいでしょう。
日蓮宗の祭壇や家庭の仏壇の飾り方には、厳格なルールはなく「法華経」の世界観を表す空間として比較的自由にお飾りいただけます。中心に据える本尊や十界曼荼羅を軸に、季節の花やしきみを添えつつ、脇侍(きょうじ)として鬼子母神・大黒天を配置するのが一般的です。
本尊は十界曼荼羅の掛軸が基本ですが、釈迦牟尼仏や三宝尊(仏・法・僧の三尊)の掛軸を用いることもあります。掛軸は祭壇の最奥、目線の高さに掲げ、題目唱和や日々のお勤めの中心とします。
仏壇の前段には花立や燭台、香炉を並べます。供花には厳密な決まりはなく、白菊や季節の生花を自由に使ってかまいません。しきみ(樒)は毒性をもつ常緑樹として邪気を祓う力があるとされ、祭壇や仏壇の隅に一対置くことで「永遠の命」と清浄を示します。
さらに、数珠やお経本、日々のお供え(ご飯・水・果物など)を壇上に整え、ほこりを払って清潔に保つことで、いつでもお参りできる状態を心がけましょう。
日蓮宗は「法華経」を唯一の教典とし「南無妙法蓮華経」の唱題による現世利益と心の救済を重視する宗派です。
日蓮宗の葬儀では、参列者も一体となって題目を唱える「題目読誦」や妙鉢・木柾による音具演出、しきみ飾りなど独自の儀礼が行われます。事前に、日蓮宗の基本的な教えや葬儀の流れ、数珠や焼香、香典表書きなどのマナーを理解しておくことで、落ち着いて参列できるでしょう。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。