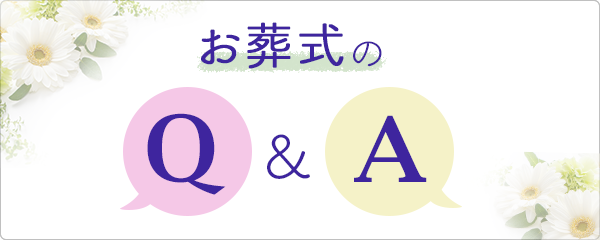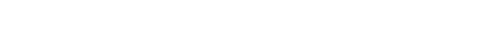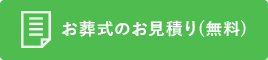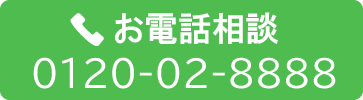通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/10/15
更新日:2025/10/15

 目次
目次副葬品(ふくそうひん)とは、故人の愛用品や思い出の品を棺に添えて納める品のことです。最期のお別れに、故人への感謝の気持ちを込めるとともに、旅立つ方への手向けの意味を持つ大切な習わしとされています。
ただし、いざ副葬品を準備しようと思っても「どのようなものを入れればよいのか」「棺に入れてはいけないものはあるのか」「入れるタイミングはいつなのか」といった点で迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、副葬品の意味や役割、棺に入れるタイミング、よく選ばれる品目の具体例、棺に入れてはいけないもの、副葬品の注意点を詳しく解説します。大切な方を想い、穏やかに旅立ちを見送るための準備として、ぜひ参考にしてください。
● 副葬品の意味を知りたい人
● 副葬品の選び方を知りたい人
● 副葬品として棺に入れてよいものを知りたい人
● 副葬品として棺に入れてはいけないものを知りたい人
副葬品とは、葬送の際に故人と共に添えて納める品の総称です。「副葬」は「副(そ)える」と「葬る」を組み合わせた言葉で、故人を葬る際に添えて納めるという意味があります。
副葬の風習は、古代から存在しています。日本では古墳時代の遺跡からも、刀剣や鏡、玉、土器など多くの副葬品が発見されています。これらの品々は、来世で使うための生活用品としての意味に加え「故人の身分や権威を示す象徴」としての役割も果たしていました。
その後、仏教の伝来や葬儀形態の変化などから、日本は土葬から火葬へと主流が移りました。この変化により、副葬品は「故人とともに火葬するもの」という意味合いが中心となり、同時に「火葬炉を傷めないこと」「遺骨を汚損しないこと」といった実務面での配慮も求められるようになりました。
現在の副葬品は、故人の冥福を祈り、故人らしさを偲ぶ「象徴的な役割」が中心となっており、手紙や生花、思い出の写真、身につけていた布製品などがよく選ばれます。入れ方や量の配慮、可否の判断は葬儀社や火葬場の基準に従うのが基本です。
関連記事:
知っておきたい火葬のすべて【意義・流れ・手続き・マナーをわかりやすく解説】
副葬品を納めるタイミングは、主に2つあります。
・納棺の儀式が行われる際
・出棺の直前
それぞれの場面で、納められる品や注意点に違いがあります。詳しく見ていきましょう。
一般的に副葬品を納める最初のタイミングは、納棺の儀式(納棺の儀)です。納棺の儀は、故人の体を清め、旅立ちの装いを整える大切な儀式であり、ご遺族が故人との別れをゆっくりと受け止める時間でもあります。
納棺の儀では、故人が生前に大切にしていたものや愛用品を少しずつ棺の中へ納めます。代表的なものとして、衣類、手紙、趣味の品、生花などが挙げられます。入れる品の量は控えめにし、燃やしても支障のない素材であることを確認しておくと安心です。
納棺の儀の際には、葬儀社のスタッフが火葬場の規定に沿って副葬品を確認するのが一般的です。金属やガラス、プラスチックなど燃えにくい素材は避け、写真や布製の品などを選ぶのが望ましいでしょう。
副葬品を入れるもう1つのタイミングは、出棺の直前です。出棺の前には、ご遺族や近親者が順に棺のそばへ進み、故人のまわりに花や手紙などを手向けます。これは「お別れ花」とも呼ばれており、故人への感謝や祈りを込めて納める最後の機会となります。
出棺直前に納める副葬品では「気持ちを表す」ことが重視されます。花を中心に、手紙や小さな布製品などが多く選ばれます。燃えにくいものや破裂・変形の恐れがあるものは避けましょう。
副葬品には、故人への想いを形にするさまざまな品が選ばれます。ここでは、副葬品として選ばれるものや具体的な品目を紹介します。
故人に伝えたい言葉や感謝の気持ちを込めた「手紙」などが該当します。直接伝えられなかった想いを文字にして棺へ納めることで、心の区切りをつけられる方も多くいらっしゃいます。
故人が生前に好んでいた食べ物や嗜好品なども、副葬品として選ばれます。たとえば、好きだったお菓子やタバコなど、故人の人柄や日常を思い出させる品が中心です。
ただし、燃えにくい素材や水分の多い食品は避けましょう。
その人らしさを表す品も副葬品としてよく選ばれます。職業や趣味にちなんだ小物、愛用していたアクセサリー、帽子やスカーフなど、見る人が「その方らしい」と感じられる品などです。
故人が生前に「一緒に納めてほしい」と伝えていた品を副葬品に選ぶこともあります。
お気に入りの服や思い出の写真、趣味の作品など、その人の希望を尊重して納めることが大切です。内容や素材に不安がある場合は、事前に葬儀社へ相談しましょう。
| 品目 | 解説 |
|---|---|
| 花 | もっとも一般的な副葬品。色や種類に決まりはなく、白い花を中心に、故人の好きだった花を添えることもあります。 |
| 手紙 | 家族や友人からの感謝や想いを伝える品。封筒に入れず、便箋1枚程度が適しています。 |
| 服飾品 | ハンカチやスカーフなど布製のものが中心。スーツや着物など厚手の衣類は避けましょう。 |
| 写真 | 故人の笑顔を偲ぶ品として人気ですが、生きている方が写っている写真は避けるのが一般的です。 |
| 千羽鶴 | 健康や平穏を願って折られたもので、祈りや感謝の象徴として添えられます。 |
| 御朱印帳 | 寺社巡りが好きだった方に選ばれることが多く、人生の歩みを象徴する副葬品として納められます。 |
副葬品は、故人らしさを表す大切な品であると同時に、残された人の想いを託す象徴でもあります。燃えやすさや分量などに注意しながら、心を込めて選びましょう。
棺に入れられる副葬品は、基本的に燃やすことができるものが中心です。火葬の際に安全に燃焼し、火葬炉やご遺骨に影響を与えない素材であるかどうかが判断の基準となります。
代表的なものとしては、紙・布・木・生花などの可燃性素材でつくられた品が挙げられます。手紙や写真、ハンカチ、タオル、スカーフ、折り紙、生花などは問題なく納めることができます。衣類の場合は、薄手のシャツやハンカチなど軽い布製品に限るのが一般的です。
また、棺に入れる量にも注意が必要です。可燃性であっても、副葬品を多く入れすぎると火葬時間が長引いたり、燃え残りが出たりする原因となります。あくまで「故人を象徴する品を少量添える」という意識で選びましょう。
食品類を納めたい場合は、紙に包む、一口大にするなどの工夫をすると安心です。水分や油分の多いものは、火葬中に破裂したり煙が出たりする恐れがあるため避けましょう。
ただし、火葬場によっては可否の判断基準や取り扱いが異なる場合があります。地域や施設によっては、同じ素材でも持ち込みを制限していることもあります。迷う場合は、葬儀社のスタッフに相談し、事前に火葬場の規定を確認しておくと安心です。
火葬の際には、火葬炉の安全性を守り、遺骨をきれいに残すことが大切です。
燃えにくいものや破裂・変形の恐れがあるものを入れると、火葬炉の損傷や遺骨の汚損につながる場合があります。以下のような品は基本的に避けましょう。
金属製品やガラス製品は、高温でも燃えずに残ってしまうことがあります。そのため、炉の損傷や遺骨への付着・変色の原因になるため避けましょう。
プラスチックやビニール製品は、燃焼時に有害なガスや煙を発生させるおそれがあります。CDやDVD、ケース類、ビニール袋などは棺に入れないようにしましょう。
厚みのある本やアルバムは燃え切らず、灰の塊が残る原因となります。納めたい場合は、表紙だけをコピーする、写真のみをアルバムから出して入れるなどの方法を検討しましょう。
果物など水分を多く含むものは、加熱で破裂したり、煙や臭いの原因になることがあります。副葬品としては避けるか、入れる場合は葬儀社に相談の上、ごく少量にとどめましょう。
火葬済みの遺骨や他の方の遺骨を棺に入れることは避けましょう。火葬の工程で混ざる可能性があり、実務・衛生上の観点からも望ましくありません。
厚手の衣類や芯に金属・化学繊維を含む着物やスーツは、燃えにくく、火葬時間が長引く原因になります。衣類を入れる場合は、布製の薄手のものを選びましょう。
革製品は燃えにくく臭気が残ることがあります。また、肉や魚など動物性のものは、殺生を連想させるという理由から避けるのが一般的です。
存命の方が写った写真を副葬品として火葬すると「一緒に連れて行かれる」と解釈される場合もあるため、縁起を気にする方も多くいます。存命の方が写っている写真は避けるか、本人の了承を得て納めましょう。
眼鏡や補聴器は、金属や樹脂を含むため、燃えにくく変形や破裂の原因になります。故人の象徴として供養したい場合は、別の形で供養するのがおすすめです。
ペースメーカーは、火葬時の高熱で爆発するおそれがあり、非常に危険です。必ず事前に取り外しの有無を医療機関や葬儀社に確認してください。
紙幣や硬貨は、通貨損傷等取締法などの法律で焼却が禁じられています。そのため、法的にも副葬品として納めることはできません。
カーボン素材は高温に強く燃焼しにくいため、火葬炉内の温度バランスを崩すおそれがあります。カーボン製のゴルフクラブや筆記具などは、故人が生前愛用していたものであっても、棺に入れるのは避けましょう。
スプレー缶やライター、電池などは、火葬時の高熱で爆発するおそれがあり非常に危険です。
とくに近年では、リチウムイオン電池を内蔵した小型家電や電子機器(スマートフォン、腕時計、電子タバコ、補聴器など)が広く普及しています。そのため「故人が愛用していたから棺に入れてあげたい」と考える方も少なくありません。
しかし、リチウムイオン電池は高温下で内部にガスが発生し、膨張や発火、爆発を起こす危険性があります。実際に火葬場で事故につながった事例も報告されているため、こうした製品は必ず取り外し、棺には入れないようにしましょう。
缶や瓶などに入った飲み物は、火葬時の高温により内部の水分が膨張し、破裂や爆発の原因となるおそれがあるため避けましょう。故人が好んでいた飲み物を手向けたい場合は、火葬後の祭壇やお供えとして用意するのが望ましいとされています。
火葬場の規定で入れられない副葬品がある場合でも、故人への想いを形に残す方法はいくつかあります。無理に棺へ納めるのではなく、安全で穏やかな形で気持ちを伝えることが大切です。
どうしても副葬品として添えたい品がある場合は、火葬直前まで棺の上に置いておく方法があります。
出棺前の「お別れの時間」に棺の上へそっと置き、最後のお見送りの際に故人のそばにあった形でお別れをすることができます。火葬の直前に葬儀社のスタッフが回収するため、安全面でも安心です。
故人の思い出の品や入れられない副葬品は、写真に残して棺に納めるのも1つの方法です。
実物を入れなくても、写真として棺に納めることで「一緒に旅立つ」という象徴的な意味を持たせることができます。また、形見や貴重品などを残したい場合にも適した方法です。
どうしても故人と一緒に残したい小さな品は、火葬後に骨壺へ納めることも可能です。
火葬が終わった後、収骨の際に葬儀社や火葬場のスタッフへ相談し、支障がなければ一緒に納めてもらえます。ただし、火葬場によっては対応できない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
副葬品は、故人への感謝や祈りを込めて旅立ちに添える大切な品です。古くから受け継がれてきたこの習わしには、故人が安らかに過ごせるようにという願いと、遺された人が心の整理をつける意味が込められています。
一方で、火葬が主流となった現代では、入れられる品に制限があるなど、実務的な注意点も多くあります。「どんなものなら安全に納められるか」「避けるべきものは何か」を理解しておくことで、故人を想う気持ちを安全かつ丁寧に形にすることができます。
無理に多くの品を納めようとせず、故人らしさを感じられる象徴的な品を少し添えるだけでも、心を込めたお見送りになります。迷うことがあれば、葬儀社へ相談しながら、故人とご家族にとって最も穏やかな形を選びましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。