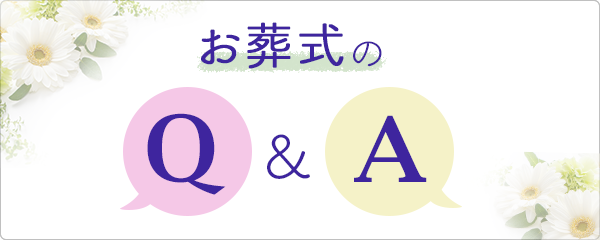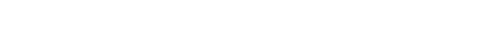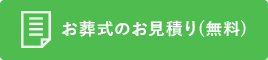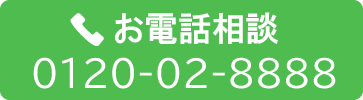通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/09/25
更新日:2025/09/25

 目次
目次● 家族葬に香典を持参するか迷っている方
● 香典の代わりになる品物を知りたい方
● 香典返しを考えている方
近年、葬儀形式が多様化する中で、家族や親しい親族のみで故人を見送る「家族葬」を選択する方が増えています。しかし、従来の一般葬とは異なる葬義形式であることから、家族葬における香典の役割やマナーについて、迷われる方も少なくないようです。この記事では、家族葬における香典やその代わりとなる品物、お返しまで、トータルに解説いたします。
家族葬は、故人の家族や親族、ごく親しい友人のみで営まれる葬儀形式です。一般的な葬儀と比べて参列者数が少なく、故人とのお別れの時間をゆっくり過ごせるという特徴があります。また、関係性の深い方のみで行われることから、葬儀の自由度も高く、より親密な雰囲気の中で故人を偲ぶことができます。
ただし、参列者の制限のない一般葬と異なり、家族葬では参列者を限定するため、故人と親交のあった方々が参列できずに不満を感じてしまう可能性がある他、後日弔問に訪れる方が増えてご遺族に負担がかかることもあります。また、身内で行うため香典収入は少なく、ご遺族の経済的な負担が重くなるケースも少なくありません。家族葬を検討する際は、これらの点を考慮した上で、故人の生前の意向や家族の状況を踏まえて慎重に決めることが大切です。
香典は、故人への弔意を表すとともに、ご遺族への経済的支援という重要な意味を持ちます。葬儀には多額の費用がかかるため、参列者が金銭を持参して葬儀費用の一部を助けるという相互扶助の精神に基づいた慣習です。仏式に限らず、日本で行われるさまざまな宗教・宗派による葬儀においても香典を包んで持参することが一般的とされており、家族葬だからといって香典が不要というわけではありません。
しかし、家族葬では、ご遺族が「香典辞退」を選択するケースも増えています。これは、香典返しの手間を省きたい、経済的な負担を参列者にかけたくない、シンプルな葬儀にしたいと考える方が増加傾向にあるためです。また、家族や近親者のみで故人を見送る場合、家族間で香典という形式的なやり取りを避けたいという意味合いもあります。
家族葬の場合も、香典の相場は一般葬と同様に考えます。金額の相場は故人との関係性によって異なりますので、以下の表を参考にされてください。
| 故人との関係性 | 金額相場 |
|---|---|
| 両親 | 5~10万円 |
| きょうだい | 3~5万円 |
| 祖父母 | 3~5万円 |
| おじ・おば | 1~3万円 |
| 友人・知人 | 5千~1万円 |
家族葬に参列する際も、香典を包むことが基本です。しかし、前述したように、家族葬では香典辞退をされるケースも多いことから、家族葬に香典を持参するかどうか悩んでしまう方も少なくありません。前提として、香典はご遺族の意向を尊重することが最も重要だと理解しておくとよいでしょう。その上で、想定されるケースごとに注意したいポイントを以下に解説します。
訃報を受け取ったら、まずは香典に関する記載がないか確認しましょう。ご遺族から「香典辞退」の意向が示されている場合は、その意向を尊重することが重要です。無理に香典を渡そうとすることは、かえってご遺族の負担となってしまうので避けましょう。
香典に対するご遺族の意向が不明な場合は、念のため香典を準備しておくことをおすすめします。香典を辞退されていない場合は通常通り受付でお渡しすればよく、葬儀場で香典辞退であることを知った場合はそのまま持ち帰ります。あらかじめ用意しておけば、どちらの状況にも対応できるので安心です。
故人やご遺族との関係性、ご自身の社会的な立場などから、相場とされる金額よりも多めに渡したいと考えることがあるかもしれません。その場合も、まずはご遺族の負担を考慮することが大切です。香典返しの負担や、他の参列者との金額のバランスを考慮し、適切な範囲内にとどめるよう心がけましょう。
そもそも家族葬への参列を依頼されていない場合、香典を持参することは控えるべきです。これは、ご遺族が家族のみで静かに故人を見送りたいという思いを尊重するためです。このような場合は、後日改めて弔問に伺うか、お悔やみの手紙を送るといった方法で弔意を表します。その際も、ご遺族の負担にならないよう気をつけましょう。
基本的にご遺族が香典を辞退されている場合は、持参しないことがマナーです。どうしても何らかの方法で弔意を表したいという場合は、香典に代わる品物を贈るのも一つの方法です。香典の代替品として適した品物は宗教や宗派によって異なります。宗教の考え方にそぐわない品物を贈ることは、失礼にあたるため十分に注意しましょう。
仏教において、故人の供養に用いられる5つの基本的な供物のことを「五供(ごく・ごくう)」といいます。五供には「香」「花」「灯明」「飲食」「浄水」があり、それぞれに意味が込められています。五供の意味と対応するお供え物を以下の表にまとめました。
| 香(こう) | お香、線香 | 香りによって、空間を清め、心を鎮める |
|---|---|---|
| 灯明(とうみょう) | ろうそく | 仏様の智慧と慈悲を象徴する光で闇を照らす |
| 花(はな) | 生花 | 美しい花で故人を偲び、弔意を表す |
| 浄水(じょうすい) | 清らかな水 | 故人の喉の乾きを癒す(宗派により供えないことも) |
| 飲食(おんじき) | 果物、菓子などの食べ物 | 故人への感謝と供養の気持ちを表す |
仏式では、「五供」に基づくお供えものを用意するとよいでしょう。ただし、宗派によって考え方が異なるため、事前に確認が必要です。また、神道やキリスト教など仏教以外の宗教ではお供物に対する考え方が異なり、適した品物も異なります。代表的な品物の例を以下にまとめました。
線香やろうそくは、仏式葬儀では一般的なお供え物として重宝されますが、神道やキリスト教など仏教以外の宗教には適していません。線香には、香りや形状にもさまざまな種類があります。以下に、お供え物としてふさわしい代表的な香りの特徴をご紹介します。
白檀(びゃくだん)
・上品で甘く、爽やかな香り
・リラックス効果が高く、アロマテラピーにも用いられる
沈香(じんこう)
・高級香木で、深みのある少しスパイシーな香り
・心を落ち着かせる効果があるとされる
伽羅(きゃら)
・沈香の中でも最高級の香木
・特別な日にふさわしい高級感のある香り
お花は、宗教・宗派を選ばずに受け入れられる贈り物といえます。ただし、宗教によって適した花の種類が異なるため注意が必要です。
| 宗教 | 花の種類 |
|---|---|
| 仏教 | 菊、ユリ、胡蝶蘭など |
| 神道 | 白い花(菊、ユリ、カーネーションなど) |
| キリスト教 | 白い花(ユリ、カラーなど) |
神道では「清浄」を重視することから、酒や塩といった「清め」の意味を持つ供物が適しています。一方、仏教の戒律ではお酒を飲むことを禁じられているため、アルコール類をお供えすべきではないとされているため避けましょう。
| 宗教 | 供物の種類 |
|---|---|
| 仏教 | ・水やお茶が一般的 ・アルコール類はNG (宗派によっては水やお茶を供えないことも) |
| 神道 | お酒を供えることができる(日本酒など) |
季節の果物や、和菓子、洋菓子などが適しています。すぐに食べずにしばらくお供えしておくことがほとんどなので、常温保存が可能で日持ちのする食べ物を選ぶとよいでしょう。
仏教では、殺生を連想させる肉や魚、卵や乳製品が使われたもの、においや刺激が強いものはタブーとされています。また、キリスト教の葬儀で食べ物・飲み物を贈ることは避けましょう。
香典の代わりに品物を贈る場合は、金額や贈り方にも配慮する必要があります。あまり高額すぎると、ご遺族の香典返しの負担が大きくなる可能性があるため、負担にならない範囲のものを選ぶことが大切です。相場としては、供花は2〜3万円、線香や果物・お菓子は5千〜1万5千円程度とされています。反対に、相場に比べて価格が低すぎる品物を選ぶのもマナー違反となるので注意しましょう。続いて、家族葬で品物を贈る際の基本的なマナーについて解説します。
品物を贈る前に、ご遺族が供物を受け取る意向があるか確認します。特に家族葬では、ご遺族の意向を尊重することが重要です。
宗教や宗派によって香典の代替品に適さない物があります。事前に確認し、適切な品物を選びましょう。
生花以外は、なるべく日持ちする品物を選びます。遺族が慌てて消費する必要がないよう配慮することが大切です。
品物にはかけ紙(のし紙)をつけましょう。かけ紙は、宗教・宗派に応じた表書きを記載します。
宗教・宗派によって、ふさわしい表書きは異なります。マナー違反にならないよう事前に確認しましょう。「御供」または「御供物」とすると一般的に用いることができます。
葬儀当日に持参するか、後日自宅に郵送するかは状況に応じて判断します。遺族の負担を考慮し、適切なタイミングを選びましょう。
ここでは、家族葬で品物を渡す際の基本的なマナーをご紹介します。
葬儀に参列する際は、受付でお供え物を渡すことが一般的です。受付係に「この度はお悔やみ申し上げます」とお悔やみの言葉を添えて手渡しします。その際、品物の内容を簡潔に伝えると丁寧でしょう。
紙袋のまま品物を渡すのはマナー違反にあたります。持参した品物は、必ず紙袋から取り出し、かけ紙の表書きの文字が相手に読める向きで渡しましょう。お供え物を入れた紙袋は渡さずに持ち帰るのが基本ですが、ご遺族が持ち帰る際に不便になる場合などは「よろしければお使いください」と伝えてお渡しするとよいでしょう。
お通夜や葬儀への参列が難しい場合は、手紙を添えて後日郵送します。四十九日法要の際にお供物として贈ったり、喪中見舞いで品物を贈るのもよいでしょう。手紙にはお悔やみの気持ちやご遺族への労りの言葉を簡潔に記すように心がけます。
家族葬で、喪主や遺族として参列者から香典や香典に代わる品物をいただいた場合、お返し(香典返し)をどうするべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。供花や供物などの品物を受け取った場合も、香典同様お返しの品を用意する必要があります。
特に家族葬は参列者が限られているため一人ひとりとの関係性が深く、より心のこもったお返しを心がけたいものです。適切な金額の目安やお渡しするタイミング、品物の選び方にはマナーがあります。ここでは、家族葬におけるお返しの基本的な考え方から具体的な方法まで詳しく解説いたします。
いただいた香典や品物の半額から3分の1までの金額を目安とします。これは「半返し」という慣習に基づいており、感謝の気持ちを表すとともに、高額すぎるものを贈って相手に負担をかけないという配慮でもあります。
以前は、四十九日の法要を済ませた忌明け後に香典返しをお渡しすることが一般的でした。しかし、近年は、あらかじめ返礼品を用意し、葬儀当日にお渡しする「即日返し」が主流となっています。ただし、相場よりも高額の香典や品物をいただいた場合は、後日追加で返礼品をお送りするのがマナーです。
あらかじめ返礼品を用意しておき、葬儀当日に香典や品物をいただいた方にその場でお渡しする方法です。参列者が少ない家族葬の場合、一人ひとりに心を込めてお渡しすることができます。
葬儀を済ませてから、後日お返しの品を郵送や持参でお渡しする方法です。仏式の場合、四十九日法要が明けてから1か月以内に行うことが一般的ですが、宗派によって異なるため確認が必要です。
香典返しには、「消え物」と呼ばれる消耗品を選ばれる方が多いようです。食べたり使ったりしてなくなる物は、相手の負担にならず、「不祝儀を残さないように」という意味も込められています。具体的には、洗剤やタオルなどの日用品、海苔やお茶、お菓子といった食べ物が好まれるようです。また、最近は受け取った方が自分の好みに合わせて選べるカタログギフトも人気が高まっています。贈る側にとっても、相手の年齢や性別、好みを問わず、品物を選ぶ負担を軽減できるというメリットがあります。
・ただし、ご遺族が香典辞退の意向を示している場合は持参しないのがマナー
・家族葬の場合も、香典の金額相場は一般葬と同様に考える
・香典に対するご遺族の意向がわからない場合は、念のため用意しておくと安心
・仏教におけるお供え物の基本は「五供」。線香やろうそくは仏教以外では贈らない
・神道ではお酒を贈ることができるが、仏教ではアルコール類を避けることが原則
・キリスト教では、白ユリなどの白い花を供花として贈ることが一般的
・あまり高額すぎる物は、香典返しの負担が重くなる可能性があるため避ける
・金額の目安は、供花は2〜3万円、線香や果物・お菓子は5千〜1万5千円程度
・喪主側でお返しを贈る場合は、品物の半額から3分の1までの金額を目安とする</p
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。