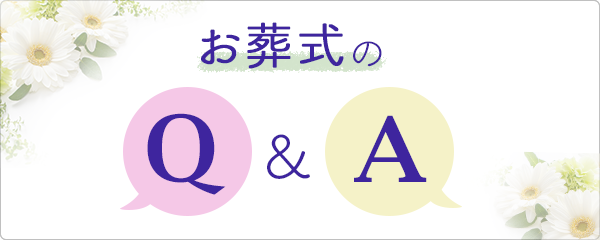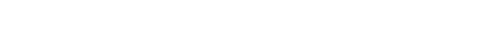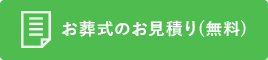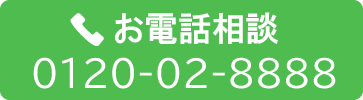通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/08/29
更新日:2025/08/29
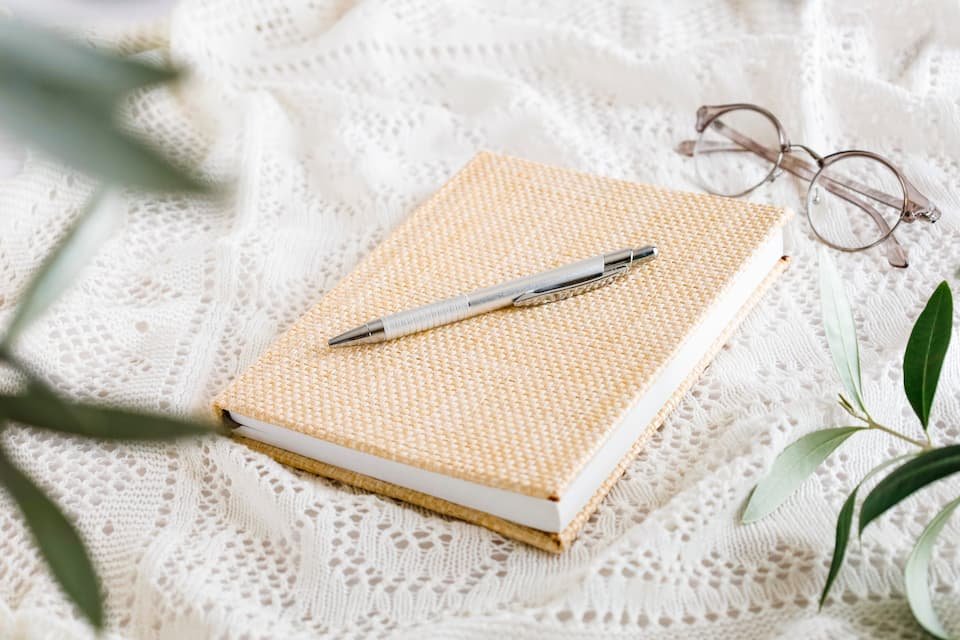
 目次
目次葬儀は、時に予期せぬタイミングで訪れることも多く、その準備をすべてご遺族が担うとなると大きな負担となります。そのため、近年では元気なうちからご自身の希望を整理し、葬儀の準備しておく「終活」が注目されています。
本記事では、ご自身ができる葬儀準備の進め方や、エンディングノートの活用法について解説します。大切な人に負担をかけず、自分らしい最期を迎えるための参考にしてください。
● 葬儀準備(終活)でやるべきことを知りたい人
● 葬儀形式ごとの費用相場を知りたい人
● 葬儀資金の準備方法について知りたい人
● 葬儀社の選び方について知りたい人
● エンディングノートについて知りたい人
葬儀は人生の最期を飾る大切な儀式ですが、実際には訃報に直面したご遺族が、短期間で葬儀に関して数多くの判断を迫られます。葬儀の形式や規模、会場の手配や費用の準備など、十分に検討できないまま進めてしまうと、ご遺族に後悔が残ることも少なくありません。
そこで近年注目されているのが、生前のうちにご自身の希望を整理しておく「終活」です。たとえば「家族葬で静かに見送ってほしい」「菩提寺に依頼してほしい」「納骨は樹木葬を希望する」といった意思を残しておけば、ご遺族は迷わず準備を進められます。
また、費用の目安を把握し、あらかじめ備えておくことで経済的な負担も軽減できます。こうした取り組みは残された方への思いやりであり、自分らしい最期を形にするための選択肢のひとつといえるでしょう。
そこでここからは、終活に関する基礎知識や具体的な準備のポイントを幅広く紹介していきます。
葬儀準備の第一歩は、ご自身の希望を明確にしておくことです。どのような形式で執り行いたいのか、誰に参列してほしいのか、宗教や納骨の方法など、事前に考えておく項目は数多くあります。
ここでは、葬儀形式や規模、宗教・宗派の確認から納骨方法まで、具体的に整理しておくべき内容について解説します。
葬儀を準備するうえで、まず検討しておきたいのが「葬儀の形式」です。葬儀の形式には一般葬・家族葬・一日葬・直葬などがありますが、それぞれ規模や参列範囲、費用が大きく変わります。
親族や友人、会社関係者など幅広い参列者を招く最も一般的な形式で、社会的なお付き合いを重視したい場合に適しています。
近親者を中心に小規模で行うスタイルで、故人との時間をゆっくり持ちたい方に選ばれています。
通夜を省き告別式のみを行う方法で、参列や準備の負担を軽くしたい場合に向いています。
通夜や告別式を省略し火葬のみを行う形で、費用を抑えたい方や儀礼を簡素にしたい方に選ばれる傾向があります。
こうした形式の違いを理解し、ご自身の希望や家族の考えに合った形をあらかじめ決めておくことが、後悔のない葬儀につながります。
葬儀形式ごとの費用に関しては「葬儀形式ごとの費用目安」にて後述します。
葬儀の準備では、形式とあわせて「誰に参列していただきたいか」を考えておくことも大切です。招く範囲によって会場の広さや必要な費用、当日の進行体制が大きく変わります。
親族だけで行うのか、親しい友人や近隣まで参列いただくのか、さらに会社関係者や地域の方々にまで声をかけるのかによって、準備の内容は大きく異なります。参列者の人数が増えるほど会場や食事、返礼品などの用意も必要になり、ご遺族の負担も大きくなります。
一方で、限られた人だけを招く小規模な葬儀は、落ち着いた雰囲気の中で故人と向き合える反面、なかには「知らせてもらえなかった」と感じる方が出る可能性もあります。そのため、参列範囲はご自身の意向と同時に、ご家族の立場や人間関係も踏まえて決めておくことが重要です。
あらかじめ参列範囲を明確にしておけば、ご遺族は判断に迷うことなく準備を進められ、故人の意向に沿った形で葬儀を整えることができるでしょう。
葬儀をどのように執り行うかを決めるうえで、宗教や宗派の確認は欠かせません。仏教・神道・キリスト教など、宗教によって葬儀の儀礼や進め方は大きく異なります。また、同じ仏教でも宗派ごとに読経や作法、必要なお道具が変わるため、事前にしっかりと整理しておく必要があります。
特に菩提寺がある場合は、その寺院に依頼するのが基本となります。葬儀を依頼する際には、僧侶の手配やお布施の金額、会場の利用可否などについても確認しておくと安心です。一方で菩提寺がない場合や無宗教での葬儀を希望する場合には、葬儀社に相談しながら宗教者を紹介してもらう、あるいは無宗教形式の進行を検討するなど、希望に沿った方法を準備しておくことが大切です。
葬儀の準備では、形式や規模に加えて「どのような内容にしたいか」を具体的に考えておくことも大切です。たとえば喪主や司会を誰にお願いしたいか、葬儀の場所を自宅・式場・寺院のどこにするか、といった点は早めに意思を残しておくとご遺族が迷わず準備を進められます。
また、音楽や映像の演出を希望する、祭壇を花で彩ってほしいなど、故人らしさを反映できる要望を記しておくのも一案です。さらに、弔電や供花の受け方、会葬御礼品の有無など、細かい部分も含めて考えておくと、当日の流れがより明確になるでしょう。
こうした内容を整理しておくことは、ご遺族の負担を軽減するだけでなく、自分らしい最期を実現することにつながります。
葬儀で使用する遺影写真は、式の雰囲気や参列者の記憶に長く残る大切な要素です。しかし実際には、急な準備の中でご遺族が慌てて選ばざるを得ず「もっと良い写真を残しておけばよかった」と悔やまれることも少なくありません。
そのため、生前のうちに遺影用に適した写真を準備しておくことが望ましいでしょう。
遺影には、正面から写っていて表情が自然で明るく、服装や背景が落ち着いている写真が選ばれやすい傾向にあります。旅行や行事などで撮影したお気に入りの一枚を候補として残しておくのもおすすめです。最近では、専門の写真館で「生前撮影」を行い、遺影用に整えた写真を準備しておく方も増えています。
葬儀後の流れとして欠かせないのが納骨です。一般的には、仏式の場合は四十九日法要に合わせて納骨を行うことが多いですが、宗派や地域によって時期は異なります。あらかじめ希望を明確にしておくことで、ご遺族が迷わずに準備を進められます。
納骨の方法には、従来のお墓に埋葬するだけでなく、近年では樹木葬や納骨堂、永代供養墓、散骨など多様な選択肢があります。
お墓を新たに建立するのか、既存の墓地を利用するのか、または自然葬を希望するのかによって費用や手続きも変わるため、事前に納骨方法についても意思を残しておくことが大切です。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀の生前予約「アンシア」をご用意しています。入会金・年会費無料にて、ご希望の葬儀内容を事前に登録できるため、ご家族の負担を軽減しながら安心して備えることができます。
葬儀の準備を考えるうえで、費用の目安を知っておくことは欠かせません。形式によって必要な経費は大きく異なるため、あらかじめ概算を把握しておくことで無理のない計画につながります。
| 葬儀形式 | 参列範囲・参列人数の目安 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 一般葬 | 親族・友人・会社関係者など 60〜100人程度 |
約150万円前後 |
| 一日葬 | 親族・友人など 20〜40人程度 |
約90万〜100万円前後 |
| 家族葬 | 親族中心 10〜25人程度 |
約80万〜90万円前後 |
| 直葬 | ごく近しい人のみ 20人程度 |
約45万円前後 |
費用は参列者の人数や地域、会場の規模によって増減する場合がありますが、おおよその相場を知っておくことで資金の準備や形式の選択がしやすくなります。
また、葬儀費用には祭壇や会場費のほか、返礼品や食事代なども含まれるため、総額でどの程度になるのかを把握することが大切です。
葬儀の形式や規模を決めたら、次に考えておきたいのが費用の備えです。あらかじめ資金の準備方法を検討しておけば、残されたご遺族の経済的な負担を軽減し、安心して葬儀を進めることができます。
ここでは、預金や生前契約、葬儀保険、信託など、代表的な資金準備の方法について解説します。
最も身近な葬儀資金の準備方法は、普段の預金から葬儀費用を確保しておくことです。ただし注意したいのは、名義人が亡くなると銀行口座は凍結され、自由に引き出せなくなる点です。相続手続きが完了するまで口座が使えないため、「いざという時に資金がすぐに下ろせない」という状況も起こり得ます。
その対策として、2019年の民法改正により「預貯金の仮払い制度」が設けられました。これは、相続人であれば金融機関ごとに上限150万円まで、かつ相続分の範囲内で一部を引き出せる制度です。ただし手続きには戸籍謄本などの書類が必要となり、すぐに全額を利用できるわけではありません。
こうした事情を踏まえると、葬儀費用として必要な金額の一部を現金として手元で保管しておくという方法もあります。
なお、故人の預貯金を葬儀費用に充てる際には、相続放棄の可否や相続税控除の対象といった税務上の取り扱いにも注意が必要です。領収書や明細を残し、専門家に相談しながら進めることでトラブルを防ぐことができます。
近年注目されている方法のひとつに、葬儀社との「生前契約」があります。これは、あらかじめご自身の希望に沿った葬儀プランを決め、契約を交わしておく仕組みです。
祭壇や会場の種類、参列者の範囲、葬儀内容などを具体的に取り決めておけるため、ご遺族はその契約内容に基づいて準備を進めるだけで済みます。
生前契約の大きな利点は、費用と内容が明確になることです。事前に見積もりを確認できるため「思っていた以上に高額だった」「希望と違う内容になってしまった」といったトラブルを防ぐことができます。また、ご自身の意思がしっかり反映されるため、希望通りの葬儀を実現しやすいのもメリットです。
一方で、契約後に状況や考え方が変わることもあるため、契約内容を定期的に見直すことが大切です。解約や変更の条件についても事前に確認しておくと安心でしょう。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀の生前予約「アンシア」をご用意しています。入会金・年会費無料にて、ご希望の葬儀内容を事前に登録できるため、ご家族の負担を軽減しながら安心して備えることができます。
預貯金や生前契約以外の方法として、葬儀保険や信託を活用する備え方もあります。
葬儀保険(終活保険)は、万が一の際にあらかじめ設定された保険金が支払われ、葬儀費用をまかなえる保険商品です。掛け金は月々2,000円〜3,000円程度と手頃で、高齢者でも加入しやすいのが特徴です。必要な時に迅速に保険金が支払われるため、ご遺族が費用を立て替える負担を軽減できます。
一方で、掛け捨て型が主流で解約返戻金がない、加入時期によっては支払総額が保険金額を上回る場合があるなどの注意点も理解しておくことが大切です。
また、銀行などの金融機関に一定の資金を預け、葬儀時に直接葬儀社へ支払う仕組みを「葬儀信託」といいます。口座凍結や相続手続きの影響を受けずに、必要な費用がスムーズに支払える点が大きなメリットです。
どちらの方法も、ご家族に負担をかけずに確実に資金を用意できる手段として注目されています。契約内容や保障範囲、解約条件などを十分に比較検討し、ご自身に合った方法を選びましょう。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀費用に備えるための「葬儀保険」をご案内しています。月々の負担を抑えながら必要な費用を準備でき、ご家族の安心にもつながります。
葬儀を安心して任せるためには、信頼できる葬儀社を選ぶことが欠かせません。近年は小規模葬や多様なプランが増え、葬儀社によって提供内容や料金体系もさまざまです。
そこで、ここでは葬儀社選びの際に注目した4つのポイントを紹介します。
葬儀社を選ぶ際には、まず「自分の希望する葬儀が実現できるか」を確認することが重要です。一般葬から家族葬、一日葬、直葬まで、形式ごとの取り扱いは葬儀社によって異なります。また、祭壇のデザインや音楽・映像の演出、返礼品や食事の内容など、細やかな部分まで希望に対応できるかも比較のポイントとなります。
とくに「菩提寺の僧侶に依頼したい」「無宗教で進行してほしい」など宗教的な要望や、「生花を多く使いたい」といった演出面の希望は、事前に伝えて対応可能か確認しておくと安心です。契約前に希望を整理し、具体的に相談しておくことで、ご自身の意向に沿った葬儀を実現しやすくなります。
葬儀社を決める際には、担当者の人柄や対応力も大切な判断基準となります。相談の際に質問へ丁寧に答えてくれるか、不安や疑問に寄り添った提案をしてくれるかを確認しましょう。形式的な説明だけでなく、要望に応じた具体的な提案があるかどうかも信頼度の目安になります。
また、見積もりやプランの説明がわかりやすく、必要に応じて代替案を示してくれる担当者であれば、万が一のときも安心して任せることができます。
葬儀はご遺族にとって大切な別れの儀式であり、不測の事態にも柔軟に対応できるスタッフがいるかどうかは重要なポイントです。経験豊富なスタッフが在籍していれば、宗派ごとの作法や地域の慣習にも精通しており、安心して任せることができます。
また、参列者の人数が予想より多く集まった場合や、進行上の変更が必要になった場合にも、豊富な実績があるスタッフなら冷静にサポートしてくれます。トラブルを未然に防ぎ、細やかな心配りができるかどうかは、実際に相談や見学の場で確認するとよいでしょう。
葬儀社を選ぶ際には、提示される見積もりの内容が明確であることが重要です。
基本料金に何が含まれているのか、追加費用がどのように発生するのかを確認しておかないと、最終的に想定外の金額になることもあります。祭壇費用や会場使用料、返礼品、食事代など、内訳を細かくチェックし、納得できる内容かを判断しましょう。
また、一社だけで判断するのではなく、複数社から資料を取り寄せて見積もりを比較するのがおすすめです。同じ葬儀形式でも料金や含まれるサービスが異なるため、比較することで自分の希望に合ったプランを見極めやすくなります。
費用面だけでなく、担当者の対応や式場の雰囲気も合わせて確認し、総合的に納得できる葬儀社を選びましょう。
メモリアルアートの大野屋では、相談窓口やオンライン相談を通じて葬儀の事前相談を受け付けています。費用や葬儀内容のご希望など、お気軽にご相談ください。
終活の取り組みとして注目されているのが「エンディングノート(終活ノート)」です。自身の葬儀や納骨の希望、医療や介護の意向、財産や連絡先などをエンディングノートに記しておくことで、ご遺族の負担を軽減できます。
エンディングノートは遺言書と異なり、法的効力はありませんが、形式の決まりがなく自由に書けるのが特徴です。気軽に始められる終活ツールとして、考えを整理したり家族へのメッセージを残したりするのに役立ちます。
| エンディングノート | 遺言書 | |
| 法的効力 | なし | あり(相続・財産分与に影響) |
| 記載内容 | 葬儀や医療の希望、連絡先、メッセージなど自由 | 財産分与、遺産相続など法定事項中心 |
| 書式 | 自由(市販ノート・自作可) | 自筆証書や公正証書など法定形式が必要 |
| 利用目的 | 家族への意思伝達・準備を助ける | 財産の承継を法的に指定する |
エンディングノートは自由に記せる分、何を残すべきか迷う方も多いものです。
必要な情報や希望を書き残しておけば、ご家族が判断に迷わずに済み、精神的・実務的な負担を軽減できます。さらに、自分らしい最期を迎えるための意思を形に残すことにもつながります。
ここでは、記録しておくと役立つ代表的な項目を紹介します。
エンディングノートの最初に記しておきたいのが、ご自身の基本情報です。氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先など、身分証や各種手続きに必要となる項目をまとめておけば、役所や金融機関での手続きがスムーズになります。
また、勤務先や加入している保険、年金の情報なども記録しておくと、ご家族が必要な連絡や確認を行いやすくなります。あわせてマイナンバーカードや健康保険証の保管場所なども記しておくと、遺された方が探し回る手間を省けるでしょう。
現在の健康状態を記録しておくことも、ご家族にとって大きな助けになります。持病や既往歴、服用している薬の名前や用量、かかりつけ医や通院している病院の情報をまとめておけば、急な体調変化や万が一の際に適切な対応がしやすくなります。
また、延命治療や緩和ケアに関する希望がある場合は、その意思も記しておくと安心です。「延命処置は望まない」「自宅で療養したい」などの考えを事前に伝えておくことで、ご家族が判断に迷う場面を減らすことができます。
財産に関する情報を整理しておくことは、相続や各種手続きを円滑に進めるために欠かせません。預貯金の口座、保険証券、不動産の有無、株式や投資信託などの金融資産を一覧にしておけば、ご家族が把握しやすくなります。
また、借入やローンなどの負債がある場合も正直に記しておくことが大切です。資産と負債を明確にすることで、相続の際にトラブルを避けられるだけでなく、ご家族が適切に判断できる材料となります。
さらに、印鑑や権利証、保険証券など重要書類の保管場所を明示しておけば、探す手間や手続きの遅れを防ぐことができます。財産の情報をエンディングノートに整理しておくことは、ご家族に安心を与えるだけでなく、スムーズな相続手続きにも直結します。
エンディングノートには、葬儀や納骨に関する具体的な希望も記しておくと安心です。葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬など)、参列していただきたい範囲、式場や宗教者への依頼方法などをあらかじめ示しておけば、ご家族は迷わず準備を進められます。
また、納骨の方法についても、従来のお墓に入るのか、納骨堂や永代供養墓、樹木葬、散骨といった選択肢の中から希望を明確にしておくことが大切です。納骨先を決めておくことで、ご家族は急な判断を迫られることなく、故人の意思を尊重できます。
近年はさまざまな契約やサービスが日常生活に組み込まれており、亡くなった後には多くの解約手続きが必要になります。公共料金や電話、インターネット、各種サブスクリプションサービス、クレジットカードや会員サービスなどは、放置すると料金が発生し続けてしまうため注意が必要です。
エンディングノートに契約しているサービスやカードの一覧、IDや連絡窓口を書き残しておけば、ご家族が速やかに解約手続きを進められます。特にデジタルサービスは利用者本人以外が把握しにくいため、ログイン方法や問い合わせ先を簡潔に整理しておくことが大切です。
こうした情報をまとめておくことで、ご家族の負担を大きく減らすとともに、不要な費用の発生や契約のトラブルを防ぐことができます。
葬儀やその後のご報告にあたり、親しい方々への連絡先をまとめておくことも大切です。特に、友人や恩師、かつての職場の同僚などは、ご家族が把握していないことも多く、連絡が行き届かないケースが少なくありません。
エンディングノートには、氏名・続柄・電話番号やメールアドレスなどを記録しておくと安心です。あわせて「ぜひ葬儀に参列してほしい」「訃報だけ伝えてほしい」など、ご自身の希望も書き添えておけば、より確実に意思を反映できます。
エンディングノートは、一度書いて終わりではなく、ライフスタイルや考え方の変化に合わせて更新していくことが大切です。最初から完璧に仕上げる必要はなく、取り組みやすい項目から始めることで継続しやすくなります。
ここでは、書き進める際の具体的なコツと注意点をご紹介します。
エンディングノートは、最初からすべてを埋める必要はありません。氏名や連絡先などの基本情報や、持病やかかりつけ医など日常的に把握している内容から始めると取り組みやすくなります。
書き進めるうちに自然と他の項目にも手が伸び、無理なく全体を整えることができます。
エンディングノートは一度書けば終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。家族構成や健康状態、財産内容は時間とともに変化するため、年末年始や誕生日など節目の時期に確認する習慣を持つとよいでしょう。
常に最新の情報を残しておくことで、ご家族が迷わずに対応でき、自分の意思を確実に反映することにつながります。
エンディングノートは書くだけでなく、必要なときに見つけてもらえるよう保管場所を家族に伝えておくことが大切です。
金庫や引き出しなど安全な場所に保管し、信頼できる家族に所在を知らせておけば安心です。所在が分からないと活用されないため、保管場所の共有も忘れずに行いましょう。
エンディングノートは、あくまでご自身の思いや希望を伝えるための記録であり、遺言書のような法的効力は持ちません。そのため、財産分与や相続に関しては遺言書を作成する必要があります。
ノートに記す内容は「家族に伝えるメッセージ」として整理し、法的手続きが必要な事項は専門家に相談するのがおすすめです。
各種サービスのログインに必要な暗証番号やパスワードですが、エンディングノートに直接書き残すのは避けましょう。
流出や不正利用のリスクがあるため、ノートには「どのサービスを利用しているか」や「保管場所」などの手がかりだけを記し、実際の番号は別の安全な方法で管理するのが望ましいです。また、専用のデジタル遺品サービスやパスワード管理ツールを利用するのも有効です。
葬儀は多くの場合、ご遺族が短期間で決めなければならないことが多く、残された方の大きな負担となります。だからこそ、生前にご自身の希望を整理し、資金や葬儀社を準備しておくことは、ご家族への思いやりであり、自分らしい最期を実現するための大切な備えといえるでしょう。
エンディングノートに想いを残し、費用や手続きの準備を整えておけば、残された方々が迷わずに対応でき、安心して故人を見送ることができます。
葬儀準備や終活は特別なことではなく、どなたにとっても大切なライフプランの一部です。無理のない範囲から一歩を踏み出し、自分らしい最期を迎える準備を進めてみてはいかがでしょうか。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。