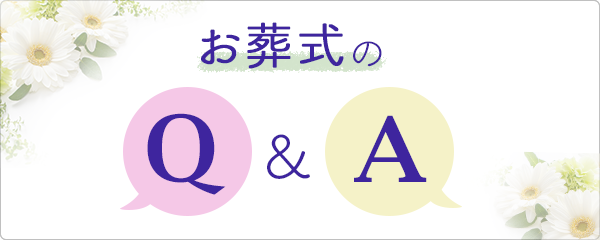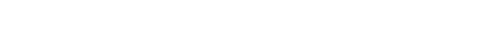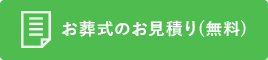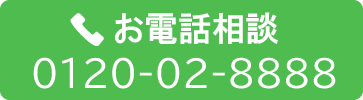通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/06/27
更新日:2025/07/08

 目次
目次臨済宗は、日本三大禅宗のひとつとして知られる仏教宗派です。鎌倉時代に栄西が伝えた禅の教えは、坐禅を通じて自らの仏性に気づき、悟りを得ることを目的としています。その精神は葬儀にも色濃く反映されており、他の宗派とは異なる儀礼や作法が行われます。
本記事では、臨済宗の歴史や教義の背景に触れながら、葬儀の流れや特徴、数珠や焼香のマナー、戒名・お布施の考え方、仏壇の飾り方まで詳しく解説します。葬儀に参列される方や臨済宗での葬儀を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
● 臨済宗の歴史や主な教えを知りたい方
● 臨済宗の経典(お経)や礼拝について知りたい方
● 臨済宗の葬儀・葬式の流れを知りたい方
● 臨済宗の葬儀におけるマナーや作法を知りたい方
● 臨済宗の戒名について知りたい方
● 臨済宗のお布施の相場を知りたい方
臨済宗は、曹洞宗や黄檗宗と並ぶ日本三大禅宗のひとつであり、坐禅による修行を通じて悟りを目指す「禅宗」に分類される仏教宗派です。中国・唐の時代に臨済義玄(りんざいぎげん)によって開かれ、その後宋代に体系化されました。
日本には鎌倉時代初期、僧・栄西(えいさい・ようさい)によって臨済宗の教えが伝えられました。栄西は宋から帰国後、1195年に日本初の禅寺「聖福寺」を博多に建立し、さらに建仁2年(1202年)には京都に建仁寺を創建。これらの寺院を拠点に、臨済宗は武士階級を中心に広がり、鎌倉幕府や室町幕府からも厚い庇護を受けました。
臨済宗の教えは、剣術や茶道、芸術などの文化にも影響を与え、日本の精神文化の礎を築いたともいわれます。特に坐禅による厳しい修行と師弟による「禅問答(公案)」を重視する点が特徴です。
江戸時代には、白隠慧鶴(はくいんえかく)によって大衆向けに再興され、今日までその教えは継承されています。
臨済宗は現在、14の宗派に分かれており、それぞれが本山を有しています。各宗派は、その本山の寺院名を冠しており、日本各地に歴史的・文化的に重要な寺院が存在しています。
以下は、臨済宗の14宗派と本山の所在地一覧です。
さらに、臨済宗の本山に関連する寺院の中には、金閣寺(鹿苑寺/相国寺派)や銀閣寺(慈照寺/相国寺派)、龍安寺(妙心寺派)といった、世界遺産に登録されている著名な寺院も含まれており、信仰の場としてだけでなく、日本文化を体現する存在としても高く評価されています。
臨済宗は、坐禅による修行を通じて「悟り」を得ることを目指す禅宗の一派です。その根幹には、「自らの仏性(ぶっしょう)に気づき、現実世界の中で真理を体得する」という厳格な教えがあります。
臨済宗では、「不立文字(ふりゅうもんじ)」という考え方を重視します。これは、仏の教えは文字や言葉に頼らず、師から弟子へと直接心で伝えられるべきものとする教えで、さらに「以心伝心(いしんでんしん)」という言葉でも表現されます。
また、修行の中心に据えられるのが「看話禅(かんなぜん)」です。これは、師が弟子に「公案(こうあん)」と呼ばれる問いを与え、それに対して単に理屈で答えるのではなく、坐禅を通して身体と精神を統一し、自ら真理に至ることを求めるものです。
このように、臨済宗の教えは厳しくも実践的であり、単なる知識ではなく、行動と思索によって仏の境地を目指す点に特徴があります。
臨済宗では、特定の本尊(信仰の中心となる仏さま)を定めていません。これは「不立文字」「悟りは自らの内にある」という禅宗の教えに基づくものです。
ただし、多くの寺院では「釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」を本尊としてまつることが一般的です。また、宗派や寺院によっては「薬師如来(やくしにょらい)」や「観音菩薩(かんのんぼさつ)」などをまつっている場合もあります。
臨済宗では、読経の前などに「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」という言葉を唱えることがあります。この言葉は「お釈迦さまに帰依します」という意味で、坐禅や仏事の場面で使われます。
ただし、浄土宗や真言宗のように特定の念仏や真言を繰り返し唱えることはありません。
臨済宗には、特定の根本経典(もっとも重要とされるお経)は存在しません。これも「不立文字」の教えを反映したものです。
ただし、仏事や葬儀の際には「般若心経(はんにゃしんぎょう)」や「観音経(かんのんぎょう)」、「大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)」などが読まれるのが一般的です。また、禅の精神を詠んだ和讃としては、白隠禅師による「坐禅和讃」も広く知られています。
臨済宗では、礼拝における所作も修行の一環と考えられており、心と体を整え、仏に敬意を示すための重要な行いとされています。
代表的な礼拝の形式として、以下の5つの所作があります。
・低頭(ていず)
立ったまま静かに頭を下げる礼です。仏前での基本的な敬意の表し方であり、日常的にも用いられる丁礼の一種です。
・胡跪(こき)
片膝を立ててひざまずく姿勢で礼をする方法です。坐礼と立礼の中間のような動作で、より丁寧な礼を意味します。
・揖(いつ)
「叉手(しゃしゅ)」という、右手を胸にあて、その上から左手を重ねる手の形を保ちつつ、軽く上体を倒して礼をします。静けさの中に深い敬意を込めた動きです。
・門訊(もんじん)
合掌したまま、深く頭を下げる礼です。両手を合わせた姿勢で仏に向き合い、感謝や祈りを捧げる基本動作です。
・大門訊(だいもんじん)
合掌した両手を円を描くように大きく動かしながら、深く頭を下げる礼です。仏に対する最大限の敬意を表す動きとされ、特別な場面で用いられます。
これらの礼法は、単なる形式ではなく、仏と向き合う心構えを体現するものです。葬儀や法要、坐禅の前後などの場面で実践されることで、より深い信仰と精神の集中を促す所作とされています。
臨済宗の葬儀は、亡くなった方が仏弟子としての道を歩み、悟りの境地へと至るための大切な儀式です。
その流れは大きく「授戒」「念誦」「引導」の3つの段階に分かれており、それぞれに深い宗教的意味が込められています。以下では、各儀式の内容と意義について詳しく解説します。
授戒は、故人に仏の戒律を授け、仏門に正式に入るための儀式です。臨済宗では、死後の仏弟子化を重視しているため、故人が悟りに向かう準備としてこの儀式が厳かに行われます。
・剃髪(ていはつ)
形式的に髪を剃るしぐさを行い、僧侶が「剃髪の偈(ていはつのげ)」を唱えます。これは世俗から離れ、仏門に入る決意の象徴です。
・懺悔文(さんげもん)
故人が生前の過ちを悔い改め、清らかな心で仏道へ進むための誓いの言葉を捧げます。
・三帰開門(さんきかいもん)
仏・法・僧の三宝に帰依し、仏弟子としての門を開く儀式です。
・三聚浄戒(さんじゅうじょうかい)
仏教の実践者として守るべき基本の三つの戒(戒律)を授かります。
・十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)
殺生や盗みなど十の基本的な禁戒を唱え、清浄な生を送ることへの誓いを新たにします。
・血脈授与(けちみゃくじゅよ)
「血脈」と書かれた紙を霊前に供える儀式です。これは仏法の系譜を継ぐ仏弟子として認められた証とされます。 地域・寺院によっては、血脈授与の儀式が省略されることもあります。
念誦は、導師(僧侶)が仏教の経典を読誦しながら、故人を仏の教えの世界へと導くための儀式です。以下の4段階の儀式で進行します。
・入龕諷経(にゅうがんふぎん)
故人を棺に納める際に行う読経で「大悲心陀羅尼」や「回向文」を唱え、冥福を祈ります。
・龕前念誦(がんぜんねんじゅ)
棺の前で十仏名などの経文を読み上げ、故人の安寧と仏道成就を祈念します。
・起龕諷経(きがんふぎん)
出棺の際に行われる読経で、入龕時と同様に「大悲心陀羅尼」や「回向文」が唱えられます。
・山頭念誦(さんとうねんじゅ)
火葬場などで行う最後の読経で、「往生咒(おうじょうしゅ)」を唱えながら鈸(ばつ)や太鼓を打ち鳴らし、故人の成仏を祈ります。
引導は、故人を現世から仏の世界へ導くための儀式です。臨済宗の葬儀の中でも、特にこの工程が重視されます。
・引導法語(いんどうほうご)
導師が法語を唱え、故人の魂に仏道への道筋を示します。臨済宗では、法語の最後に導師が「喝!」と一喝するのが特徴です。これは、故人の迷いを断ち切り、悟りへ導くための重要な行為とされています。
・焼香
導師や参列者が焼香を行い、故人の冥福を祈ります。焼香の際には「観音経」や「大悲心陀羅尼」などが読誦されるのが一般的です。
・出棺
葬儀の最後に棺を送り出す儀式です。導師が回向文を唱えながら、故人を見送り、火葬場へと向かいます。
臨済宗の葬儀では、各工程が仏道修行としての意味を持ち、故人が悟りの道を歩むことを願って一つひとつ丁寧に執り行われます。参列者もまた、故人の旅立ちに心を寄せながら、それぞれの作法に真心を込めて参加することが大切です。
臨済宗の葬儀では、宗派独自の儀礼や考え方に基づいた作法がいくつか存在します。特に、数珠の使い方や焼香の所作、香典の表書きといった基本的なマナーを理解しておくことで、葬儀に落ち着いて臨むことができます。
ここでは、参列者が知っておきたい主なマナーについてご紹介します。
臨済宗で正式とされる数珠は「看経念珠(かんきんねんじゅ)」と呼ばれる本式念珠です。主玉108個、天玉4個、親玉1個から成る二重輪構造で、銀輪はありません。男女とも形状は同じですが、男性用は紐房、女性用は頭付房が使われるのが一般的です。
正式な場ではこの本式数珠を用いるのが理想とされていますが、一般の参列者は、略式数珠を持参しても問題ありません。
数珠を持つ際は、数珠の一重輪をひねって二重にし、左手の親指と人差し指の間にかけて合掌します。その際、房は下に垂れるようにし、手のひらで包むように持ちます。
臨済宗の焼香作法は比較的シンプルで、以下の流れが一般的です。
① 仏前に進み、合掌して軽く一礼する
② 親指・人差し指・中指の3本で抹香をつまむ
③ 額に押しいただかずに、そのまま抹香を香炉へ静かにくべる
④ 再び合掌・一礼し、静かに席へ戻る
焼香の回数は1回が基本ですが、寺院や地域によっては2回、3回と指示されることもあります。迷った場合は、葬儀社のスタッフや僧侶の指示に従うといいでしょう。
線香を用いる場合は、1本だけを立てて供えるのが通例です。火をつけたあとは、手であおいで火を消すか、線香を軽く振って消すようにし、息で吹き消さないように注意しましょう。
臨済宗の香典の表書きは、他の仏教宗派と大きな違いはなく、基本的なマナーを守っていれば問題ありません。
四十九日以前の場合は「御霊前」または「御香典」、四十九日以降の法要では「御仏前」を用いるのが一般的です。
水引は黒白や双銀の結び切りを選び、表書きは薄墨を使って楷書で丁寧に記しましょう。
金額は地域や関係性により異なりますが、一般的な仏式葬儀の相場に準じます。新札は避け、一度折って使用するなど、悲しみの場にふさわしい心配りも大切です。
臨済宗の葬儀では、故人に「戒名(かいみょう)」を授けることが非常に重要な意味を持ちます。戒名とは、仏門に入った証として与えられる名前であり、故人が仏の弟子として新たな人生を歩む存在であることを示すものです。
臨済宗においても他の禅宗と同様、戒名は「授戒(じゅかい)」の儀式の一環として授与されます。これは、故人が仏教の戒律を守る修行者として正式に認められたことを意味し、成仏への第一歩とされています。
戒名の構成は、一般的に以下の4つの要素から成り立ちます。
・院号(いんごう)
高位の戒名に付される称号で、社会的功績や信仰の厚さが評価された場合に授けられます。
・道号(どうごう)
仏道修行者としての人格や精神性を象徴する語句で、故人の人柄や生前の生き方が反映されます。
・戒名(本名部分)
仏門に入ったことを表す新たな名前で、在家信徒としての故人の魂を表現する中心的な部分です。
・位号(いごう)
性別や地位に応じて末尾に付けられる称号で、男性は「信士」「居士」、女性は「信女」「大姉」などが用いられます。
なお、葬儀の際に使用される仮位牌(白木位牌)には、戒名の上部に「新帰元(しんきげん)」という文字が刻まれるのが臨済宗の一般的な形式です。「新帰元」とは、「新たに仏の元(真理の世界)へ帰る」という意味を持ち、禅宗に特有の言葉として、故人の魂が迷いなく仏道へ向かうことを願う表現とされています。
臨済宗に限らず、仏教葬儀において僧侶にお渡しする「お布施」は、読経や戒名授与などの仏事に対する感謝の気持ちを表す大切な行為です。お布施に明確な金額の決まりはありませんが、一定の目安を把握しておくと準備しやすいでしょう。
一般的に、臨済宗の葬儀におけるお布施の相場は15万円〜50万円程度とされています。この金額には、通夜・葬儀の読経料や戒名料が含まれているのが一般的ですが、寺院の格式や地域性、また戒名の位によって大きく異なります。
戒名の位が高くなる場合や、院号を付ける場合などは、50万円〜100万円以上になるケースもあります。加えて、僧侶の交通費にあたる「お車代」や、通夜振る舞いなどを辞退された場合の「御膳料」を別途包むのが通例です。
お布施は白無地の封筒または奉書紙にお包みし、表書きとして「御布施」と記します。裏面または中袋には施主の氏名と金額を記入します。お布施を渡す際は、袱紗(ふくさ)に包んで持参したうえで、切手盆などに乗せて丁寧にお渡しするのがマナーです。
金額に関して迷った場合は、あらかじめ葬儀社や菩提寺に相談しておくといいでしょう。形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを込めて丁寧に対応することが大切です。
臨済宗では、教義上特定のご本尊を定めていませんが、実際の供養や礼拝の場では、仏壇の中央に「釈迦牟尼仏」を本尊として安置するのが一般的です。仏壇は、日々手を合わせる大切な場所であり、仏教への敬意と先祖供養の心を形にする場でもあります。
臨済宗には14の分派があり、仏壇の飾り方にも違いがあります。たとえば、妙心寺派では本尊の両脇に「無相大師(むそうだいし)」と「花園法皇(はなぞのほうおう)」の掛け軸を飾るのが通例です。建長寺派や円覚寺派などでは、開山の祖師や「達磨大師(だるまだいし)」を脇侍とする場合もあります。
仏壇には、香炉・燭台・供花を基本に、ご飯・水・果物などを清潔に供えます。細かな飾り方は分派や地域によって異なるため、菩提寺に確認するといいでしょう。
臨済宗は、坐禅による修行と師から弟子への直接的な伝達を重んじる、実践的かつ精神性の高い仏教宗派です。その教えは葬儀にも色濃く反映されており、一つひとつの儀式に深い意味が込められています。
葬儀に参列される方やご家族を見送る立場の方にとって、臨済宗の教義や葬儀の流れ、数珠・焼香・香典のマナーを知っておくことは、心を込めて儀式に向き合うための大切な準備となります。また、仏壇の飾り方や戒名・お布施に関する基礎知識も、安心して故人をお見送りするうえで役立つでしょう。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。