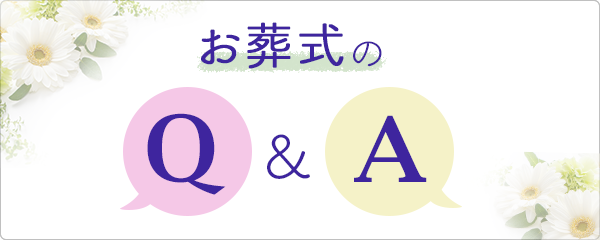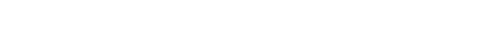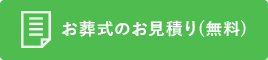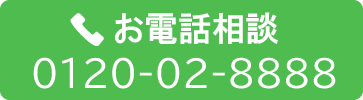通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/06/12
更新日:2025/07/08
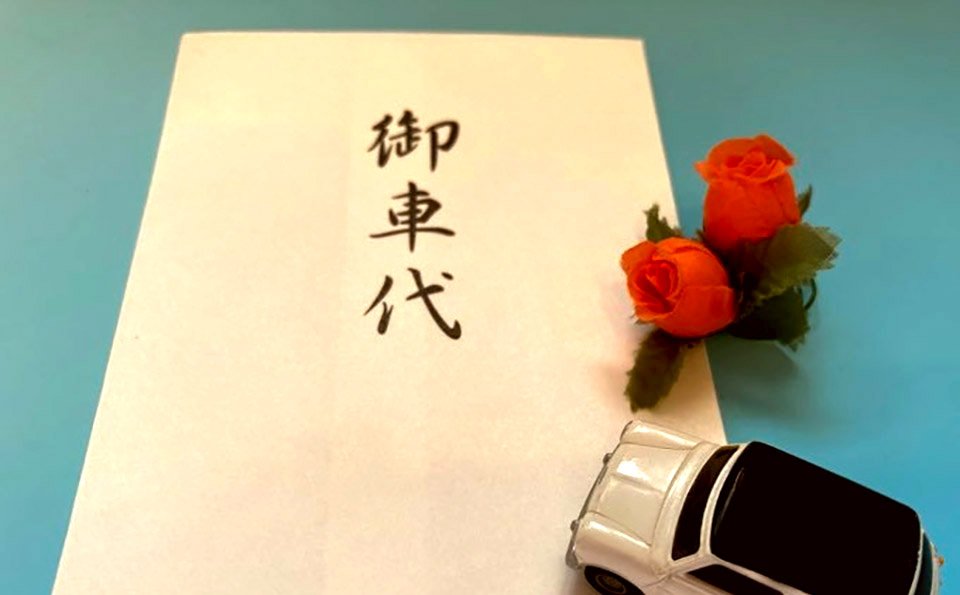
 目次
目次葬儀や法要で僧侶にお車代をお渡しする際に「どれくらい包めばよいのか」「どんな封筒を選べば失礼がないか」「お布施や御膳料とはどう違うのか」などでお悩みの方も多いでしょう。
そこで本記事では、お車代の基本的な意味と役割、お布施・御膳料との違い、必要・不要のケースをわかりやすく解説します。さらに、お車代の金額相場や封筒の選び方、表書きのポイント、お札の入れ方、お車代の渡し方など、葬儀での謝礼マナーもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
● お車代の意味や役割を知りたい人
● お車代とお布施・御膳料の違いを知りたい人
● お車代が必要なケース・不要なケースを知りたい人
● お車代の金額相場を知りたい人
● お車代の封筒選びや渡し方などのマナーを知りたい方
お車代とは、葬儀や法要の際に、僧侶などの宗教者が会場に来るためにかかった交通費相当を包んでお渡しする謝礼のことです。移動にかかった実費に感謝の気持ちを添え「お車代」または「御車代」として封筒にお包みして渡します。
お車代と似ているものに「お布施」や「御膳料」があります。これらはいずれも僧侶にお渡しする金銭ですが、意味や目的が異なります。
お布施
お布施とは、読経や戒名授与など、宗教的儀式を執り行っていただく対価として渡す謝礼金のことです。金額はサービスに対する「感謝の気持ち」として包むため、明確な相場はなく、宗派や地域、儀式の規模に応じて幅広く設定されます。
御膳料
御膳料とは、通夜振る舞いや精進落としなどの会食に僧侶が参加しない場合に、その飲食代相当としてお渡しするものです。会食を用意しない場合や僧侶が会食に参加される場合は用意する必要がありません。
また、神式の葬儀ではお布施の代わりに「祭祀料」を、また神様にお供えする金銭である「玉串料」を用意します。
葬儀の際にお車代を用意するべきかどうかは、僧侶の移動手段や会場の場所によって異なります。ここでは、お車代が必要なケースと不要なケースについて、詳しく見ていきましょう。
葬儀を寺院以外の斎場や自宅で執り行う場合、僧侶は自家用車やタクシー、公共交通機関を利用して会場に来られるのが一般的です。この場合は、移動にかかった実費をお車代として包むのがマナーです。
葬儀を僧侶の所属する寺院内で行う場合は、移動が発生しないためお車代のお渡しは不要です。また、喪主やご親族が自家用車やチャーターしたタクシー・ハイヤーで僧侶を送迎する場合も、遺族側で既に交通費を負担しているため、お車代を別途包む必要はありません。
お車代の相場は5,000円〜10,000円程度が一般的です。交通費の実費を目安にしつつ、謝意を添える形で「実費+α」のキリの良い金額に調整します。たとえば実際の交通費が4,300円の場合は5,000円、7,200円なら8,000円や10,000円、といった金額を用意します。
ただし、地域ごとにタクシー初乗り運賃や公共交通機関の料金体系が異なるため、同じ移動距離でも必要となる金額に差が出ます。大都市圏では初乗り運賃が安めの代わりに加算単価が高い場合があり、地方では初乗りが高く加算単価が低い場合があるため、事前におおよその金額を調べておくといいでしょう。
また、遠方からお招きする僧侶の宿泊が必要な場合は、交通費とは別に「宿泊代」も用意します。宿泊代は実費精算が基本ですが、地域や旅館の等級に応じた相場(1泊あたり8,000円〜15,000円程度)を目安にお包みします。
お車代を準備する際は、金額だけでなく、封筒の種類や書き方、お札の入れ方といった細やかなマナーにも配慮が必要です。ここでは、葬儀の謝礼として失礼のないお車代の包み方・準備方法を解説します。
お車代を包む封筒は、郵便番号欄のない白無地の封筒を使用するのが基本です。
地域の慣習などで水引付きの不祝儀袋を使う場合は、結び切りの黒白もしくは双銀(白銀)を用いるのが一般的です。また、関西圏で一周忌以降の法要などでは、黄白の水引付きの不祝儀袋が使われることもあります。
表書きは薄墨ではなく、普通の濃墨で毛筆するか、または濃墨の筆ペンを用いて書きます。
上段中央に「御車代」または「お車料」と大きめに書き、下段に少し小さめの文字でフルネームまたは「〇〇家」と記載します。
裏面や中袋には、住所と金額を漢数字の大字(旧字体)で縦書きにします(5,000円なら金伍仟圓也、1万円なら金壱萬圓也など)。
なお、氏名の記入は宗派や地域によって省略する場合もあるため、悩んだ場合や事前に葬儀社に確認するといいでしょう。
お札を入れる際は、肖像画がある面を表にし、封筒表側の文字が読める向きにそろえて入れます。複数枚ある場合もすべて同じ向きにそろえましょう。
また、香典では新札を避けて用意するのが一般的ですが、お車代は僧侶への感謝を表すものなので、なるべく新札やきれいなお札を用意するのがマナーです。
中袋がある封筒を使用する場合も、お札の向きをそろえて中袋に入れてから封筒本体に入れます。また、中包み用の半紙がセットされている場合は、半紙でお札を包んだ上で封筒に入れてください。
最後に封筒をのり付けし、のり付け部分に「〆」と書きます。地域によっては封筒をのり付けしないケースもあります。
お車代は袱紗に入れて持参し、お渡しする際に袱紗から出します。
封筒を直接手渡しするのではなく、必ずお盆に乗せてお渡しします。切手盆と呼ばれる小さな黒塗りの礼盆を使用するのが一般的ですが、切手盆の用意が難しい場合は袱紗を広げてその上に封筒を乗せてお渡しする方法でも失礼にはあたりません。
お車代は、お布施と一緒にお渡しします。お布施の封筒を1番上に、お車代はお布施の封筒の下に重ねて乗せましょう。
お布施とお車代をお渡しするタイミングに明確な決まりはありませんが、葬儀前の控室での僧侶へのご挨拶時や、葬儀終了後に僧侶の控室や出口で渡すなどが一般的です。
お車代は、葬儀で儀式を行う僧侶などの宗教者にお渡しする交通費のことです。交通費の実費に加えて、感謝の気持ちを添えて、キリのいい金額を封筒にお包みしてお渡しします。ただし、僧侶の所属する寺院で葬儀を行う場合や、喪主が送迎を行う場合、喪主がチャーターしたタクシーやハイヤーを使用する場合は、お車代のお渡しは必要ありません。
お車代を用意する際は、封筒の選び方や表書きの書き方などにも注意しましょう。また、お渡しする際は切手盆を用いるなどのマナーもあるため、事前に流れを理解しておくといいでしょう。
この記事を参考に、お車代の意味や相場、お渡しする際のマナーを把握して、適切に備えておくことをおすすめします。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。