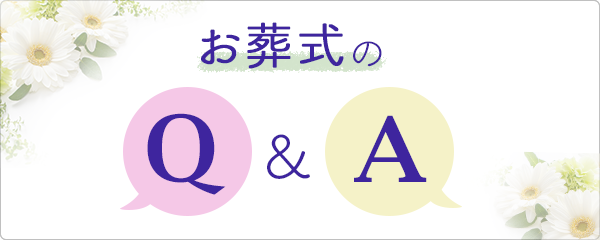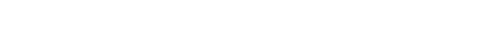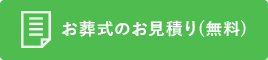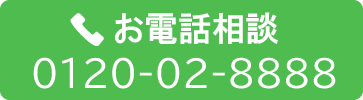通話無料・24時間365日対応
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
葬儀の申し込み・緊急相談・搬送の手配など24時間365日対応しております。事前のご相談がなくてもすぐに対応可能です。
ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。

公開日:2025/05/16
更新日:2025/05/16

 目次
目次葬儀の場に欠かせない「数珠」。私たちがご遺族や故人に手を合わせる際、心を整え、煩悩を清める役割を果たす大切な法具です。しかし、その形や素材、持ち方は宗派ごとに微妙な違いがあり、初めての方には選び方やマナーが分かりにくいのも事実でしょう。
そこで本記事では、数珠の起源や種類、本式・略式の違いから、宗派ごとの数珠の扱い方まで詳しく解説します。さらに、購入のポイントや日常のお手入れ、万が一の修理、そして供養・処分方法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
● 数珠(念珠)の意味や役割を知りたい方
● 数珠(念珠)の種類を知りたい方
● 数珠(念珠)の宗派ごとの違いを知りたい方
● 数珠(念珠)の選び方・購入方法を知りたい方
● 数珠(念珠)の持ち方を知りたい方
● 数珠(念珠)のお手入れ方法を知りたい方
● 数珠(念珠)の処分・供養の方法を知りたい方
数珠は、小さな珠(たま)を糸でつなぎ輪状にした仏具で、読経や念仏の回数を数えるために用いられます。仏教のお経や念仏を唱える珠という意味から、念珠とも呼ばれています。
心を落ち着け、手を合わせる際に身近な法具として欠かせない存在です。ここではまず、数珠の基本について解説していきます。
数珠の起源は、紀元2世紀頃のインドにまでさかのぼります。その始まりは、インドのバラモン教で用いられていた「連珠」と呼ばれる珠を使った道具だといわれています。その後、連珠のような道具は仏教にも受け継がれ、中国を経て日本へ八世紀頃に伝来したとされています。
数珠は、念仏やお題目を何度唱えたかを数える役割を持つと同時に、108個の珠が煩悩の数を象徴し、手にすることで心身を清める意味合いも担っているのです。
数珠には大きく分けて「本式数珠」と「略式数珠」の2種類があり、どちらも輪の構造を持ちながら用途や宗派に応じて区別されます。
本式数珠
本式数珠は、各宗派で定められた格式高い形式です。主に正式な法要やご自宅での仏事で用いられます。珠数は108玉が基本で、大きな「親玉」が1つ、少し小さめの「天玉」が4つ含まれています。
略式数珠
略式数珠は、本式数珠を簡略化したもので、宗派を問わず使えるシンプルな形状です。「片手念珠」とも呼ばれています。珠の数に厳密な決まりはありませんが、22玉や20玉、18玉、27玉、54玉などが一般的です。携帯性に優れ、初めて数珠を購入する方でも手に取りやすいでしょう。
上述のように、数珠の玉の数は人間の煩悩を表す「108玉」が基本です。本式数珠は108玉でつくられているものが多いですが、簡略化された略式数珠では厳密な決まりはなく、扱いやすい22玉や20玉、18玉、108の半分である54玉などが採用されています。
数珠の玉に用いられる素材には、以下のようなものが挙げられます。
・木(黒檀、紫檀、栴檀、屋久杉など)
・香木(白檀、沈香など)
・天然石(本水晶、虎目石、オニキス、翡翠など)
数珠の色には特別な決まりはありません。ただし、宗派によっては特定の素材や色が好まれる場合もあるため、宗派に合わせて選ぶといいでしょう。
また、数珠の房には以下のような種類があります。
・頭付房:最もポピュラーな形状。
・梵天房:丸い房が特徴で、ほどけにくく丈夫。
・紐房:紐状の房でシンプルな印象。
・かがり房、松風房:繊細な編み込みや美しいシルエットが特徴。
房の種類や色にも厳密な決まりはありません。ただし、宗派によっては特定の房の種類が好まれるケースもあります。
メモリアルアートの大野屋のオンラインWEBSHOPでは豊富な種類の数珠・念珠入れを取り揃えています。すぐに必要な方はぜひご覧ください。
各宗派には、それぞれの教義や儀礼に合わせた数珠の形式と作法があります。ここでは7つの代表的な宗派について、その概要と数珠の種類、持ち方をまとめます。
親鸞聖人が開いた浄土真宗は「阿弥陀仏の他力本願」による救済を説く宗派です。
浄土真宗の正式な数珠は「門徒数珠(もんとじゅず)」と呼ばれています。男性用は紐房付きの片手念珠(22玉や20玉、18玉)、女性用は蓮如結びを施した108玉の二重輪に五本の房を配した格式高い形式を用いるのが一般的です。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
合掌した両手の親指と人差し指の間にかけ、本願寺派は房を下に、大谷派は房を左側に垂らすのが基本です。
浄土宗は法然上人が開いた宗派で「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで、極楽浄土に往生できると説いています。
浄土宗の本式数珠には「日課数珠(にっかじゅず)」「百八数珠(ひゃくはちじゅず)」「荘厳数珠(しょうごんじゅず)」の3種類がありますが、お葬式の際は二重輪の「日課数珠」を用います。玉の数は108個ではなく、主玉と弟子玉などを配した独自のつくりになっており、男性と女性とで玉の数が異なります。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
合掌時は、二重輪を両親指にかけて房を手前に垂らし、読経や念仏、焼香の際には左手にかけたまま行うのが正式な作法です。
密教系の真言宗は、弘法大師・空海の教えに基づき即身成仏を説いた宗派です。真言宗は、仏教宗派の中でも数珠を重要視しています。
正式な数珠は「振分数珠(ふりわけじゅず)」と呼ばれ、主玉108個に親玉2個、四天玉4個を組み合わせ、梵天房が付された重厚な形式となっています。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
両手の中指に数珠の両端をかけ、そのまま合掌して房を外側に垂らします。念珠を擦り合わせながら唱題を行うこともあります。
道元禅師が開いた曹洞宗は、座禅修行を重んじ、日々の生活そのものを修行と捉える禅宗の一派です。
曹洞宗の数珠は「看経念珠(かんきんねんじゅ)」と呼ばれており、主玉108個に加え銀輪1個、天玉4個、男性は紐房、女性は頭付房を配した数珠が正式な形とされています。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
一重輪をひねって二重にし、左手の親指と人差し指の間にかけ、合掌時にはそのまま握って房を下に垂らします。
最澄が開いた天台宗は、一乗思想を基盤に顕教と密教の両側面を併せ持つ宗派です。
天台宗の正式な数珠は「大平天台(だいひらてんだい)」と呼ばれており、平玉を中心に108個の主玉が二重になった独特の形をしています。男性は9寸、女性は8寸が一般的です。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
人差し指と中指の間に数珠をかけ、そのまま手を合わせるようにして持ちます。房は下に垂らします。
日蓮宗は法華経を唯一の教典とし、南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」の題目を唱和することによる現世利益と救済を重視する宗派です。
日蓮宗の数珠は「勤行数珠(ごんぎょうじゅず)」と呼ばれるもので、主玉108個に親玉や天玉、数取玉などを配して二重にした独特の仕様になっています。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
輪を八の字にして、房が3本ある方が左に来るようにして両中指にかけ、そのまま合掌して房を左右の外側に垂らします。
臨済宗は、栄西が開いた禅宗の一派です。座禅で悟りを得る「自力」と、師弟による「公案」という問題提示を重視しています。
臨済宗の正式な数珠は「看経念珠(かんきんねんじゅ)」と呼ばれています。主玉108個、天玉4個、親玉1個からなる二重輪で銀輪はなく、男女とも同形ですが、男性用は紐房、女性用には頭付房が付されています。ただし、一般の参列者は略式数珠を用いても構いません。
数珠の持ち方
一重輪をひねって二重にし、左手の親指と人差し指の間にかけ、合掌時にはそのまま握って房を下に垂らします。
数珠は種類や用途を理解して選ぶことで、長く大切に使えます。ここでは宗派や性別、素材・価格帯、購入場所ごとに押さえておきたいポイントを解説します。
数珠を選ぶ際は、まずは「本式数珠」と「略式数珠」のどちらを購入するかを検討しましょう。本式数珠を購入する場合は、宗派ごとに形式が異なります。
宗派ごとの本式数珠の名前
浄土真宗:門徒数珠
浄土宗 :日課数珠
真言宗 :振分数珠
曹洞宗 :看経念珠
天台宗 :大平天台
日蓮宗 :勤行数珠
臨済宗 :看経念珠
宗派にこだわらず使用したい場合は、汎用性の高い略式数珠を選ぶといいでしょう。
男性用と女性用では珠の大きさや房の形が異なります。一般的に男性用は珠径10〜12mm前後、女性用は6〜8mmが主流です。
略式の片手念珠なら、男性は20〜22玉、女性は6mm・7mm・8mm玉の22玉前後がおすすめです。体格や手の大きさ、着物や洋装時のバランスも考慮して、腕や手にかけたときの見た目や携帯性をチェックしましょう。
また、男性であれば落ち着いた色の濃いブラウン系が定番です。ビジネスシーンや冠婚葬祭でも浮かないシックな色合いを選ぶと使い勝手が良いでしょう。女性の場合は、黒やグレーなどシックな色であればフォーマルに使えますが、淡いピンクやパステル系の天然石、クリアな水晶など、柔らかな色合いも人気です。
ただし、本式数珠を選ぶ際は、宗派ごとに男女での決まりが設けられていることもあるため、上述の「宗派別の数珠の違い」をご覧ください。
素材は木製(黒檀・紫檀・屋久杉など)、香木(白檀・沈香)、天然石(本水晶・オニキス・虎目石など)から選べます。
木製は軽く、使い込むほどに艶が増す風合いが魅力です。香木は仄かな香りがあり、心を落ち着かせてくれる効果も期待できます。また、天然石は色味や質感に高級感があり、石ごとの意味や効力を重視して選ぶ方もいます。
価格帯は2,000円台の手頃なものから数十万円の高価格なものまで幅広くそろっています。価格は、素材の希少性や製造方法(職人仕立てか量産品か)などによって変わるため、あらかじめ予算を決めて、比較しながら選びましょう。
数珠は仏具店や百貨店、ホームセンター、通販サイト、ネットショップなどで購入可能です。
仏具店には本式数珠などが豊富にそろっており、宗派や正式な作法について相談しながら選べるのがメリットです。百貨店やホームセンターでは、実物を見て購入できるメリットがありますが、店舗によっては品ぞろえが少ない場合もあります。
一方で、通販サイトやネットショップでは、自宅でゆっくりと商品を比較しながらの購入ができます。ただし、素材感や大きさなどを判断しにくい場合もあるため、レビューや実物写真をよく確認しましょう。
また、通販サイトやネットショップを利用する場合は、数珠に詳しい仏具店や葬儀社、寺院などの店舗を利用するのがおすすめです。
メモリアルアートの大野屋のオンラインWEBSHOPでは豊富な種類の数珠・念珠入れを取り揃えています。すぐに必要な方はぜひご覧ください。
お葬式に参列する際は、数珠の扱いにも気を配る必要があります。宗派ごとに細かな違いはありますが、持ち方などの基本作法は共通しています。ここでは、お葬式の際の数珠の使い方と基本的なマナーを解説します。
読経や合掌、焼香の際には、数珠を以下のように持つのが一般的です。
着席中・待機時
数珠を使用しないときは、左手首にかけておきます。
移動時
房(ふさ)を下に垂らしたまま、左手で数珠を軽くつかんで持ち運びます。
焼香中
左手の親指に数珠をかけ、房を下に垂らします。抹香を右手でつまみ、静かに香炉にくべたあと、左手に数珠をかけたまま合掌します。
合掌・読経中
両手を合わせるときは、房を下にした状態で両親指に数珠をかけます。または、数珠を左手にかけたまま、右手を添えて合掌します。
※数珠の持ち方・かけ方は宗派ごとに細かな作法が異なります。詳しくは「宗派別の数珠の違い」をご覧ください。
数珠は大切な仏具であるため、床や机のうえに無造作に置くのはマナー違反にあたります。お葬式の際は、数珠は常に左手に持つか左手にかけておくのが基本です。
数珠を一時的に手放す必要があるときも、床や机、椅子に直接置かず、袱紗(ふくさ)や数珠袋に入れてバッグの中にしまうなど、丁寧に扱いましょう。
数珠はご自身の信仰心を表す大切な仏具です。他人と貸し借りせず、参列者それぞれが自分の数珠を用意するのが望ましいとされています。急なお葬式でも対応できるように、あらかじめご自身の数珠を用意しておくことをおすすめします。
数珠は日々の勤行や法要で用いる大切な仏具です。長く使うためにも、適切な手入れと保管を心がけましょう。
日常のお手入れや保管では、次の3つのポイントを押さえましょう。
汚れを落とす
使用後は、柔らかい乾いた布で珠や房のホコリをやさしく拭き取ります。汚れがひどい場合は、水を含ませた布(お湯は避ける)で軽く拭き、すぐに乾いた布で水分を取り除いてください。
房を整える
房が乱れたら、指先でそっとほぐして形を整えます。髪の毛や繊維が絡まった場合は、ピンセットなどで丁寧に取り除きましょう。
乾燥・湿気対策
直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管します。湿気が気になる場合は、防湿剤をそばに置くとカビ予防になります。保管時は、形を整えてから、数珠が入っていた箱や専用の保管箱に入れておきましょう。
仏具としての数珠は「切れる」ことで煩悩が断ち切られる吉兆ともいわれます。また、自分の分身である数珠が「身代わりになってくれた」と捉えることもできます。
切れた数珠を修理する場合は、早めに専門店や寺院の数珠職人に依頼しましょう。1度切れてしまった数珠も、珠を1つ1つ外して新しい紐を通す「仕立て直し」が可能です。
または、切れた数珠をお寺に納めて供養してもらうという方法もあります。
不要になった数珠は、仏具としての「最後のお勤め」を行ってから手放すのが望ましいとされています。
数珠を手放すとき、法的・宗教的に定められた厳格なルールはありません。そのため、地域のルールに沿って、一般ごみとして処分することも可能です。
しかし、数珠は大切な仏具であり、ご自身を表すものでもあります。思い入れのある数珠を手放す場合は、ご自身で簡単な「お清め」を行ってから処分するといいでしょう。例えば、お経を唱えお清めの塩を振ってから、白い布や数珠袋に包んで処分するといった方法などです。
そのほか、寺院での引き取りや仏具店・購入店での回収サービスを利用する方法もあります。
数珠を正式に弔い供養する場合は、まずは菩提寺や近くの寺院に問い合わせを行い、数珠供養やお焚き上げの可否と費用を確認します。
供養の依頼が決まったら、数珠を袱紗(ふくさ)や白い布に包んで持参し、受付で供養の申し込みをします。読経やお焼香などの簡単な式次第ののち、数珠は丁寧に火にくべられるか、あるいは僧侶がお唱えしたあとに寺院内でお焚き上げされます。
供養の依頼料やお礼の金額は、寺社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。遠方で持参が難しい場合は、郵送での受付に対応している寺院もあるので、梱包方法や送料もあわせて問い合わせておくと安心です。
数珠は、複数の小さな玉に糸を通した仏具であり、仏事や葬儀の際に使用されます。数珠には、格式高い本式数珠と宗派を問わず使いやすい略式数珠の2種類があります。本式数珠は、宗派ごとに形式が異なるため、用意する際は宗派ごとの決まりを確認しておきましょう。
数珠の貸し借りはマナー違反とされています。そのため、急なお葬式の際も慌てずに済むよう、事前にご自身に合う数珠を購入しておくことをおすすめします。
メモリアルアートの大野屋のオンラインWEBSHOPでは豊富な種類の数珠・念珠入れを取り揃えています。すぐに必要な方はぜひご覧ください。